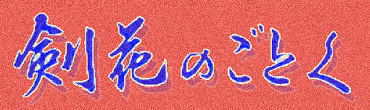 |
| 第 11 回 |
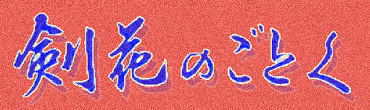 |
| 第 11 回 |
| 第 一 部 暁 闇 |
| (八) 旅 立 ち |
| 1 |
| 一月も末頃になると、江戸は少しずつ春に向かってゆくようになる。一日も早く暖かく なりますように、と白い息で手を温めながら、早坂の女中お初は町なかを歩いていた。今 日はおりつに言いつけられて、音羽町の薬種問屋松代屋へ、調合済みの薬を取りに来てい た。この日が二十五日である。帰りには、家を空けられぬおりつの為に、穴八幡宮と近く の菩提寺へ参詣してくる事になっていた。 松代屋では、手代の直次郎が用意した薬の袋を手渡しながら、 「旦那様のお具合は、どうです。」 と、尋ねた。お初は黙って、この娘らしからぬ暗い顔をした。 「そうかい……」 直次郎が嘆息した。渡す薬の中身からも、快方に向かっていない事は察しがつく。 「なんていったかしら、あれ。……いっしん……」 「一進一退、かい。」 お初はうなずいて、 「しばらくそんな風だったんだけれど。……少しずつ、悪い方へ悪い方へ……って、向か っているみたい。若奥様も、大奥様も、なんだかおやつれになって……」 長い病人、しかも不治で寝たきりとなると、看病の家族は疲れが大きい。直次郎としては、 薬を渡しても効を奏さないのがもどかしい。 「気を落とさず、皆さんでがんばっておくれよ。」 「はい。」 お初は立ち上がりかけて、 「直次郎さん、いつかの……あの土方、歳三っていうご浪人さん、どうなさったか、知り ません?」 と、今度は自分が尋ねた。直次郎はきょとんとして、 「歳三さん……。何であんたが、そんなことを?」 聞き返した。 「ううん、ちょっと、思い出しただけ。男前の人だったから……」 お初が誤魔化すと、直次郎はへっと笑って、 「子供のくせに……さてねえ、そういえばもう、かなり顔を見ていないね。あの人はもう、 薬売りはやめたんじゃないかな。」 と言った。直次郎が個人的にうまが合ったというだけの事で、松代屋にとってはもともと 得意先とは呼べぬ小口の客に過ぎない。ふっつりと向こうの足が途絶えた以上、どこで何 をしているのか知るすべがなかった。 「柳町のお道場に行けばわかるかもしれないが。」 「ううん、いいんです。じゃあ。」 お初はやや慌てて断った。娘一人で再び道場を訪ねる程の勇気はありはしない。 ところが偶然というのはあるものである。予定していた参詣の帰り、穴八幡宮近くで、 お初はばったりと出会った。歳三ではない。いつかその試衛館道場で出会った沖田である。 「あっ……沖田、様。」 「やあ、あなたは確か……」 沖田も覚えていたらしく、人懐っこく笑った。 「よくわかりましたね、私が。」 相変わらず、侍のくせに笑顔の多い男である。 「はい……」 お初は笑いかけられて、思わず照れた。 「どうして、こんな所に……ああ、五のつく日、でしたね。そうか、まだ続いていたのか、 偉いなあ。」 「覚えてらしたんですか。」 今度はお初が驚いた。早坂家の先祖の言い伝えで、五という数字を大事にする。主人の回 復祈願は五のつく日に墓参する事になっていて、穴八幡にも行って茶店で一服するのが気 晴らしの楽しみだ、という話をした事がある。沖田は沖田で、お初から聞いた話の後、歳 三にそれを教え、何度か外出するのを見かけている。 「ええ、まあ……今日は、あの方は?」 「ちょっとお出になれなくて……私が代参しております。」 「そうですか。お帰りになったらよろしくお伝えください。」 はい、というお初の返事を聞き終えた後で、沖田は去りかけて、急に思いついたように、 「そうだ。あの、ええと、あなた……」 と言いながら、ちょっと目線を宙に泳がせて指を差した。 「お初です。」 「そうか、名前を聞いていなかった。」 お初はきょとんとして、それからぷっと吹き出した。 「お初さん、おなかがすいていませんか。」 「は……?」 お初といい勝負で、回転が速すぎるのか、話の接ぎ穂のない若者である。今時間があるか、 と問われ直してやっとわかるのであった。お初が、今日はいくつか廻る用事があって日暮 れまでに帰ればよいから、自分次第では小半刻程の融通がつく事を答えると、沖田は得た り、という顔で、 「じゃあ、昼飯につきあって下さい。すぐそこなんです。」 と、言った。 「えっ。」 お初は驚いて、つい尖ったような声をあげた。 「まずいですか。」 沖田のほうが意外な顔をしている。 「いえ……あのう、道で女の人を誘うようなお方には、見えませんけれど……」 お初はもじもじしている。町中で育った昔ならいざ知らず、これでも一応は武家奉公の身 であって、いくらかずつは男女の風儀の厳しさのしきたりに染まりつつある。顔見知りな らちょっとお茶でも、という現代ではない。目の前の沖田も、浪人とはいえ武士ではない か、という遠慮も手伝った。 「女の人……ああ、そうか。」 沖田のほうは、思わずあっけらかんと笑い出した。目の前のお初は子供っぽくて、そんな 意識がなかったのだ。 「あっはっはっは。……いや、失礼。」 お初はむくれた。 「私の事、女だと思っていらっしゃいませんね。」 沖田は拳を口の下に当てて、くすくす笑っている。 「道場破り。」 「まあ。つまらない事をいちいち、覚えていらっしゃるんですね。」 「女の子であんな事を言った人はいませんからね。」 「………。」 剣術の道場を入る時にはたのもう、と言うものかしらと独り言を言ったことである。意地の 悪い、と思った。ただし、沖田には邪気がまるでない。 「別に、変な所じゃありませんよ。ただちょっと一人じゃ行きにくいわけがあるので…… もちろん、お嬢様のご都合がよろしければ、の話ですが。」 「ま……」 お初は決心したように、 「では、お供いたします。いずこへ参ればよろしゅうございますか。」 と、無理に調子を合わせた。 「あははは。ただの小料理屋ですよ。『たつ次』っていう……」 「たつじ……あっ……」 小料理屋「たつ次」の店に、まだ暖簾は出ていない。主の藤吉が一人、仕込みをしていた。 酒の客が殆どであるから、昼飯の客だねは相手にしていない。通いのお運び女中たちも、七 つ時を超えないと手伝いに来ないし、来てもだしの加減や煮汁の味付け等は触らせないのだ。 腕一本で渡って来た親父だから、いくつかの定番の他にはその日に入った魚や野菜たちの顔 ぶれを見ながら、さて今日はどんなふうに料理して食わせてやろうかと考えるこの時間が、 一日で最も充実した時でもあるのだった。 が、内側にたらしてある縄のれんを分けて入ってきた人の足音に、藤吉は包丁をもったま ま無愛想に、 「まだ開けてねえよ。夕方から来てくんな。」 と言いさして、目を上げてげっと驚いた。試衛館の沖田総司が、いたずらっぽく笑いながら 高い背丈で突っ立っている。 「な、なんで……」 「久しぶりだね、藤吉さん。」 そのせつはどうも、という感じで沖田は手を上げて見せた。何と言っても、道場でさんざん 叩きのめされて罵倒を浴びせていった不肖の元門弟と試衛館塾頭である。 「何か……ご用ですかい。」 ばつの悪い顔で藤吉が言った。 「土方大先生の代わりですよ。」 「……内緒だって言ったのに……」 ちっ、と舌打ちした。 「私にも土方流の稽古の成果を見せてほしいな。さぞ上達しただろうと、楽しみにしてきた んだ。」 「勘弁してほしいなあ。」 「まあ、今日はやさしく教えますよ。最後だからね。」 「最後って……」 「それはそうと、昼飯がまだなんだ。何かないかな。」 藤吉は話の転化に面食らった顔をして、 「……まだ、煮しめと漬物ぐらいしかありませんぜ。」 と、渋い顔で言った。それで頓着するような沖田ではない。 「それでいいですよ。稽古は、食べてからにしよう。」 「調子がいいね、どうも。」 藤吉はとうとう苦笑しながら、早くも支度にかかって目線をまな板に移しながらぼやいた。 「こんな時分から貸し切りなんざ、割りにあわねえや。」 沖田はそうそう、という顔をしながら、 「実は、もう一人お客さんがいるんだ。」 と言って、え?と目を上げた藤吉に構わず、店の外へ呼びに行きながら、 「お初さん、どうやら旨いものにありつけそうですよ。お入りなさい。」 と、手招きをした。 「あれっ、あんた……」 縄のれんを分けて入って来た姿を見て、藤吉がまたも驚いた顔をした。お初がおずおずと入 ってきて、頭を下げている。 店の入れ込みの卓に、向かい合って座っている沖田とお初に、藤吉は焼きたての干物を運 んで来て、 「いってえ、どういう、組み合わせなんで?」 と、じろりと沖田の顔を見た。両方とも歳三の知り合いである事はわかっているが、二人連 れである事の得心がいっていない。 「八幡様の前で、釣り上げたんですよ。」 「へっ、子供のくせに生意気言っちゃいけねえ。こんなケツの青い坊やにひっかかるほど間 が抜けちゃいねえや、ねえ、お初さん。」 「ひどいな。」 「口はひどいが味がよい、ってのが売り物でね。」 と、藤吉は正直な評判通りの事を平然といった。お初は聞きながらくすくす笑っている。先 ほど沖田から子供扱いされた事の仕返しを藤吉がしてくれた格好になった。 「……ほんとに、おじさんにはお世話になって……あの晩、目が覚めた後にいただいた熱い お味噌汁のおいしかったこと……このお店じゃなかったら、つられて来ませんでしたよ。」 「嬉しい事を言ってくれるじゃねえか。」 藤吉はにやりと笑うと、配膳を終えて、板場の中に戻った。そこから、やや声を高めて、 「よう、沖田先生。さっき、剣術の稽古、最後だって言ったよなあ、ありゃあ、どういう事 だい。」 と、手が忙しくて忘れていた疑問を投げかけた。沖田はその美味な味噌汁、今日は春大根の 綺麗な千六本に刻まれた実の入って、小口のネギをちょっと散らしたのを一口すすりつつ、 「ああ、忘れてた。来月、京都へ上るんですよ。」 「えっ。」 お初も、驚いて顔を上げる。 「そりゃまた、一体……」 「浪士隊、っていうのに応募してね。公方様御上洛の警護についていくんです。まあ、都の 用心棒の集まりですね。」 藤吉は流石に毎夜客商売をしているから、ふと思い当たった顔をして、 「ああ、そういやゆんべ来た客がなんだか、そんな噂をしてたな。……で、何、沖田さん、 あんただけじゃなくて、土方先生も?」 「ええ。近藤先生をはじめ、試衛館の主だった連中は、揃って。」 「それじゃあ、道場はどうなるんで。」 「試衛館は閉めて行きます。」 「うへっ、……とうとう潰れたか。いや、あたしの通ってた頃から、このオンボロ道場じゃ 長くは持たねえとは思っていたが、そりゃまた早かったねえ。」 沖田は吹き出した。 「ひどすぎる。」 藤吉は苦い顔で顎のあたりを撫で、 「そうか、いくら強くったって、貧乏にゃ勝てねえもんなあ。」 「別に、貧乏で潰れたわけじゃないって。」 「いいよ、いいよ。俺の前で格好つけなくったってさ。かわいそうだから、たんと食ってい きなよ。」 「違うのになあ。」 と、沖田は苦笑しながらそれでも目の前の飯を旨そうに食べている。 「……まあ、藤吉さんには途中で終わってしまって、申し訳ないけど。今日はね、土方さん、 多摩の方へ挨拶回りに行っていて、来られなかったけど、近いうちにちゃんと来るって言っ てましたよ。」 「さいですかい。行ったきり、帰って来ねえんで?」 「さあ、わからない。」 沖田も、そこのところになると首をかしげた。 「ふうん……。まあ、公方様のお役に立つんだ、出世かもしれねえ……」 藤吉は、それっきり黙って中断していた仕込みを始めている。本当は歳三がいなくなる事が 寂しいのかもしれない。 入れ替わるように、今まで黙っていたお初が声をひそめて、言った。お初の箸は、さっき から止まってしまっている。 「あの……本当ですか。」 「え?」 「京へ行かれるって……」 「ええ。本当ですよ。」 沖田が道場主近藤の名まで挙げた嘘を言うはずもない。お初は悲しそうにうつむいてしまう。 「どうしたんですか。」 「………。」 沖田はお初の手元の味噌汁を指さして、 「さめますよ。」 と、言った。お初は促されて一度汁椀を手にとってから、やはり卓の上に置いて、更に小声 になって話し掛けた。幸い、藤吉は板場の奥に忙しく出入りをしていて、聞かれる気配はな い。 「あの……沖田様、ご存じでしょうか。」 「え?」 「うちの、おりつ様と……そちらの、土方様のこと……」 沖田はふと瞳を上げたが、さりげなく、いや?と言った。お初は意を決したように顔を上げ、 「あのお二人……きっと、好き合ってると思うんです。」 「えっ」 ぎょっとした拍子に、つまんだ箸から煮豆がころん、と皿の上に落ちた。 「もちろん、あの、おかしな事は何も……ないと、思うんですけど……」 と、お初は主人のために弁護した。この「たつ次」で眠りから覚めた時に、おりつは一人で 枕もとに心配げに座っていたのである。勿論、貧血の状態から疲れのあまり昏々と眠ってい た間の事まではわからないが、挙措は落ち着いていた、と思う。お初は遠慮があって、その 間の事、つまり、歳三とおりつがどれほどの時間一緒にいたのか、或いは、ひとつ部屋にい たという事すら聞いてはいない。ほんの少し、気をきかせて茶店の歳三と言葉を交わす時間 を作ろう等とした小さな試みが、思いがけず自分が転んだまま気を失って、女あるじの帰宅 の時間を大きく遅らせてしまった、という動揺のほうが先に立って、それどころではなかっ たのである。目が覚めた時、藤吉が店の材料を使って気付けの替わりにと体を温める味噌汁 や握り飯を出してきてくれたが、その時も「美味しい」と思いながら、とてもゆっくりとし ていられる心境ではなかった。おりつは自費で駕籠を呼び、祖父の家へ薬をとりに行って遅 くなった、という理由を姑に詫びて、それからお初は迷惑をかけた挨拶を「たつ次」にして おかなくて良いだろうか、という事を尋ねたのだが、その時だけはおりつはわずかに顔を曇 らせて、無用の事と止められて終わったのである。 勿論、沖田は歳三の口から、そんな細かい経緯は聞いてすらいない。お初も、先ほどまで は用心して、おりつと出かけて気分が悪くなった時に休ませてもらった店だ、という言い方 で、ついて来たのである。 「なぜ、そんな事を?」 「そりゃ、女ですもの。見ていればわかります。」 「ははあ……」 その、女ですもの、の部分は沖田にはちっともわからない。話がいきなり核心を突いてきた ものだけに、少女のお初がませた口を利くのを、からかいたてる気にもならなかった。 「でも、若奥様のお気持ちは……無理もないと思うんです。旦那様も、大奥様もそれは、冷 たい人なんですもの。ちょっとくらい他の人にときめいたって……」 と、お初はわが事のように顔を赤らめて、うつむいた。 「………。」 これは迂闊に相槌を打てないぞ、という困った顔になって、沖田はとりあえず、間合いをと るつもりで再び味噌汁の大根を口に含んで、汁をすすった。 「沖田様。あの……逢い引きをさせてあげることはできませんでしょうか。」 あやうく、ぶっと味噌汁を吹き出すところであった。大急ぎで口の中に大根を流し込んでか ら、 「なんてことを……わかって言ってるんですか。」 と、今度は年上の口調を取り戻して、真顔で言った。 「だって、土方様はいなくなってしまうんでしょう。」 「はあ。」 「だったら、一度くらい……」 「それは、出来ないな。」 沖田は即座に、お初の正面をピシリと打つように制した。 「どうしてですか。」 「私たちがどうこうすべきことじゃない。」 打って変わったような沖田の真剣な目に、お初は息を飲んだ。 「………。」 沖田は膝の上に両手を置いて、体勢を整えた後、 「あなたの言うとおり、土方さんにはひょっとしたらそういう気持ちがあったのかもしれな いけど……しかし、ある時から迷いが吹っ切れたように、剣に打ち込むようになった。それ に、今は上洛を控えて大事なときです。余計なお節介はしないほうがいいと思う。」 「よけいな、お節介……」 「あなたの若奥様だって、ご主人の看病に懸命になっておられるのではありませんか。そん な事を外の人間に言うのは、主家に対していけないことだと思いますよ。」 沖田は自分が主人を持った事はないが、物心ついてから内弟子として人の下に従い、試衛館 と天然理心流を第一に大切にする、という考えが自然と身についている。日頃はまじめな時 がない、と言われる位の冗談好きだが、たまに改まると、「まず上への礼をたてよ」という 節義は肌身に添っている。ましてや、人妻の不義は(ある程度形骸化したとはいえ)天下の 御法に触れる禁忌である。あの凛として美しいおりつが、人目を忍び歳三と「逢引き」する 等という罪びとになる事など、沖田の心情からしても反射的に嫌であった。歳三がわずかの 機会で惚れ込んでしまった理由も、何のために「振られてきたよ」と珍しく問わず語りに切 り出したのかも、沖田には、そう深いところではないが何となくわかるような気がしている。 女の側に身近なお初がそう感じたからには、一方的に歳三の片恋だったのではなく、惹かれ あうものがあったのだという事は今初めて知った。当人どうしに何か思う事があって、一度 けじめをつけて抑えた事ならば、余計に触れてはいけないことがらのような気がした。それ でつい、お初に対して手厳しい言葉になった。これが、沖田の身内である歳三がからんだ事 でない、まるで別の世間話として相談されたものならば、沖田は或いは、あははと笑って面 白がりながら逃げたかもしれない。 「……ごめんなさい……」 ふと見ると、お初がみるみるうちに目を潤ませ、しくしくと泣き出した。沖田は慌てた。 「お初さん。ちょ、ちょっと……」 「何泣かしてんだよ、沖田さん。」 藤吉がいつの間にか、お茶を二つ乗せた盆を持ち、ぬっと後ろに立っている。 「ち、違うって。違いますよ。」 「ごめんなさい……あたし……あたし……」 若い娘が感情を高ぶらせて泣き出したら、そう簡単には止まらない。お初はすすりあげて、 袖で顔を覆った。藤吉は、横目で困り果てる沖田の顔を見ている。 |
| 2 |
| 文久三年も二月に入った。いよいよ京都出立の日が近付き、試衛館では、食客たちが部 屋に集ってそれぞれ刀の手入れをしたり、荷作りをしたり、文を書く者もいて、そわそわ とした雰囲気がこぼれていた。食客の溜まり部屋に、最年長の井上源三郎がからりと障子 を開け、 「皆、いるかい。」 と一声かけて、ひい、ふうと人数を数えている。 「なんだい、井上さん。」 いずれにせよ着古した衣類を並べて、限られた荷にどれを丸め込もうかと迷っていた永倉 が顔を上げた。井上は見回して、 「あとはサンナンさん(山南敬助)と……トシさんか。どこへ行ったか知らねえか。」 と、呼び名を挙げた。この井上源三郎は日野の出で、天然理心流の古い門人であり、近藤 勇や土方歳三、沖田総司より入門歴からいえばずっと先輩に当たる。仏頂面の歳三を昔な がらの「トシ」で呼ぶのは、ここ試衛館の門弟では井上だけである。 「山南さんは、ちょっと同門の友達に挨拶してくるって、出掛けましたぜ。夕方には戻る って言ってた。」 と、山南と同流儀出身の藤堂が答えた。続けて沖田が、 「土方さんは、奥で何か書き物をしてましたよ。『ちょっと一人にしてくれ』だって。」 原田はそれを聞くとにやにやと顎をなでて、 「女に文でも書いてるのかね。」 と茶化す。 「まさか。ここのところ、身辺はきれいなものだそうですよ。」 「どうだか。」 からきしモテた事のない井上は女の話題には興味のない様子で、 「一さんは今朝発ったんだっけなあ、惜しかったな。」 一時期試衛館に寄食していた斎藤一は所用を済ませ、京都で浪士隊に合流すると言ってい た。出身が明石藩だとも言い、いやあの言葉遣いは江戸だ、いや奥羽だと皆の噂はまちま ちだが、この男は平素目立たない上に肝心な話はとんとしないから、誰も本当のところを 知らない。ふっと現れてはふっと消えるので、何やら実家の用事だと言われれば気にも留 めていなかった。そもそも、誰がいつ出入りしてもあまり詮索する連中ではないのだから、 気楽なものである。 「何かあるのか、源さん。」 永倉が、最初の質問を思い出したように顔を向ける。 「うん、皆覚えているだろう。去年の春頃まで、道場に来ていた、藤吉。」 「ああ、……沖田にこっぴどくやられて、やめた奴だろう。」 「その後の、たんかがすさまじかった。」 原田、藤堂も続けて答え、一同、思い出して笑い声をたてる。変わり種が多いこの道場の 門人の中でも、藤吉は入門の年齢も動機も、やめ方も特に変わっていた。自分の半分ほど しか生きていない塾頭の若造、つまり沖田総司にぶん投げられたのが余程に頭にきたらし く、江戸の悪態に慣れ育った男たちも目を丸くする程の軽やかな悪口雑言を並べ立て、竹 刀を叩き折って道場を出ていった後は、悪かったともいわず姿を消してしまったのである。 もっとも、それをげらげらと笑い話にしてすませてしまった近藤道場はやはりずいぶん変 わっている。 井上が、 「うん。その藤吉が、われわれを店に招いてくれるそうだ。」 と言った時は、当の沖田が「ええっ」と声をあげた。永倉は鷹揚に「ほう。」とのんきな 声で目を見開いている。 「皆さんの門出を祝って、ぜひ心ばかりのおもてなしをしたいというんだが。」 「なんだか、おっかねえなぁ。」 原田がさもおかしそうに、横目でじろりと沖田を見た。藤堂も視線を合わせて、 「特に、沖田君はな。意趣返しに一服盛られるかもしれんぜ。」 「えっ……藤吉はそんなことしませんよ。」 沖田がぎょっとすると、皆笑っている。 「ふうん、じゃあ行かねえのは、誰と誰だ。」 井上は冗談話のゆとりを楽しまない。原田があわてた。 「ちょ、ちょっと待ってくれよ。源さん、誰も行かねえとは言ってねえ。」 「そうとも。せっかくの、御招待を……」 このところ、長旅前の諸費用倹約で、まともな外食等していない。若い藤堂は「御招待」 とつい漏らしたのも正直なところだが、そんなに気取った店でないのは承知している。 「あのよう、これは……?」 原田が指で丸を作る。皆が、出発を前に遊ぶ金がないのは同様なのだ。井上が珍しくふっ ふっ、と笑って、 「ぜんぶ、藤吉のおごりだとよ。」 と言った途端に、わっという歓声が起こった。食い放題、飲み放題の貸し切りだというの である。藤堂などは「やった、やった」と手を合わせて拝むふりまでした。永倉が、 「藤吉は太っ腹だな。」 と、肥満ぎみの自分の腹をパン、と叩いてみせると藤堂はさっきの毒料理と言った事など けろりと忘れて、 「いやあ、やっぱり、あいつはいい奴だと思ってたんですよ。」 と今度は藤吉さまさまな持ち上げようだ。沖田が呆れた。 「調子いいなあ。」 また笑い声が起こった。 奥の小部屋では、障子が少し開いており、そこから半紙が一枚、風に飛ばされたらしく、 廊下に舞い落ちている。今も風にそよ、と吹かれて四辺の端をひらひらさせているその紙 を、山南敬助が外出から戻ってきた所でそれを拾いあげ、さっと文字の上に目を走らせた。 歳三の俳句の下書きらしい。何度も字句を推敲された跡がある。 「………。」 山南は文字の列を黙視した後、障子の中の気配を伺った。中はしん、としている。 「土方さん、いるのかね。」 不意に、室内でガサガサと乾いた音がした。歳三はつい陽光につられて、うたたねをし ていたようだ。「どうぞ」という声の後で山南はすっと障子を開けて入っている。 「……山南さんか。」 「春とは言っても、風邪をひくといけない。少し冷えてきた。」 「ああ……」 半分は返事、半分はあくびのような声を出して、歳三が伸び上がった。確かに午後の陽光 で室内はぬくもっていたが、山南と共に入ってきた空気が心地よく冷たい。昼寝の間にか いた汗がひやりとする。 山南は、ちらりと文机の辺りを見た。慌てて裏返しにしたような半紙が無造作にまとめ て置かれている。 「句をひねっていたのか。」 と、聞かでもの事を山南はきいた。 「いや、その……」 「拝見したいな。」 「よしてくれ。とても、あんたに見せられたもんじゃない。」 と言ったのは謙遜ではない。山南敬助も出身に謎が多く自らの過去を語りたがらないのは 不思議なところなのだが、言葉の端々から滲む知識の量と学の深さは、試衛館の中では近 藤ですら足元にも及ばない。根が真面目なだけに物事への批評も率直で、全くの悪気はな く指摘したところが痛いところを突いている事があり、それだけに歳三は時にはそれが無 闇に勘にさわる時もあり敬遠する事もあるのだが、逆に、純朴で飾りのない人柄と教養に 尊敬の念も併せ持っている。どうしてもやや老けてみえるが山南は同年齢でもあり、その 辺りが男同士として微妙な関係でもあった。歳三の俳諧は郷里では名の通った俳人である 実兄、義兄の感化で手すさびに始めたものであり、もとより本格的にその道の上達を目指 した程のものではないが、五七五という最も短い言葉の中で表現する、という方法が、七 面倒な平仄を重んずる漢詩よりは歳三の性格に合っている、というに過ぎない。兄たちな らば山南と俳諧談義も結構深い興趣のところまで弾むのであろうが。 が、山南は歳三の「遠慮」を意に介さない様子で続けた。 「沖田君に聞いたよ。号は、豊玉というそうだね。良い名前だ。」 歳三は「ちっ」という顔で、 「あの、おしゃべり。」 とぼやいた。ちなみに歳三が、武士として名乗る時の名は「義豊」である。義の字は亡父 譲りのものだが、号の「玉」は勿論、玉川とも書かれる郷里の「多摩」に通じる。玉とい う文字は、優れて美しいという意味もある。勿論そんな事は山南ほどの者なら百も承知で あろう。豊かで美しい、とは我ながら句の出来からすると口はばったいような俳号でもあ り、歳三がこの名も持っている事は郷党でもごく親しい人しか知らない。ただし、日野に もしょっちゅう出入りしている沖田総司が漏れ聞いてきた事の吹聴癖までは止められない。 「君にしては、至極穏やかな趣味で結構じゃないか。」 山南は決して嫌味ではなく、歳三の別の一面を本当に歓迎してこういうのである。歳三は むすっとして、 「素人さ。いくつか句帖にまとめておこうと思ったが……我ながら下手でうんざりした。」 と、諦めたように言った。正直者には正直に返すしかあるまい。 「素直に、書き残しておけばいいじゃないか。後で、ああ、あの時はこんな事を思ったの だな、と振り返るだけでも、楽しみになる。手直しもできるだろう。」 「そうかね。」 山南は先ほど廊下で拾った紙を差し出した。 「これが、落ちていた。」 歳三はうっと慌てて手に取った。素早く目を通してややほっとした顔をする。 「ああ……これか。」 と、興もなげに畳に投げ出した。 「ずいぶん、苦心の跡がある。」 「いや、これは……うまく形にならなかった。捨てるつもりだったんだ。」 「春の月、か。どんな情景を詠みこもうと思ったのかね。」 「多摩で川っぷちを歩いていたら、ぽっかりとな、月が浅瀬に映った。前は川で、後ろに は……人影もなくただ田畑が広がっていてな。それを何とか書き留められないかと思った んだが……いや、もういいんだ。」 口を開いてしまってから、歳三は手を横に振った。出来上がったところでいずれ凡作だと 思っている。しかし山南は相変わらず真面目なおももちで、 「なるほど。いや、途中で捨てるのは惜しい。工夫すれば、秀句になると思う。」 と、言った。 「俺にしては、か。」 歳三は苦笑した。山南が、もう一度しげしげと紙片の字面を見ると確かに「玉川や」「玉 の水」「畑を背にして」「水清く」「前は水」「ぽかりとうつる」などなど、様々な文字 が書いては消してある。 「下の句は『春の月』」で決まりとして……この五と七が互いに呼応するようにすれば、 趣が増すのではないかな。川を前面ととらえず、その方角を入れるとかして……それに、 多摩川と、田や畑を無理に入れないでもいいように思う。風景が狭くなり、野暮ったい響 きになる。あ、いや……失礼。」 禁句を言ったかな、という顔で山南が訂正したが、歳三は考え込んだ。 「……いや……」 歳三は仏頂面のまま筆をとって新しい紙に素早く句をしたためた。山南は読んで、 「山を西、川を東に、春の月……ふうむ……」 今度は山南が、困ったように腕を組んで考えている。確かに下手だ。これでは見たままで はないか。しかし、うかつに口を出すと歳三がどうへそを曲げるかわからない。 「山と、川、か。『川』は『水』の方が、響きが美しいのではないかな……」 「うーん……」 歳三は頭を掻きながら、苦しげな顔でぶつぶつ言いながら、また一行、消してまた一行と 書く。興が乗ってくると集中しだす男である。山南は、その間は筆先を見ないようにして 歳三の集中を妨げないよう、じっと待っている。 しばらくして、歳三がやや明るい声を発した。 「できた。」 どうだ、という顔をした。山南が身を乗り出す。 「どれ……。」 歳三は、まだ墨が濡れた新しい紙をさっと手渡し、今度は自分が目をそらしている。先生 に課題の提出をして評価を待っている学生のような感じ、なのである。 そこには、こう書かれていた。 ―――水の北 山の南や 春の月 山南が「ほう、」と一息、感嘆の声をあげた。 「いいじゃないか、秀作だよ。」 「………。」 歳三は黙っている。こういう時、すぐに有難うとは言わないのが悪い癖だ。しかし沖田等 から誉められるのよりずっと真実味がある山南の誉め言葉が嬉しからぬはずはない。が、 山南がふと気付いたように 「しかし、……」 と言葉を切ると、歳三が聞きとがめた。 「しかし?」 何かまだまずい点があるのか、と気になるのである。 「あの辺りで、山が南側に見えたかな。」 と、言ったのは、山南は他の食客とは違い、天然理心流の一門人として堂々の扱いを受け 沖田総司と共に多摩の村々への出稽古にも指南役として出る事を許された程だからである。 つまり、歳三の説明した辺りの土地の風景を見て知っている。現実の方角では東西ではな かったか?と細かい相違を気にしたのだ。杓子定規はこの人の癖なのである。歳三は指摘 を受けたことにむすっとして、 「多摩をはぶいたんだから、どうだっていいのさ。」 と言った。現実の多摩地方限定の語句にすれば野暮ったくなるとついさっき教授したのは 山南ではないか。歳三には歳三の感覚というものがある。春で温むとはいえ、夜気の中で さらさらと音を立てて流れる水、それも「玉(多摩)」との水はやはり清涼に冴えていなく てはならない。それには北という語感がぴったりする。また、それに対比して春の山は、 日中の日差しを蓄えて若葉が柔らかに芽吹き、あたたかく落ち着いて風土に根ざしていな くてはならず、この場合に限り山は南という語感が最も相応しかるべき気がするのである。 と、いうこじつけを知ってか知らずか、山南は微笑した。 「しかし、偶然とは言え……これでは私の名になってしまう。」 「偶然じゃねえ。この句はあんたが作ったようなもんだからな。拝借したんだ。」 と、歳三は珍しく敬意を表すような言葉を口にした。山南のほうがきょとんとして、 「いいのかね、それで?」 歳三は面倒くさげに、 「悪くねえや。俺にしては、だが。」 と答えた。 「ふふ……『水の北 山の南や 春の月』……ありがとう。いい記念になる。」 山南は即座に紙と筆を借り、歳三よりも達筆な文字でさらさらと写し、「文九三年二月 土方豊玉宗匠作」と添えて、それを丁寧に懐にしまった。歳三はその動作を見るともなく 見ている。 ふと山南はここに来た本題を思い出し、 「そうだ。今晩、『たつ次』で集まるそうだよ。藤吉のご招待で、出陣の祝いだそうだ。 土方さんももちろん、行くだろう。」 「藤吉が?ほう。」 「君はあの男を可愛がっていたからな。お陰で我々も、お相伴に預かれる。」 「ああいう、癖のある奴とは馬が合うのさ。」 「ふふ……では、井上さんに伝えておこう。人数を心配していたからね。お邪魔をした。」 と、山南は立ち上がって、部屋を出て行く。歳三はふう、と溜め息をつき、さっき裏返し て置いた書き損じをめくって、小声のひとりごとを漏らした。 「しれば迷ひ、しなければ迷はぬ恋の道……」 と、そこには歳三独特の手蹟で似つかわしくもない文句が書かれている。うんざりしたよ うに、 「字数が合わねえ、季語がねえ。どどいつじゃあるまいし……こっちを見られたら、最悪 だった。」 こんなものを見られた日には、流石に教養人の山南が吹き出すだろう。 歳三は、墨で一度 その出来損ないの句を塗り潰したが、ふと、山南の言葉を思い出したように、まあいいか、 と、そのまま、もう一度同じ句を書き残した。これらの句は、歳三が江戸を出発の前に新 たに「豊玉発句集」と表題した句帖にまとめられて、その後も長く残っている。ただし、 「しれば迷ひ」の句は流石に若干ためらわれたようで、更に「しれば迷ひ、しらねば迷ふ 法の道」とやや硬く改稿されて、それでも無季の風変わりな一行となっている。 |
| 3 |
| その夜。小料理「たつ次」の店に集まった天然理心流江戸道場試衛館壮行会には、京都 出発組の他に、残留する江戸近辺の門人たちも駆け付けて、いつになく盛大に盛り上がっ ていた。門人といっても大半が町人か百姓である。「おーい、こっちこっち、お酒が足り ないよ」「刺身が来ねえ、刺身が」など、好き勝手に騒いでおり、藤吉の店の小女たちも、 てんてこ舞いで働いている。調理場から運びやすいように一階の椅子席と小座敷を貸し切 って、商売の合間に顔を出す連中も加わると総勢は三十を超えた。もっとも、弟子といっ ても熱心な輩ばかりではなく、どこから聞きつけてきたのかという久しぶりの者もいる。 小半時も経つと、誰が誰やらわからない騒ぎになってきた。 まず原田が猪口を左手に掲げたまま呆れた。 「しかし、タダってだけで、こんなに集まるとはねえ。」 「本当だ……夏に、麻疹が流行った時にゃぱったりと習いに来なくなったくせにな。」 昨年に麻疹やコロリが江戸の町で大流行した頃には、湯屋も髪結いも、およそ人の集まる ところでは死病がうつるといって、人垣が出来たのは寺と棺桶屋だけという様相だったの である。天然理心流は幸いに郊外の多摩一帯に地盤があるので当主の近藤らの出稽古や、 地縁の人びとの物資応援で食うには困らなかったが、居候剣客の面々は毎日道場の床の埃 をよそめに見ながら、鼻毛でも抜いているしか仕方のない閑古鳥状態であった。 と、そこへ 突然、銚子をぶら下げた門人の町民某が原田たちの席に割り込んできた。 すでに生っちろい顔が朱赤に染まり、したたかに酔っている。 「なーにを、言ってんですかい仰っちゃってるんですかい、先生がた。あたしら、居残り 組はねぇ、ちゃあんと、身銭を切って出し合いましたよ。ここの払いは。」 「ほう。そいつは、知らなかった。」 「あるじに、包んだのかい。」 見送られるほうはそれこそ小銭入れすら持たぬ手ぶらご招待の身である。門人は胸をそら して、 「あったりめえでさ。曲がりなりにも、同じ弟子っ子の仲間だってぇのに、藤吉ひとりに 持ち出させたりしちゃあ、こちとらの男が、すたる。」 「それは、殊勝だなあ。いや、悪かった。」 永倉は素直に頭を下げた。今でいうカンパが、店主にいくばくか出し合われたらしい。 「……ひとりあたま、いくら出したんだよ。」 原田が疑わしいという目をじろりと向けた。門人は「ひっく」とひとつシャックリを飲み、 その原田にこそっと耳打ちした。原田は猪口の酒を吹いて笑い出した。 「そりゃあ、気の毒だ。」 「何、何?」 永倉が寄せてきた耳に原田が聞いた金額を耳打ちする。永倉も吹き出した。 「その金でそれだけ飲んじゃ、たまらんだろう。」 「ああ。たまりませんねえ。酒もうめえし、肴もうめえ。こてえられねえ。」 「違う違う、藤吉がだ。」 永倉たちの座席はげらげら笑う声が高まる。 一方、山南と藤堂の席には別の門人たちが卓を囲んでこちらは比較的真面目なつらつき で飲んでいた。山南敬助は北辰一刀流出身だが天然理心流の古武術的な稽古術をもやさし く噛み砕きながら話し具体的に長所短所を教えてやるので、現代ならば中学高校の教諭が 立派につとまったであろうという親切丁寧な指導法だったから、へたをすると流派生え抜 きの歳三、沖田、井上という古顔の門人よりも、一般の弟子たちには人気があった。藤堂 も同じ北辰一刀流が出身だが剣技に熟達するというにはまだ山南には遠かった。しかし、 こういう席になるとなんとなく山南先輩の横が居心地がいいらしい。奥羽人であまり口達 者とはいえない山南に比べると藤堂は江戸の水で産湯を使った人間だから、座持ちがよい。 面白い取り合わせの席である。 「いやあ、お名残惜しい……山南先生には、本当に手取り足取り親切に教えていただいて、 あたしはもう、ほんと、ご恩は忘れません。ああ、もちろん、藤堂先生も、お世話になり ました。」 と言ったのは中年になりかけの商人の弟子だが、 「なんだい、取ってつけたみたいに。」 藤堂が口をとがらせて、それでも酒が入っているから笑っている。 「こちらこそ、私のような他流から来た者を皆さんに立てていただいて、ありがたかった。 どうか、試衛館が閉まっても、鍛練は続けて下さい。続ける事で本当に力になるものです。」 と、きまじめに説く山南に商人弟子は手を振って否定し、 「山南先生は、後からでも立派に天然理心流を学んだ先生じゃございませんか。あ、いや、 藤堂先生、北辰一刀流が悪いってわけじゃないですよ。藤堂先生も、強い。」 「また、ついでか。」 藤堂がちぇっといいながら、猪口が面倒くさくなって銚子の首からじかに残り酒を煽った。 一階でも畳の座敷席では、当然のように最上席には近藤勇が、主賓として座っている。 下戸の近藤は、弟子たちが代わる代わるにやってきては、ひと口だけでもと勧める酒で、 すでに真っ赤になっていた。 「せんせえ、近藤先生。頼みます。アレやってくだせえよ、アレ。」 まだ雇われ職人の大工をやっている弟子が、酒で汗をかき腹掛け一つになって、頭には手 ぬぐいで鉢巻をしながら身を乗り出して近藤にせがんでいる。 「おいおい、よせよ。失礼だよ。」 年かさの弟子が止めたが、職人は構わず、 「てやんでえ、俺ァ、近藤先生のアレを見ずにゃあ今晩は終わらねえ。都へ行かれちまっ てからじゃあ滅多に拝めやしねえじゃねえか。」 近藤は黙ってニコニコと笑っていたが、黙ったまま大きく口を開けて、握りこぶしをもっ てゆき「あむっ」と、拳固を口の中に飲み込んでみせた。後年まで有名になった近藤の酒 席での唯一の芸なのである。 「あっ、やった、やった!!」 周りが一斉に囃し立てた。カメラのある時代ならまずはスナップとして必須で残ったかも しれない一場である。 「相変わらずだなあ………」 その側の席では沖田がくっくっと横目で近藤の芸を見ながら笑い、若い弟子の一人と飲み 比べをしている。沖田は子供っぽい顔に似合わず、次々と茶碗酒を飲み干しけろりとして いる。周囲からまた別の喚声が上がった。最年長の井上が横で苦い顔をして、 「おい、もうよせよ。総司はつぶれねえよ。」 「いやあ、参った。沖田先生が、こんなに強いとは思わなかった。」 「剣術だけじゃないんですねえ。」 沖田は、酒はいくらでも飲むが酔ったような顔もしなかった、といわれる。ただし小遣い で飲みに行くという事をしないから、江戸の弟子たちは連れ立って居酒屋に遊んだことも なく酒量を知らないままきたのである。試衛館では酒代にも事欠く食客たちが多いせいも あり近藤が飲めないので遠慮もしてきたのだろうが、多摩へ出稽古の教授に行けば、そこ は裕福な豪農の家にあがるのだし、若い上にしゃべっていて話の尽きないという若者だか ら、話を肴に、すすめられるままに飲んでいつのまにか強くなったものらしい。飲まなけ れば飲まないでいられるが、飲んだら飲んだで平気なのだ。肌が浅黒く顔が赤く染まると いう事もないし、何より普段から笑い上戸なので、酒で騒いでいるのだか地のままなのか 区別がつかないのである。 「こいつが弱いのは女だけさ。」 沢庵をかじりながら井上が言うと、飲み比べで負けた弟子がほう、という顔をして、 「そりゃ、本当かねえ。おいっ。……それ!」 と、狭い座敷内であいた皿を片付けに通り掛かった店の小女の袖を素早くつかんで、むり やり沖田のひざに押し倒した。 「きゃあっ。」 頃合なら三十過ぎという女は膳を避けようとしてよろめき年相応の量感のある体をひるが えして、どさっと沖田が組んだあぐらの上に尻餅をつき、丁度「抱っこ」をされた格好に なった。反射的に落ちてきたものを抱きとめようと動かした沖田の手が、思わず、つかん ではいけないあたりをつかんでしまった。 「あっ」 「あらっ」 小女はこういう酔漢のらんちきにも慣れたもので、もののはずみだから大仰にしても悪い と思ったのだろう、驚いている沖田の手をちょい、とつまんでけろりと振り払った。裾が みだれてちょっとしどけない足が見えている。沖田は呆然として豆鉄砲を食らった鳩その ものになっている。 「ほんとだ。」 門人たちがどっと笑った。 近藤は拳固飲みの芸を終わってからも、いやもう酒は結構とすすめを断りながら、逆に 代わる代わる挨拶に来る弟子たちにニコニコと返杯をついでやっていたが、間をみはから って数人置いた席の沖田に声をかけようとした。 「おい、総司。」 答えどころかのっぽの上半身の姿がない。ふと気付くと、沖田は先ほどの突発事故で一気 に酔いがのぼせにまわって、人の合間に埋もれるようにぶっ倒れている。 「……つぶれた。」 井上がぼそりとつぶやいた。 近藤は、歳三にこっそり声をかけた。 「歳。」 「ん?」 近藤は何気なく厠に立つふりをし、物陰で何事か歳三に話している。 時ならぬ大宴会も終盤に近付き、板場のほうではやっと嵐のように出てゆく酒と料理の 手配りを終えて、ひと段落した所であった。歳三が立って来て、藤吉に声を掛けた。 「藤吉、ちょっと、いいか。」 「へい。」 二人は連れ立ってトントンと階段を上がっていった。二階はいくつかの襖で仕切られた小 部屋の座敷があるが、今日は下の騒ぎがあるから、他の客は入れていない。そのうちの一 室では沖田他、飲みつぶれてきた者が四人、雑魚寝で寝かされており、高低交えた音色の いびきが聞こえている。その隣の部屋に入ってきた歳三は、藤吉と向かい合って座った。 奇しくも、昨年の雨の晩に滞留した部屋でもある。 「大勢で押し掛けて、すまなかったな。」 「なあに、お賑やかでよろしゅうござんした。腕のふるい甲斐がありましたよ。」 と、言いながら藤吉は照れたようにタスキを外している。久々の大仕事だった、という、 ややほっとした顔であった。 歳三は、さほど酔ってはいない。この男は不思議なもので、酒が大好きという程ではな いせいでもあるが、大勢の人間が集まる時にはどことなくさめて、全体の状況を俯瞰して いるほうが合っている、というところがある。適当に杯を重ねているように見せながら、 殆ど口にはしなかった。酔いがまわってしまうと、料理の味も何もわからなくなってしま うという事が理由のひとつにあった。歳三はこの店に通って日頃の品書きのものは味わっ てきたのだから、今日の藤吉がいかに丹精こめて腕をふるってくれたのかは、目と舌でも わかっている。上洛が決まってからこの親父がぼそりと呟いたのは、上方へ行くのはいい があちらさんじゃあ毎日食うものの味が違ってきっと東育ちにゃ閉口しますぜ、という事 だった。海のない山城京都へ行く歳三たちの為に、江戸前の味を腹一杯食わせることで、 千言を費やす以上のはなむけになる事をこの職人気質の親父は知っていたのである。 「うん、うまかった。……これは、近藤先生からだ。」 歳三はうなずいてから、懐紙に包んだ金を差し出した。 「足りないかもしれんが、不如意なもんで勘弁してくれ。」 「と、とんでもねえ。こんな物、受け取れません。」 藤吉が慌てた。勘定の損得はもとより度外視の今日の企画である。 「いや。是が非でも取ってほしい。」 「今日の一席ァ、もともとこっちが言い出した事ですぜ。あんな風に道場を飛び出して、 それっきりおさらばっていうんじゃ寝覚めが悪いからね。てめえの気の済むようにしたま での事で払いをもらっちゃあ筋があわねえ。持って帰って迎え酒のひとっ樽でも買って景 気をつけたほうが、まだましでさァ。」 歳三と阿吽で通じるほどの頑固者である。首を縦に振らぬことは予想済みで、歳三はつぎ の切り札を続けた。 「近藤先生がおっしゃったんだ。もらってくれ。」 「………。」 「ほんの短い間だったが、試衛館に通ってくれた可愛い弟子だからな。おごられっぱなし じゃこっちの筋が通らんと言うんだ。近藤先生は、俺か沖田の言う事ならうんと言いやす かろうとも、言った。自分はあまり藤吉に教えてやらなかったから、とな。」 「近藤先生が、俺を……」 近藤勇も江戸と多摩を合わせれば数百の門弟後援を抱える棟梁である。中年を過ぎてから 一時期だけ通った藤吉などは、確かに手をとって教えてもらうほどの師弟ではなかったし、 上達が遅い事に苛立ったすえに頭に来てやめた時には、貧乏道場芋流儀、と、本来なら袋 叩きにされてもおかしくない暴言を吐き捨てて来たのである。それを笑い話にすませて、 招待の席に宗家みずから足を運んでくれた事で充分におつりがくる位なのであった。 「まあ、俺にしても、途中で教えてやれなくなって、面目はない。なに、これは皆さんで 飲んでくれといって日野の名主から出た金だよ。路銀にするべきものじゃねえから、飲み 食いの足しでいいんだ。」 これは歳三の嘘である。今日の事を知ったその足で近藤が他出し、たださえ物いりの所を またどこからか借りて急場に工面してきたものである事は、言わなかった。歳三も先ほど 近藤から廊下で言われた時には、なけなしの小銭をはたこうとしたが近藤はにっと笑って 受け取らなかった。ここは大将の出番、お前は使いに甘んじろという謎である。 「土方、先生よう……」 藤吉が下を向いた。鼻をすすっている。そのまま黙って、ついに男泣きを始めた。 「なんだよ。……いいから、しまっちまえ。」 歳三は、無理に藤吉の骨ばった手を取り、包みを握らせた。藤吉は泣きながらそれを両の 手にかかげて、拝み伏している。歳三は仕方なくもう一度包みを奪い取り、今度は直に、 藤吉の懐にねじこんだ。 「らしくねえな、藤吉。日頃の威勢はどうした。」 「……先生がた、どうか……お達者で……。」 藤吉は顔を上げられない。彼のような肩肘張って生きて来た男には、尊敬する師と仰ぐ者 があまりなかったのかもしれない。それだけに、薄い縁しかなかった近藤勇と土方歳三の 情けが不意に身にしみたのかもしれなかった。 襖をへだてた部屋の中では、藤吉の鼻をすする音につられて、寝ているはずの弟子の一 人が、こっそりと肩をふるわせている。沖田は、ごろ寝の皆には背を向けて、目を開けて いた。黙っている。酒臭い寝息が充満するのを避けるために、小部屋の窓が四、五寸ほど 開いていた。その隙間から、半分ほど白い顔をのぞかせた朧月が浮かんでいた。 |
| 4 |
| 翌昼下がり、である。早坂家の裏口に、中年増の女が訪ねてきている。下男の甚七が、 庭を掃いていて声を掛けた。 「何か、ご用で?」 「ああ、すいませんね。ここに働いている、お初さんを……」 呼ばれて裏庭から出てきたお初は、女に思い当たらない顔で頭を下げた。 「あのう、あたしの親戚の、おしげさんって……」 女はああ、というと急に声をひそめて、 「ごめんなさいよ。さっきのおじさんに言ったのは、うそ。」 「うそ?」 「取り次いでもらえないといけないと思ってね。」 「どなたでしょうか。」 「あたしは、たつ次って店で働いている者です。あるじの藤吉に、頼まれましてね。ご存 じでしょ。」 と、言ってちょっと笑いかけたその女は、昨晩沖田総司の膝の上に抱っこしてしまった、 お運びのねえさんの一人なのである。忙しい時間だけの雇いだから、二度だけ店に行った お初は会っていない。 「……藤吉さんが、なぜ?」 女は袂から薄い手紙を取り出した。 お初は、糊で封付けされた手紙を持って、急いで女中部屋に戻った。中には藤吉なりに 精一杯きれいに書いたつもりの仮名文字が並んでいる。 「二月八日 こいしかわ てんつういん、せんせいかた、いよいよおたちときまりたるよ し、おみおくりされたきかたあるときは、よろしくおつたへのほと、ねかひ上候………。」 お初は手紙を胸に抱いた。 二月八日、小石川伝通院。歳三、沖田たちが浪士隊として出発する日が決まったのだ。 一方奥の寝室では、靖志郎の病床にに付き添っているおりつがいる。主人の病状はなお も重く、靖志郎もすっかりやつれているが、看病のおりつの表情にも、疲労の色が濃い。 「りつ。」 「はい。」 「もう、やすめ。」 夫が静かに言った。昨晩も発作を起こして、薬のお陰でおさめたものの、おりつは眠って いない。 「いえ、私は大丈夫でございます。」 「そんな顔で、じっと見ていられては、落ち着かぬ。」 「………。」 おりつは煎じ薬の盆をさげに、台所へと入ってきたが、お初が竈の前で粥を炊きながら、 ぼんやりと考え込んでおり、背後のおりつに気づかない。 「お初?」 お初は、びくっと肩を揺らしてから振り返った。 「は、はい。」 「どうしたのです。ぼんやりして……」 お初は返事をためらったあと、決意したように顔をあげて、 「お話が……あの、お叱りを覚悟で申し上げます。」 と、声をひそめた。胸一つにおさめておくのは耐えかねたのである。 出発前夜の試衛館である。夜更けて、流石に興奮していた出発組も明朝の出発に備えて 灯りを消し、いびきの音が聞こえ始めていたが、歳三はなかなか寝つかれなかった。明日 から半月ばかりも歩けば京の都の空の下にいる。わかっていた事とはいえ、やはりこの男 にも血がざわめくような静かな興奮があった。 (京………京か。) 様々な想いが頭をよぎっては消える。年が明けてから、親類知人への必要な挨拶回りは、 着々と済ませてきた。お返しなしという了解の餞別も受け取った。昨今、政都の江戸より 京洛のほうが物騒な暗殺騒ぎが続いている、という事は多摩でも知識階層の庄屋や馴染み の商人たちは知っている。皆、将軍警護という華々しい名分を門出として祝いながら、そ の陰では大丈夫かと危ぶんだ表情もした。遠い先祖以来の将軍上洛ともあれば、行ってす ぐに都見物をして帰るというわけにもいくまい。また、歳三にはから手で戻るつもりなど さらさらなかった。大きな転換になる、という予想、勘のようなものが手足を火照らせて いる。そのせいで横になっても眠れないのだ。近藤はもう一刻ほど前から家族のいる奥の 居室に引っ込んだが、或いはやはり床の中で目を見開いているかもしれない。その血のた ぎりを妻のお常の体に打ち込んでいるのか、そこは一人身の歳三にはわからない。恐らく そうかもしれない。予定がわからぬほど長期の不在は夫妻にとっては初めてである。 交差するくさぐさの回想の中で、歳三は長い間さ迷ったあげく、長旅の前夜、体を温め てくれる女の一人も残っていないことにふと苦笑した。なるべく後のほだしがないように 捨ててすり抜けてきたつもりではあったが、本当は女たちから捨てられたのは自分のほう ではなかったのか。自分がなかば力づくで、骨のきしむほどに抱きしめ、腕の中で存分に 踊らせてやった女たちの誰ひとり、この夜に歳三を思い出してもいないのではないか。 別離の前、飽きるほどの情欲に溺れたお品でさえも、今ごろは亭主の胸に寄り添い、春の 夜の夢にいるのかもしれない。 (………おりつ………。) 考えても詮無いと知りつつ、やはり一度は腕の中に抱き、あと一歩という時に詰めること の出来なかったおりつを想った。あれは何だったのか。恋というにはあまりにうぶな惑い であった。歳三は、おりつに憧れただけなのかもしれない。手の届かぬ女、武士という上 位の世界の規約の中にきっちりと箱に納められて生きている女。だからこそ、ないものね だりの子供のように高価なものを手にしようとし、そしてその後に起きる面倒を思い知っ てとりやめたのだ、と。 歳三は、肩書きだけの武士になどさほど尊厳を置いているわけではない。むしろ、本来 の意味での「戦う男」としての武士ならば四角四面に縛られた家つきの武士どもより、ず っと自分のほうがなり得るはずだと自負していた。単に、生れ落ちた環境がそことは離れ ていただけだ、と。おりつは、その隔てられた世界の庭に踏み込めば手折る事の出来る花 のような存在だったのではないか。 しかし。いや、違う。とも歳三は思った。確かにおりつは、俺とは育ちも考えも違う。 だが元来、人が人に吸引されるまでに細々とした理由が必要なものだろうか。理屈などは 後から何とでもこじつける事が出来る。歳三は、わずかな機会のうちに確実におりつとい う女に、惚れたのだ。正直におりつを抱きたいと思い、また深く突き放される哀しみを見 て、引いたのだ。自分には、惚れたと思う女ひとり守る力がない。欲しいままに体を貫き 一瞬は我が物に組み敷いたとしても、その後の彼女を生かすすべがない。 おりつへの恋慕を失って、肉欲だけは浴びるほどに代償の女の中に捨ててきた時から、 歳三は試衛館に戻り、今何をしなくてはいけないのか、本能的に感知した。男としての、 怠惰な自分を叩き捨てることだ。幸いな事に、試衛館では口よりも剣、でものをいう腕の 剣客たちがごろごろと屯している。歳三の技量では元々追いつかぬほどの真っ当な実力を 持った連中が。少年の頃からわき目をふらず修業した彼らの剣を正道とするなら、歳三の 剣は確かに我流を含む邪道であろう。しかし、野に育った雑草のように、歳三には鉢植え の中で伸びた花にはないふてぶてしさと強さがあった。相手の長短を見、隙をついて食ら いつく。「土方さんの剣は人を殺す剣だ」、と後々まで言われるほど、恐れられ不気味が られた歳三の剣は、この頃にようやく、むくむくと土を掻き分けて育ちつつあった。 そしてその頃に持ち上がったのがこの上洛募集の話である。天運としかいいようがない。 その天運は、今夜の歳三の五感を覚まさせ、眠らせないのである。 (ガキの頃、石田の庭に矢竹を植えたっけな。) そんな事も脳裏によぎった。武士は戦時の備えに矢竹を植えるものだという。大人の誰 から聞いた話だったのかは定かでないが、次兄には内緒で小作の連中に頼み、探してきて もらって勝手に植えさせた。俺は農家は嫌だ、いずれ武士になるという少年の宣言を、兄 たちは笑いながら聞いていたが、あの頃から二十年を経て、世の中は急激に変わろうとし ている。もともとは死に値する罪であった主家からの脱藩が流行り、農民、町人あがりが 帯刀して諸国を巡歴し、現に、農家出身の近藤勇が一時は幕府の講武所撃剣教授の候補に のぼり、同じく清河八郎なる人物が浪士隊を提唱して実現するような世相になってきてい る。 流れ者同様の半人前でいる事は最早我慢が出来ない。たとえ京洛が噂の通りの死地であ ろうとも、ここでぐずぐずと三十を越していくよりは余程よい。 歳三は遂にそのまま眠りに就くことを中断して、そろりと部屋を出た。道場へ行った。 取り立ててわけはない。体を動かせば寝られるかもしれない。 道場の中は塵一つなく磨き上げられている。歳三はひとり、手にした真剣をすらりと抜 いて、型を行っている。刃が時折、薄闇にきらめく。 「……ふっ!」 暗がりの中の何かを断ち切ったように渾身の一振りを終えたあと、やがて、ぱちりと刀 を納めた。そのまま気を静め、無言で立っている。 「………。」 と、入り口に人の気配がして、振り向く。沖田である。 「お前も来たのか。」 「ええ……なんだか、眠れなくて。」 「ふふ。」 歳三と沖田はほぼ同時に、照れ臭そうな含み笑いをしている。 「……明日ですねえ。」 と、沖田は当たり前の事を当たり前に言った。 「夜が明ければ、さ。」 もう数時間後のことで、明日、という程の感覚ではない。 「なんだか、まだ嘘みたいだなあ。……今年は、江戸で花見ができないんだ。上野のお山 や、王子の桜もお預けか……。」 からく 「京は、花洛というほどだぞ。その花の都へ行こうってのに、おかしな奴だな。」 「花の都、ねえ。」 歳三は、日頃一番のはしゃぎ屋である沖田のぼんやり顔がいっそおかしくなってきた。 「お前でも、落ち着かねえのか。」 「そりゃあ……そうですよ。私は武州から出たことがないもの。それに……」 沖田は道場を見渡した。 「この、試衛館か」。 「うん。……いよいよ、閉めると思うと、なんだかね。」 沖田は歩いて、ぼんやりと、傷だらけの壁板に触れている。 「お前は子供の頃から、試衛館に住み着いていたからな。」 いわば、歳三のような寄食の気分ではなく、沖田にとっては居心地の良い家なのである。 「うん。ずいぶん雑巾掛けをしましたよ。あちこち、穴もあけましたしね。羽目板一枚、 節穴ひとつ、私が触ったことの無いところは、ないかもしれない。」 歳三はちょっと鼻白んで、 「そんなに寂しけりゃ、一枚はがして持っていけ。」 と言った。ようやく睡魔が訪れて、沖田の感傷につきあいきれなくなってきたのである。 沖田はあくびをかみ殺した歳三の顔を見てくすくす笑うと、 「どこにしようかな。」 とふざけて、羽目板の継ぎ目に指を掛けた。まさか本当に試衛館の板切れを抱いて出かけ るわけにもいくまい。 |
| 5 |
| 二月八日(一八六三年三月二十六日)、早暁。試衛館一同は道場に正座し、壇上では、 送り出す側の代表として、先代当主の近藤周斎老が、珍しく羽織を着けて座り、挨拶を受 けている。養子の勇に譲ってからはすっかり隠居然としていた周斎だが、この時は流石に 往年の長らしい貫禄を見せて、弟子の男どもの面構えを一渡り見渡してから、 「男の門出だ、長い口上はいるめえ。」 と、一息置き、 「ご武運を、お祈りする。」 と言った。 昨日までは若い剣客達が騒がしく足踏み鳴らしていた試衛館道場も、この瞬間から女と 子供、年寄りだけが暮らす文字通りの留守宅・隠居所となり、嘘のような閑静さとなろう。 この二月八日が、実質上は試衛館終幕の日でもある。 筆頭に構えた勇が、湧き上がる感興を抑えて静かに、しかし野太い声で礼を述べ、 「では、行って参ります。」 というのを機に、一同が上座にうやうやしく礼をした。 玄関では、近藤の妻、おつねを始め見送りの者たちが並んで頭を下げている。出発組は、 それぞれに高揚したおももちである。その面々は近藤勇、土方歳三、沖田総司、井上源三 郎(以上天然理心流)、山南敬助、藤堂平助(共に北辰一刀流)、永倉新八(神道無念流)、 原田左之助(種田流とも、宝蔵院流ともいう)以上八名。この日を境に長い旅立ちとなる。 集合所となった小石川伝通院には、雑多な浪士たちが二百数十名も押し寄せ、ざわめき に包まれていた。江戸中の浪士を寄せ集めた、という印象で、彼らの風体は実にさまざま である。多少はまともな武士らしい身支度を整えた者、一見して食い詰め浪人とわかる者、 博徒上がりの者。手にした得物もてんでんばらばらで、異様な軍団である。この雑多な男 たちの匂いの中から、後に世を震撼とさせる一団が生まれ出るとは誰もが想像しているは ずがなかった。出発となっても、規律正しく粛々とした将軍警護隊の行軍とはとても言い 難い。近藤以外は皆、平隊士として進み始めた列に紛れこんでいる。 伝通院の庭を出ると、沿道にもさまざまな人達が見送っていた。ただの見物人、家族、 知人らしき者……異様な旅装にこわごわと目線をそむける者、「がんばれよ」とのんきに 声をかける町人体の男、無言で挨拶をし合う者……。 試衛館の面々が並ぶ中で、沖田はこの軍列の珍妙な雰囲気に耐えられなくなったらしく、 ひそひそと歳三に耳打ちした。 「忠臣蔵の時は、もうちょっとまともだったんでしょうね。」 同じ浪士ながら隊列も群衆の見る目も、という意味である。 歳三が、ばか、という顔で、 「比べ物になるか。」 といった。後に「忠臣・内蔵之助」を略して忠臣蔵の芝居が一世を風靡し永く伝えられる 程有名になった赤穂浪士が主君の仇である吉良上野介の首を捧げに、浅野内匠守の墓所・ 高輪の泉岳寺まで凱旋の行列をした時は、よくぞ本懐を遂げた「義士」の勇姿を一目見ん とて江戸の群衆が群がったという。赤穂の浪士団の処遇には賛否続出し、多くの同情論を 跳ね除けても全員切腹という成敗を下した幕府であったが、時の将軍綱吉の独裁に意地を 貫いた浪士達の胸には誇らしい感興が沸いた事でもあろう。しかしその時から将軍も九代 を経て、同じ雪上の行列では先年、幕府大老井伊直弼が浪士に首を打たれて強権を失墜さ せ、少年将軍家茂は、不動の膝元江戸を離れて、はるばる都へ上らざるを得ない時代にな っている。浪士組はその将軍警護の為に出立するのであり、まだ赤穂侍のように己の目的 を果たしたわけでもない。つまり、列の行く手に待つものも知らぬ海のものとも山のもの とも分からぬ集団であった。大事を成した後の男の歩みと、まだ何も成さぬ男の歩みとで は、それぞれの面構えも人の見る目も違って当然であろう。 (忠臣蔵、か。) この時の何気ない一言が、後の新選組を大きく印象付ける事例へと繋がっていくのだが、 まさかこの時の歳三にもそこまでの予想はついていない。 「総司。やはり、義だな。」 「え?」 隣の沖田がきょとんとした。歳三は頭の回転が速すぎて、時々途中の脈絡を飛ばした言葉 が口をついて出る。 「義、だよ。只の浪士ならゴマンといるが、赤穂の侍は死しても義士と呼ばれ、その行い は義挙と呼ばれた。」 「義、ですか。」 沖田はわかりかねつつ相槌を返した。 「俺達は、ただ行列して歩いている浪士で終わりたくはねえ。」 「ああ、そういう事ですか。」 今度は何となく納得がいったような顔で、沖田がうなずいた。それからにやっと笑って、 「男子一生の大事、を成し遂げないといけませんね。」 とからかった。勿論冗談で、沖田には更に、この旅の後に訪れる大事の数々など予想だに していない。歳三は何を言われたのかわかったらしく渋い顔をした。 一行は、これから江戸を離れて中山道を上る事になっている。伝通院を出ての道筋で、 藤堂が沿道の連中をよそめに見ながらぼやいた。 「ちぇっ、俺の馴染みは誰も来ていねえや。」 「我々は、親類縁者には別れを済ませて来たものな。」 と永倉がなぐさめた。藤堂平助、永倉新八の二人は共に江戸の生まれ育ちである。家を飛 び出した格好ではあるが、一人くらいは当日の朝に様子を見にきてくれてもよさそうなも のであるが既に挨拶を済ませたのだから、と思ったら、原田左之助が茶化した。 「ふふん、平助の言っているのは、別の意味だろう。わざわざ見送りに来てくれるほど、 つまりはどの女にもモテちゃいなかったわけさ。」 藤堂が見透かされたように口を尖らせた。 「ちぇっ。」 しかしその時、若い娘の声が飛んだ。呼びかけられたのは誰もが思いがけぬ名であった。 「沖田様!」 皆、ぎょっとして声の方角を見た。行列から少し離れた橋の袂で、お初が、思い切って声 をあげていた。群衆に見られる恥ずかしさで顔を真っ赤にして可愛らしい手を振っている。 「沖田様。沖田様……どうかご無事で!」 一番驚いたのは沖田である。どうしたものかと思いつつ、ぎこちなく会釈する。お初も似 たように、これはぺこりと体を折った。娘が顔を上げた時には、男達の歩みが速くて、 沖田の背もその列の中に紛れ込もうとしていた。 「よう、よう……おやすくないねえ、色男。」 原田がどん、と肘鉄をくらわせた。 「知りませんよ。」 「いつの間に、あんなウブいのに手をつけたんだい、坊や。」 周囲の者たちが半ばあきれて、沖田をからかい始めた。沖田は小突かれながら「違う違う」 と必死で言い訳をしている。 「しかし、あの娘、どこかで見たような……」 「土方さん、誰だか知らねえか。」 と原田たちが歳三にたずねるが、 「………。」 歳三の答えがない。 「土方さん?」 歳三はふと我にかえって、 「あ……いや。………。」 知らぬ、と首をふってそのまま、また黙った。 歳三はお初よりも、まったく別のものに目を奪われていたのである。 (来たのか……。) しみじみと噛み締めた。目の奥に、たった今見た、おりつの面影がよみがえっている。 「………。」 お初の声の方を振り返ったとき、少し離れて、おりつが初めて会った日の淡い紅藤色の小 紋を着て、ひっそりと立ちつくしていた。はっと気づき、無言でまっすぐに見つめ合った。 だが、それもほんの数秒だったろう。 朝早くから、女ふたりがどのようにしてここまで駆けつけたものか、歳三にはその苦心 のほどはわからない。だが、ただ通りかかったというはずはない。本当はよそながら見送 るはずだったものを、少女が一目こちら側に気づかせようとの振る舞いだったに違いない。 おりつが命じた事ではなかろう。思いがけず振り向けられた歳三の視線が矢のようにおり つを射止めた時、おりつもそのまま、身じろぎもせずに同じ視線を返してきた。 それで充分であった。 歳三もそれ以上振り返らなかった。おりつは既にきびすを返して立ち去りつつあるだろう。 (……終わった。) 恋といえるほどの形はなかった。だが歳三の中で、ひとつのものが確実に終わった、と 感じていた。それは、おりつも同じ思いだったかもしれない。 「土方さん、あれ。」 沖田がふと、歳三の袖を引っぱって道筋の木立ちを指差した。 「ん?」 桜である。わずかだが、先の方にやっとほころび始めた枝がある。 「……ほう。」 今の騒ぎの真意を気づいていたかいないか、沖田はもう仲間から冷やかされるのから解放 されて、歳三の側に戻ってきていた。 さいさき 「花開く、とは幸先がいいですね。一句できそうじゃありませんか。」 「ふ……。」 確かに、何を書きとめても足らぬほどの興趣が今の歳三の心中にはある。 「そうか、桜と擦れ違いながら行くんだ。京では、まだ咲いているでしょうか。」 声が楽しげであった。京は花洛といったのは歳三である。 「咲いているだろう。いや、……咲かせにいくのだからな。」 長旅の果ての都の桜には間に合わずとも、である。 「それは、豊玉宗匠らしい。」 沖田は感心して、にこっと笑った。 「咲くとも。……これからだ。」 歳三が言った。その姿は一歩ずつ、春の陽射しの中を進んで行く。 (第一部 終) |