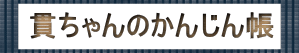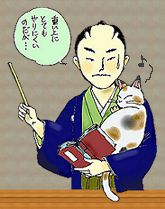| その1 |
前がきのページにある、新選組局中法度、巷間知られている通りの5条からなる文章を
そっくり引用いたしましたが、実際には法は4条しかなく、「私闘の禁止」は後世に加えられた
といわれております。生き残りの永倉新八の談話をもとに、作家の子母沢寛が、語調もよく、
さもこの通りに出来あがっていたかのように、文章を創作したもののようです。
道理で語句がうますぎる……現代の社訓でも、あんな上手なリズム感のある文句は、
なかなか作れないでしょう。 |
| その2 |
「新選組」と「新撰組」。いまでもよく混同して表記されています。当時の人たちは、音が合って
いればさほど文字は気にしなかった、という点も確かにありますが、(校正が入るわけではなし)
字義からいえば、「新たに選ばれた者」という意味で、また、朝廷から賜った正式名称として、
「選」が正しいです。資料探しの折には、どちらの字を使っているかも正確性の参考になること
でしょう。
前がきの文のように上洛して「新選組」を結成したわけではなく、当初は「壬生浪士組」といって
おりました。それで、新選組隊士をやや軽蔑した呼び方が「みぶろ」(壬生浪人)となります。
文久三年八月十八日の政変のあとからが、「新選組」です。 |
| その3 |
作品中では、一般のイメージ通り、新選組隊士たちが「隊服」として、有名な浅葱色(あさぎいろ
=淡い青色)に白の山形模様のついた羽織を着ていることにしておりますが、実際にはあまり上
等の品ではなく、作った数も少なく、新選組(あるいは、壬生浪士組のころ)のごく初期にしか、
用いられなかったというのが事実のようです。慶応年間には、上下ともに黒い羽織袴を着てい
て、ああ、あれは新選組だとわかった、という話が残っていますので、案外渋い制服でした。
黒ずくめのほうがよっぽどこわそうですが、わかりやすく、また作者もあの衣装が好きなので、
登場人物たちには、あえて「浅葱のダンダラ」を着せています。 |
| その4 |
井上源三郎甥、井上泰助の年齢ですが、当初、慶応三年13歳というふうに書いたのですが、
本当のところが今ひとつよくわかりません。しかし戸籍の通り昭和2年71歳没、という根拠で
いくと、当時11歳くらいになってしまう、いくらなんでもそれでは幼なすぎだろう、嘉永4年の
生まれで数え17満16くらいか?普通は元服が15歳、ということで、新選組の末期には少年兵
と呼ぶべき人たちが何人かいますが、入隊時にはいわゆる「鯖をよんで」年齢をいつわった人
がいるかもしれません。血気盛んな少年たちのこと、兄や先輩たちについて参戦を望んだので
あれば、子供扱いは好まなかったのでしょう。白虎隊の史話にも「大人でも怖気づく戦に子供
らが黄色い声を揃えて進むのを見て涙が出る」という部分がありました。 |
| その5 |
土方歳三が石田散薬の行商をしていたのが何歳までか、という話ですが、おそらく上洛前の
数年には、もう歩いてはいなかっただろう、と思われます。天然理心流に正式入門した頃には
やめたのではないかな、と思いますが、どうも薬売りの歳さんが出てこないとお話になりにくい
というのでその格好で登場してもらいました。若い頃、小野路小島家の老母に風邪薬を届けて
その処方をこまごまと説明している手紙が残っています。で、頼まれれば家伝薬の他のものも
持っていってあげたりしたんじゃないだろうか、ということで音羽町松代屋の場面となりました。 |
| その6 |
歳三の若い頃の話に、婚約者のことが出てこないじゃないか、と思われる方もいらっしゃるの
ではと思いますが、私自身はあまり「お琴さん」という女性と歳三の婚約話に信を置いていま
せんので省きました。歳三は四男で独立できる職もなく、婿養子でもなければ妻帯できない
はずですから、「嫁を持たせよう」という発想も「婚約者の女性が何年も待っている」という状態も
想像しにくいからです。女性の結婚は早くても、男性の場合は、例えば商店の奉公人などは
一人前に独立した所帯を持たせてもらえるまでには相当の年数が必要で、三十代半ばを過ぎ
てやっと結婚という事も珍しくなかったといいますが、歳三が「男子一生の大事をなしとげたい」
から琴女との結婚を延期したというのが本当ならば、それとないお断りだったのではないかと
思っています。そもそも本人の認めていない恋愛の噂話は願望も憶測も入ったりして尾ひれが
ついていることが多いのだ、しかも後からだと美談悲恋にされやすいというのが千太夫の持論
らしいです。当事者どちらかの証言が欲しかったところです。 |
| その7 |
沖田総司の少年時代の話ですが、両親はすでに亡くなり、姉お光らと暮らしていたであろう、と
いう位で不詳としたほうがよかろうと思っています。日野の井上家から婿養子の林太郎が入って
長姉と結婚した事や、沖田家も白河藩からは浪人していたらしい事から、多摩の日野住まい、と
設定しました。天然理心流入門も九歳説と十一歳説の二種類あります。
そもそも、没年齢も遺族が明治以降に書き残した「二十五歳」という説が長く信じられていました
が、上洛時の届け出からそれより二つ上の二十七歳(当時は数え年ですが)で亡くなったという
のが正しかろう、というふうに変わってきています。という事でそもそも有名になる予定のなかっ
ただけに生涯の謎が多い人ですが、あまり肩肘はらずに少年沖田の伝説をつないだ創作、と
いう形でお読み下さい。 |
| その8 |
沖田の幼名「そうじろう」ですが、記録に残るものでは「沖田惣次郎藤原春政」であり、墓碑には
「宗」の字が使われています。惣は総領(惣領)、宗は宗家につながるとすれば、どちらも実質上
の嫡男として相応しい文字ですが、小説などでは「惣次郎」「宗次郎」のどちらも使われている
ようです。事実上は、宗次郎として生まれ、林太郎を養子として当主にした時点で「惣二郎」と
した、というのが正しいと思われるのですが、千太夫は個人的な文字の好みの問題で、「宗次郎」
に統一しました。 |
| その9 |
沖田林太郎夫婦が、末弟を試衛館に弟子入りさせた時点で、沖田家の籍はまだ白河藩に残って
いるというのが実説です(暴露)。それをいれて年代を合わせてしまうと浪人の子としての自由な
書き方が出来ないもので(^-^;;)物語を書き始めた時のまま勢いで続けております。お詳しい方は
ひらにご容赦ください。 |
| その10 |
土方歳三の書簡、を御覧いただければ想像がつくように、歳三は上洛前の住所を日野の石田村と
しているようです。姉のぶの婚家である日野宿佐藤家に居候していたというのは有名な話ですが、
小説のように江戸の試衛館に長く居着いていた時期があったのか、正直なところわかりません。
でも田舎暮らしのままより、江戸の都会暮らしで世慣れした歳三のほうが後年の姿がわかりやす
い気がします。よってこのままでいきます。(爆) |
| その11 |
最近気になることに、新選組には「死番」(しばん)という、屋内突入の順番を当番制にしていた、と
いう新説が定説化してきつつあります。つまり、市中見廻りの時、京都の狭い民家の中に入口や
階段など、狭いところへ最初に入っていく隊士はもっとも危険が高いので皆がしり込みし、敵を
逃さないために4人1組で1から4番までを決め、トップバッターを「死番」と呼んだそうだという伝聞。
出典がどこなんだか覚えていないんですが、なんと皆様のえぬえ○けーの某歴史番組までが、さも
もっともらしくそうナレーションしていらしたもんでぶっとんだ。新選組在京時代、助勤(組長)藤堂平助
は「サキガケ先生」と異名をとったくらいで、若くてもその度胸を買われておりますし、箱館戦争の時
野村利三郎という隊士が、他の幕臣の隊長の下でいつも先鋒を任されないと口論になったなんてい
う話があります。近藤勇はあの池田屋で敵が何人いるかも把握できない夜の屋内で先頭をきって
おります。「先陣は武士の誉れ」しかも実践が最優先の新選組。日頃から仲間の寝込みを襲う抜き
打ち深夜訓練までやっていたといいます。半端なサラリーマン根性でいたらつとまりません。
私が見廻り小隊の隊長だったらおっかなびっくり、の奴には戦いのトップバッターは任せません。
その日調子のよい選手を指名します(笑)。現場の建物を見て4人かそこらの配置だったらすぐ
その場で下知したでしょう。初戦から一人斬られるという想定より不審者がいれば逮捕して、無事
全員生きて帰すのが本筋でしょう。新選組がめったやたらに浪士を斬ったというのは創作です。
「戦場で隊長が死んだらヒラは生きて帰るな」という規則を発した新選組ですが、じゃあヒラの
隊士はどうなってもいいというわけではないのです。と、いうわけで順番押し付けっこから始まったと
いう「死番」説は私は信じていません。隊士からのナマな記録ではないからです。
|
| |
(以下、気づいた時に更新してまいります) |