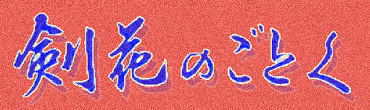 |
| 第 10 回 |
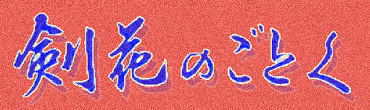 |
| 第 10 回 |
| 第 一 部 暁 闇 |
| あ ら た ま (七) 新 珠 |
| 1 |
| 早坂の家では、このところ靖志郎が毎夜遅くまで書き物をする事が続いていた。靖志郎 は江戸藩邸での勘定を扱う役目の中では群を抜く才を示していたが、病身は如何ともし難 く、本来なら国元の勤めも何度か往復して経験を積んでいるはずの年令になっても、江戸 勤めの年月は変わらなかった。うつる病でないのを良いことに公邸では体を気遣いつつも 歳末の繁忙が近づけば靖志郎に負わせる仕事を増やしてくる。しかし、それもこの頃は日 暮れ前早々に帰宅して、後はいつ横になってもよいように布団を述べたまま、自室篭りの 時間で賄うようになっていた。 そろそろ夜も四つを過ぎ、家の中は戸締りも済んで静もっている頃である。おりつが薬 湯を持って、靖志郎の部屋に入って来た。 「お薬を……」 靖志郎は書面に目を落としたまま、振り返らない。冷笑を浮かべた。 「薬?ふふ……毒でも入っているのではないか。」 「何をおっしゃいます。」 仕事を家でするようになってから、靖志郎の言葉の棘が増しているようである。 「早く死んでほしいのだろう。」 「あなた。いい加減になさいませ。」 おりつはきっとした表情で夫の背を見返した。 「怒ったか。」 「あたりまえでございましょう。」 いつもなら取り合わずに過ごすのだが、おりつの声にもつい、責めるようなものが混じっ た。文机の上薬の椀を置こうとして袖口をつまみ、手を伸ばした。すると、靖志郎が唐突 におりつの腕を掴んだ。薬がこぼれる。 「あっ。」 驚いて瞳を上げた。夫の冷えた視線がぶつかった。 「お前こそ、その取り澄ました顔は、いい加減にしたらどうだ。」 「私が?」 靖志郎はおりつのあごに手を当て、 「この、殊勝ぶった顔で男をたぶらかすのか。」 「おっしゃることがわかりませぬ。」 「嘘をつけ。お前には、好いた男がいよう。」 意外に直截な質問を受けて、おりつはつい、黙った。夫の視線を逸らしながら、 「知りませぬ。」 と答えた。言えるはずがない。 靖志郎は無言のまま、夜具の上におりつを押し倒した。 「何を……おやめ下さいまし。」 「………。」 「いや!」 おりつは肩と足を縮めて、靖志郎の手を強く拒もうとした。 「何がいやだ。」 「こんな……いやでございます。」 「夫婦の間で、何の不思議がある。」 理詰めな男だけに、こんな時でも正論を吐く。本来、夫が求めれば否も応もなく、おりつ が肌を許すべき相手は世の中でこの靖志郎でしかない。月の障りは数日前に終わっていて、 それは靖志郎がおりつの着物の上前を分けてしまえばすぐにわかる。殊更に拒む理由がな いのである。それでも、おりつの中では夫に屈する事への強い反発が生まれていた。つい、 言わでもの言葉を発した。 「今さら……夫婦だなどと、おっしゃいますか。」 靖志郎が、カッとこめかみに怒りを走らせて、おりつの頬を打った。 「………!」 手を上げられたのは初めての事である。おりつはそれでも、逃れようとした。靖志郎の腕 が襟を掴んで引き戻した。どさり、という音と共に掛け布団の上へ体が落ち投げ出した足 が畳に積んだ書物の山に当たって、一部が崩れた。 「やめて……」 おりつは反射的に、揉み合う事での物音を怖れた。靖志郎はいっとき手を止めた。 「お前が逃げるなら、お初を呼ぶ。」 おりつが目を見開いた。 「あの娘に手をつける。それでもよいか。」 「なんという……卑劣なことを……あっ……」 靖志郎はそのまま手を動かし、おりつの衣服を解き、ついに屈服させた。おりつの内部に、 無遠慮に異物の侵入する痛みが走った。 半刻も経ったであろうか。いや、どれほどの時間が経ったのか、おりつには正確にはわ からない。一分、一分が非常に長く感じたが、体が繋がっていた時間は案外に短かったの かもしれない。髪はすっかり乱れ、折り敷かれた襦袢は皺になって、剥ぎ取られた湯文字 が畳の上に乱れていた。おりつは力を失った操り人形のようにぐったりと身を横たえてい た。横の夫は疲れ果てたように眼を閉じている。薄闇に浮かんだその顔を冷え冷えと眺め ながら、おりつは、これが一頃は胸を高鳴らせて待った事のある夫婦の交わりであろうか と、唇を震わせていた。無理につかまれた二の腕には指の形のあざが出来、うっすらと痛 みが残っている。 「私が、憎いか。」 「………。」 寝入ってしまったのではないらしい。先ほどとは違い、衝動を吐き出した後の男の声は、 ごく静かなものに変わっていた。 「憎めばいい。」 「………。」 「私も、母も、この家も……憎み、怒り、それが当然だ。」 「なぜ、このような……」 と、おりつが言った。 「ひどいことを……?」 生娘のお初を犯す、とまで言ったのは嘘であろうと信じたかった。靖志郎の暴力的な心の 動きは、自分にのみ向けられたものと感じている。おりつはゆっくりと半身を起こした。 その背に向かって、靖志郎はあくまで静かに、次の言葉を吐いた。 「私は、母もお前も、憎んでいる。」 しばらくの間があった。 「私には、かつて……愛しんだ女がいた。」 「えっ。」 おりつは、嫁いでから五年も経って、初めて靖志郎の口から、容易ならぬ過去を紐解かれ る事となった。 「……文字通り身も心も許し合い、その女といるためになら、どんな苦労も厭わぬとまで 思った。千代乃という、岡場所の女だった。……しかし、私に対する時だけは客としてで はない。本当の女の気持ちで抱かれていると言った。女郎の嘘に騙されていたとは思わぬ。 あと二年の年季が開けたら通う家を借りようと約束をしていた。しかし私が病に倒れた後 ふっつりと姿を消した。いうまでもない。母が手を回したのだ。千代乃は鞍替えをした町 で、死んだ。」 「………。」 「その頃、母が見付けてきたのが、お前だ。」 「………。」 「病や女のことは、外へはひた隠しにしてな。出世に関わる、縁組に差し支える。早坂の 家はどうなるのだ……傍目には滑稽なほど、躍起になっていた。……そして格好の相手と して見繕ったのが、町医者の孫娘だ。何よりこの先、病が長引いても医者と薬には困らぬ。 お前の祖父は裕福で、名声もある。幸い当の娘は器量も評判もいい。藤本の家格が多少低 かろうと、嫁として迎えるに対面は立つ。お前の家の立場ではまさか不足とは言うまい。 これは一刻も早くものにせねば……すべて、母の筋書きどおりだ。お前は何も知らず、こ の家の生け贄に選ばれたというわけだ。」 「おやめ下さいまし。」 「そうでなくて、あの母がわざわざ、我が家より低いところから嫁を貰ったりするものか。 それまでは縁組さえ、出世の道具と考えていたはずだ。少しでも身分のある家の娘をと物 色してな。ところが私の病、いかがわしい女との仲、お前との縁談は……母にとっては、 とんだ思惑違いの末、不承不承、手を打ったというところだ。女郎と心中をされる位なら まだましだというわけだろう。ふふ……そんな思いで迎えたお前に、やさしくするはずが ない。」 「もう、やめて……」 「それでも、子ができさえすれば早坂の家は守れる。私の気も変わるだろう。ところが、 肝心の息子はまたも発作を繰り返す。せっかくあてがってやった嫁にも、跡継ぎはできな い。またも思惑がはずれたわけだ。ますます剣呑にもなろう。」 「靖志郎どの。」 「揃いも揃って、無駄なことをしたものだ。千代乃の死んだ時から、私は……」 「………。」 「何もかも、物憂くなった。……どうでもよくなってしまった。」 「………。」 「かといって、自ら死ぬ気も、家を捨てることもせず……ただ、生きている。お前のいう 通り、卑劣な男だ。」 「聞きたくありませぬ。」 「こうはっきり言われると、こたえるか。」 靖志郎は、自嘲気味に笑った。 「私は……」 この後に続く言葉を思いつかないまま、おりつは茫然と側の夫を見た。得体の知れぬ他人 がそこで息をしているように見えた。 「出て行きたければ、それでもよい。想う男がいるなら……」 と、靖志郎はここでまた凍りついたような表情に戻り、 「私の前から去れ。」 と言い放った。表向きは無論、離縁は男にのみ決定権がある。しかし、女のほうが望めば 彼は明日にでも淡々と非の打ち所のない去り状を書くだろう。 「なぜ、そのような」 「うわべだけで尽くされるのはかなわぬ。」 これは案外に正直な感想であったろう。おりつは、形の上では早坂靖志郎の貞淑な妻であ っても、夫婦として心が通わぬ実態は自分が一番よく知っている。 「では、なぜ。」 おりつはきっと顔を上げて、 「なぜ、抱くのです。」 と言った。隔てを置いている事を認めはしても、靖志郎の看病にも世話にも、心を砕いて きた事に偽りはない。身を売る女の替わりにされた、という心外の念がおりつを苛んでい る。 「私が、憎いのなら……なぜ、抱いたりなさったのです。」 「わからぬ。」 「………。」 「お前を苦しめることで……いや、」 靖志郎は視線をはずし、横を向いた。 「ただ、女が欲しくなった。それだけだ。」 「うっ」 おりつは打ちのめされ、乱れた身なりのまま、部屋を走り出た。靖志郎の顔は黙然とし たまま何事か考え込んでいる。 おりつは自室に走りこんだ。そのまま襟元をかき抱き声を殺して泣く。 「………。」 泣くより他に自分を救う手立てがなかった。懐紙で拭い去ったはずの内腿に、ツ、と温か いものが伝い流れた。夫との儀礼的な営みは絶えて久しかったが生々しい陵辱の感触が蘇 り、おりつはぞっと屈辱のあまり身震いをした。 「……だれか助けて……だれか……」 微かな声に応える者は、誰もいない。おりつは崩れた髷の後ろから簪を抜き、先端を喉に 当てた。誰か、ではなく本当に呼びたかった名が口元から零れ落ちた。 「……歳三どの……歳三どの……。」 おりつは簪を胸に抱くようにして、首をうな垂れたまま夜更けの畳の上に座っていた。 翌朝は晩秋から既に初冬と言ってよいほどに抜けるような濃い青空が広がっている。居 間では隠居の松枝が、靖志郎の朝食を給仕していた。 「……何やら、頭が痛くて起き上がれぬとか……旦那様の朝げにも顔を出さぬとは、情け ないこと。」 「………。」 靖志郎は黙って椀の味噌汁を口に含んでいる。 「私は熱があっても、父上のお支度の前に寝ていたことなどございませんでしたよ。」 「母上。」 黙っていてくれ、という顔で靖志郎が咎めた。 「喧嘩でもしたのですか。何やら、夕べは騒がしかったようですけれど。」 「口出しは御無用に願います。」 「また母をのけ者にして……」 松枝は不服そうに、剃り上げた眉根のあたりをしかめた。 「でも、お陰でこうして、久しぶりにそなたのお世話ができるのですからね。りつには、 たまに休んでいてもらっても構わぬのですよ。」 「………。」 靖志郎は憮然として箸を置いた。 「あら……もう、召し上がらないのですか?」 食欲を無くさせたのは自分なのだが、それでも靖志郎が身支度を終えて出仕する時になる と、玄関の式台にうやうやしく手をつかえて、丁寧な仕草で頭を下げた。この老婆にも、 かつてはこの家の主婦として毎朝当主を送り出した歴史がある。 「行っていらっしゃいませ。」 一方おりつの部屋では、お初がつききりで、粥を給仕している。 「旦那様は……」 とおりつがきいた。 「大奥様がお支度を手伝って、無事お出掛けになりました。」 「そう……」 「どういうんでしょう。まるでご自分のご亭主のように、いそいそと……お声まで若返っ ていらっしゃいました。」 「以前は……お母様がすべてなさっていたのですから。」 「それはそうですけど。若奥様が具合が悪いっていうのに、何も嬉しそうになさらなくっ たって。」 嬉しそう、という言葉におりつは苦笑した。 「正直でいらっしゃるのですよ。」 「私には、まるで若奥様が仮病のような言い方をなさって……本当にもう……」 「………。」 昨晩の靖志郎の話を聞いてしまった後では、姑がおりつに不満を抱く理由もわかる気がし て、おりつは黙った。初めから相容れるはずのない人間関係というものがあるのだろう。 「ちゃんと、お熱があるって申しましたのに。」 「ちゃんと、というのは、おかしいわね。」 お初はあら、という顔で恥ずかしそうにしてから、 「とにかく、寝ていらっしゃらなくては駄目ですよ。若奥様。堂々と寝ていらっしゃれば いいんです。」 堂々と、というのもおかしな用例だが、おりつは今度は逆らわずに、はい、と言った。 勝手口では初老の下男の甚七が、戻ってきたお初の顔を見て、心配げに尋ねた。 「若奥様のあんばいはどうだい。」 「うん。お咳もくしゃみもないし……大丈夫だと思う。ただ……」 「ただ?」 「なんだか、たいそう疲れていらっしゃるみたい。」 甚七は得心顔でうなずいた。 「そりゃあ、気苦労だなあ。無理もねえ。旦那様も大奥様も、難しい人だから。」 お初もこくり、とうなずく。朝方、部屋へ挨拶に行った時、無理に起きようとしていたお りつの顔色は尋常ではなかった。 「こんなシンキ臭い家に来て、気が滅入らねえ方がどうかしてら。」 「昔から、そうなの?」 「いや。先代の旦那様と靖志郎様は、そんなに悪いお人じゃなかったんだけどね。少なく とも俺はそう思っていた。」 「へえ……」 甚七は声をひそめて、小指を立てた。 「先代様にこれができてからだね。この家がおかしくなったのは。」 「それって……乙弥様ってかたの、母上様?」 「そうさ。まあ奥方があれだからね、旦那の気持ちはわからねえでもねえが……段々お帰 りが遅くなるし、泊まりがおおっぴらになる。しまいにゃ、別宅で倒れて亡くなったんだ からなあ。」 「あらまあ……」 妾の家で壮年の当主が急死したというのは外聞の良いものではない。それをひた隠しての 葬儀の時には、未亡人と嫡男はさぞ嫌な思いを味わったであろう。 「ご遺言で乙弥様を引き取ってはみたものの……うまくいく筈がねえ。」 「はあ……」 「靖志郎様も、ますます暗くなっちまったな。」 「込み入ってたのねえ。」 「ただ、靖志郎様は昔っから、頭が良くて期待が大きかったからね。いきおい、お袋様の いれこみようはひどくなっていったね。まあ、亭主に見捨てられて、息子を身代わりにす るってのは、ありがちな話さ。きれいな嫁さんがきて、ちっとはよくなるかと思ったんだ が……いけねえ。おりつ様はいい人だが、おとなしすぎる。」 「我慢しすぎなんですよ。何でも。」 「あれじゃあ、つぶれちまうかも知れねえ。」 お初は急な熱のおりつを見た後だけに、潰れるという言葉には敏感に反応した。若妻の身 がもたなくなってこの家を出て行くのではないか、という危惧は奉公人の誰にでも一度や 二度はよぎったことがある。 「いやですよ……あたし、若奥様がいなくなったら、すぐにでも出て行く。」 「おいおい。」 「啖呵きって飛び出してやるんだから。」 お初は義憤にかられたように、盆を持ってすくっと立ち上がった。 祖父から貰っている熱さましが効を奏したのか、おりつの熱は夕刻には下がった。その 夜は靖志郎の帰宅は遅かった。おりつはつとめて何気なく、出迎えた。 「お帰りなさいませ。」 「起きてよいのか。」 「はい、もう……申し訳ございません。」 一過性の発熱だったのだとすれば、原因は二人ともにわかっている。交わす言葉は少なく てよかった。おりつは靖志郎に従って部屋に入り、淡々と脱いだものを片付けた。その背 中に、声がかけられた。 「りつ。」 「はい。」 「昨夜は……どうかしていた。」 「………。」 おりつが驚いたように振り向く。 「気が立っていた。許せ。」 「いいえ……」 抑揚のない会話が交わされた後、おりつは早々に部屋を出た。靖志郎の真意をはかり兼ね ている。それは、ひそかに抱き始めていた歳三への思慕に対する嫉妬か、それとも病から 来る、体が利かなくなることへの焦燥か、職務での苛立ちか……漠然とした不安が、靖志 郎をあのような言動へと駆り立てたのかもしれなかった。 (何かが……不安なのだ。でも……私は靖志郎どのの不安を受け止めていただろうか。) 実は昨夜、おりつは靖志郎に抱かれている時、目を閉じながら歳三の顔を想った。そう する事で、夫への屈辱に耐えようとした。それはおりつ自身にも意外な反応だった。だが、 ふと夫の声で、その幻想はかき消えた。靖志郎はその間一言だけ声を漏らしたのである。 「りつ」と。 おりつはその声ではっと目を見開いた。しかし靖志郎の表情は読み取れなかった。その後 の夫の言葉を思い返せば、抱かれたことがおりつへの愛情からとは信じることができなか った。ただほんの少し、靖志郎の心のほころびを垣間見たような思いがした。 「………。」 おりつは寝室にぼんやりと佇んでいる。雨戸の外には風が出てきたようだった。 |
| 2 |
| 試衛館では寒稽古の日々が続いていた。冬とはいえ、激しく体を動かしているとうっす らとした蒸気が立ちのぼり、床板の上には汗が落ちるほどになる。このところ道場では、 数年来希有な現象が起こっていた。食客連中に比べると、試衛館を離れてぶらぶらと出歩 く事の多かった歳三が、このところずっと詰めきりで、しかも殆どの日時に顔を出してい る。今日は今日で、北辰一刀流出の藤堂平助と打ち合っていた。歳三の剣には我流の修行 でつけた独特の癖があり、天然理心流の位では近藤、沖田に遠く及ばないが、型にとらわ れない実戦ではむやみに強い。藤堂はそれを知っているから、かの商家の用心棒を歳三に 代替わりさせたりしたのだが、この男も若いながら遮二無二剣術修行に励んで、向こう気 の強さでは一番といわれたくらいの使い手である。その藤堂が、今日は歳三の気迫に押さ れ、ついに竹刀を落として羽目板まで吹っ飛ばされた。 「まだまだ!」 「いや、……まいったっ。」 藤堂は肩で息をしている。歳三は汗を飛ばして、振り返った。 「誰か、次。」 居合わせた者が、一瞬躊躇して顔を見合わせた。 「では、私が。」 これも若手では猛者といわれる斎藤一がすっと立ち、歳三と稽古を始めた。激しい竹刀 の音が響く。稽古を見ていた原田左之助、ちょんちょんと沖田の肩をつつき、道場の外へ 連れ出した。 道場脇。 「どうしちゃったの、あれ?」 と、原田は親指で道場の方向を指差した。 「さあ。」 「帰ってきてから急に、稽古の鬼になっちまってよ。」 この原田左之助も、実戦の喧嘩になれば無鉄砲なほどに強いが、生真面目な稽古は嫌いで、 その点では鍛錬をサボって歳三の行商のあがりで安い酒でもおごってもらうほうが好き、 というほうに馬が合う。それが、このところの歳三は原田などほったらかしで自分の剣技 を磨くことのほうに一所懸命なのだ。おいてけぼり、のような気がしたらしい。 「迷いが吹っ切れたって所じゃないですかね。」 「その顔は、何か思い当たる節があるな。」 「別に……」 沖田は含み笑いをした。歳三が何日か雲隠れをして、沖田にだけは「女にふられてきたよ」 と物憂げに告白してから後、がこの状態なのである。色恋にはとんとうとい青年だが、歳 三の一念発起の理由は、何となくわかるような気がする。 「ちぇっ。けち。」 原田が口をとがらせると、その時、庭の方から、山南敬助が現れた。 「こんな所で、内緒話かね。」 「ああ、山南さん。お帰りなさい。」 沖田は、丁度いい助け舟、とばかり山南に微笑んだ。 「うん。ただいま。」 この山南敬助は、仙台の出らしいというだけで出身地のことはあまり言いたがらないが、 江戸にはある程度の年数住み着いて、北辰一刀流の免許を取得している。その後でなぜか このちっぽけな試衛館道場を訪れ、近藤勇と立会い、負けた。なぜ負けたのかわからない。 しかし、その後で純粋朴訥な近藤の人柄に惚れこんでしまい、わざわざ天然理心流に入門 しなおして、多摩の田舎で催される流儀の行事などにも律義に名を連ね、出稽古にもちゃ んと出かけていく、という、食客の中ではやや風がわりな存在である。しかし、学識家で もあるから、旧出身流儀とのつきあいもいまだに広い。数日前、深川の知り合いに用があ ると言って、普段よりは若干身なりを小奇麗にして出かけ、今戻ったのである。 「山南さんが居続けの朝帰りとはな。深川通いとはうらやましい。」 と、原田がからかった。深川は言わずとしれた辰巳芸者の町で、遊興の土地である。山南 は笑った。 「とても、そんな金は無いよ。……同流の門人で、深川佐賀町に私塾を開いておられる方 のところへ、行ってきたんだ。」 「私塾?」 と、沖田が尋ねた。 「うん。伊東大蔵(後の甲子太郎)先生と言ってね、文武共に高名な人物だよ。」 「知らんなあ。」 と言ったのは原田である。沖田は素直に続けた。 「また、国事についてのお話をなさりに?」 「うん。他の友人たちの所も回ってきたのだがね。伊東先生の所が最も有意義だった。時 節柄、ああいう優れた見識を持つ人と交わることは、大いに役に立つよ。」 「北辰一刀流、か。大流儀のご出身はさすが高尚でいらっしゃるね。」 原田は権威ばった事が大嫌いである。他の食客たちのように、江戸に出て有名流派を学ん だ事がない。当時の有名道場は、剣術は二の次で寄れば時勢談義という政治サロン化した ところは多かった。一匹狼の原田左之助の好みに合うはずはない。 「原田君、棘のある言い方だね。」 「あそこの流儀は、剣術のみならず弁舌も教えるんですかい。 「いや、人が多いから、自然とさまざまな議論を交わすことにはなるが……しかし、それ も自分を磨く上では大切な事だよ。」 「ふん、俺はそんな堅苦しいことは性に合わんな。それくらいなら、始めからこんな所に 居候したりはしないね。」 「こんな所はないでしょう。」 と、沖田がチャチャを入れた。沖田は「こんな所」の天然理心流生え抜きである。 「俺はここの、ざっくばらんなところが気に入って転がり込んだんだからよ。」 「それは、私もそうだが。近藤先生の質実剛健たる気風や、道場ののびのびとした素朴さ は、他流にはない美点だからね。」 「そうそう。」 「しかし、これからは我々も、時勢に無関心では済まされなくなると思う。好むと好まざ るに関わらず……だ。時勢を知らずして国は語れないし、語らねばわからない事もある。」 「その辺は、山南さんにまかせておきますよ。」 原田は面倒臭くなったのか、ぷい、と立ち去ってしまった。山南は首をかしげて、 「原田君は、なぜ……腹を立てているのかな。」 と、これもやはり不快げな顔をした。温和なようで、融通のきかない短気さがこの男にも ある。もっとも、試衛館の連中は大なり小なり短気者ぞろいであるが。 「山南さんも、わりと鈍いところがおありですね。」 沖田はいつもと変わらない口調で、さらりとこの年長者の悪口を言った。 「鈍い……私が?」 「ええ。」 にこっと笑っている。 「なぜ。」 「原田さんは、大坂で修業したでしょう。それももともとは槍のほうが得手なお人です。 いろいろな所を流れ歩いて、やっとこの試衛館に肌が合って落ち着いた人だ。江戸でも一、 二を争う大流儀の北辰一刀流のご出身である山南さんとは地金が違う、教養も違う。日頃 仲間だと思っている山南さんに、そういうつきあいがある所を見せられると、何となく面 白くないんじゃないかな。」 「別に、そんなつもりはないんだがなあ……」 「山南さんは、真面目だから。」 「そうか。気にさわったのなら、すまなかった。」 「ふふ、しかし原田さんは、昼飯でも食ったら今怒ったことなんか忘れていますよ。」 気にするほどの事ではない、というのである。沖田はこう見えて、子供の頃からこの試衛 館に住み込んでいる若者だから、出入りする人間を観察する目に長けている。山南はこだ わるタイプだが、原田はカッとした後でもけろりと忘れてしまう事がある。 「君にとっても不快だったかね。」 「私は、別に……山南さんのことは尊敬しています。」 どちらかというと大雑把な人間が集まった道場の中で、山南の知識、教養は群を抜いてい た。しかも、この男はそれを下の者にでも懇切丁寧に説く。時にはそれがくどい、と感じ られる事もあるが、沖田は若い天才選手にありがちな教え下手で、口頭での細かい説明が 苦手であるから、山南と組んで出稽古に行くとその点をきっちり補ってくれ、多摩の田舎 の弟子たちにも、沖田の実技に補足して実にわかりやすく噛み砕いて技術を教えてくれる。 現代なら公立の小・中学校の先生にでもなれば良い教職者の手本にもなれるだろう。 「いや……君の方がよほど、頭がいい。」 「ご冗談でしょう。私も、難しい話はとんと苦手です。」 沖田は正直に驚いた。この若者は、自分が賢いなどとは露ほども思っていないし、人から そう言われることにも慣れていない。 「君は、まだ若いんだ。本気で書物を読むなり、いろいろな見聞を広めれば、私ごときは すぐに追い越してしまうよ。」 「まさか。私は、これだけです。」 沖田はくすっと笑って、両手の指を組んで剣を振る真似をした。 「もう一人、目下これに取りつかれている人がいますよ。」 「剣に?」 沖田はええ、と言って道場の窓を指差した。山南が中をのぞき込む。激しい気合いと共に、 歳三が斎藤を打ち込み、二人とも、汗が飛び散る程になっている。 「ほらね。」 「ほう……どうしたんだ、土方さんは。」 「高尾山に籠って、天狗に術でもかけられてきたんじゃねえか、って、井上さんが。」 「斎藤君を押してるじゃないか。」 「今日は、ほとんど休みなし。」 「君は、相手をしなくていいのかい。」 「ああいう時の土方さんは、こわいですからね。手負いの猪に向かっていくようなもんで す。」 「手負い……?」 「いけね。」 沖田は小声で言って、肩をすぼめた。歳三がおりつに失恋したことは、他の誰も知らない のだ。 「さっき、三本に二本とられちゃった。分が悪いから今日は逃げますよ。」 山南が驚いた。 「君が?」 山南の頭には、道場内の強弱の順列がきちんと出来上がっていて、喧嘩はいくら達者でも、 正規の稽古で土方歳三が沖田総司、斎藤一に勝るとは思ってもみないらしい。前学期の成 績表を基準に人を計ってしまう教職者のような癖が、この男にはある。 その時、 「ほう。」 と、背後で声がした。二人がびっくりして振り向くと、いつの間にか周斎老先生が、背後 に立っている。このところの寒気で長めの風邪をひいて奥に引っ込んだきり、道場には顔 を見せていない。ひなたぼっこのついでに庭に出て来たらしい。綿入れの半纏を引っ掛け ており、その厚みの中に埋もれた周斎は余計にちっちゃく見える。 「先生。」 「しーっ。……どれ、」 周斎は道場の窓をのぞこうとして背が届かず、仕草で沖田に「持ち上げろ」と示した。沖 田は何の気もなく師匠である周斎を「抱っこ」して、視線が入る位置に届かせてやった。 山南はぎょっとした。 「ふうん……歳め、本気になったか。」 「中で、御覧になったらいかがです。」 と、この会話は抱っこのまま。 「なに、いいのさ。……おお、おろしていいよ。」 沖田は周斎を降ろした。 「あの気組が出てくりゃ、もう大丈夫。」 気組とは、天然理心流が最も好んで使った用語で、気概、気合などの事と同意である。 周斎は何事もなかったように、飄々として奥のほうへ歩いて行ってしまった。沖田と山南、 ぽかんと顔を見合わせている。 「思うに……」 と、山南が呟いた。 「はい?」 「天然理心流には、不思議なひとが多いな。」 「そうですか。」 沖田は首をかしげて、また笑うともつかぬ笑いを浮かべた。自分も「不思議なひと」の一 員に数えられているとは思わないらしい。 |
| 3 |
| 師走も半ばに入った。夕刻は震えが来るほどの寒さである。早坂家では、にわかに玄関 の方が騒がしくなっていた。小者の弥助が、血相を変えて飛び込んできたのである。 「た、大変でございます。旦那様が……」 その声で、おりつと松枝、使用人たちが玄関に駆けつけた。勤めに出ていた靖志郎が倒 れ、自宅まで戸板で担ぎ込まれてきたのだ。 「靖志郎!」 松枝が悲鳴を上げた。 蒼白な顔面でぐったりとなった靖志郎を見るや、おりつは奥へ走り込み、戸棚から気付 け薬を取って戻った。その間にも皆口々に、「旦那様」と呼び続けている。 「お初、これを湯に溶いていらっしゃい。甚七、ともかく、奥にお運びするのです。弥助 は、小川町の古谷へ駆けておくれ。必ず、順徳先生をお連れするように。」 と、おりつは素早く使用人たちに指示を出した。 「へいっ!」 小者の弥助が、後も見ず駆け出して行く。 「靖志郎、靖志郎……しっかりしておくれ……」 使用人たちが再び戸板を持ち上げようとする中で、息子の顔のあたりをのぞきこみ、病人 におろおろとまつわりつく松枝を、おりつは厳しく一喝した。 「お母様、おどき下さいませ。」 数分後には、自室の布団に寝かされた靖志郎がいる。甚七たち男の使用人は、廊下や庭先 に降りて、遠巻きに様子をうかがっていた。お初が薬湯を持って来る。 「靖志郎、靖志郎……」 今度は発作が大きい事を、母親の松枝には過敏にわかるのであろう。靖志郎の父親も出先 で急死している。呼びかけても答えない息子のそばで狼狽するばかりであった。おりつは 受け取った薬湯の椀を靖志郎の口元へ持って行くが、病人の意識がないため、入らない。 「………。」 おりつはくっと顎を上げて、薬湯を自分の口に含み、そのまま口移しに飲ませた。 「!」 松枝が、まわりの者たちが、息を飲んで見守っている。おりつは一気に口の中が溢れない よう注意して、苦い薬湯を夫の唇へ流し込んだ。ごくり、と喉仏が動いた。 「あなた。……あなた。」 軽くだが、手のひらで靖志郎の頬を叩いた。ふっ、と目を開いた。 「あなた。」 「靖志郎!」 「りつ、か……」 ぼんやりと目を開いて、靖志郎は両脇の女二人のうち、おりつだけを真っ直ぐに見た。 「はい、ここにおりますよ。もう大丈夫でございます。今、祖父を呼びにやりましたから ご安心下さいまし。」 靖志郎がかすかにうなずく。おりつは、しっかりと靖志郎の手を握った。藩邸から外気の 中を歩いたために心臓に来たのだろう。冷たくなっている。おりつが丹念にこすってやる と靖志郎はそのまま目を閉じた。混濁ではなく、安心して眠りに落ちたらしい。お初は少 し離れて、涙ぐんでいる。やがて、松枝が呆然とした顔で、ふらふらと出て行った。病人 の目には、気丈なおりつの顔しか入らなかったのは明らかであった。おりつは靖志郎の顔 色にわずかに生気が蘇ってくるまで注視した後、初めて松枝が開けたまま出て行った障子 に気づき、 「お初、障子を……ああ、それと、水を汲んできて下さいな。」 と言って、自らもほうっと吐息をついた。お初は返事をして、そっと障子を閉め、部屋を 出た。廊下で甚七がそっと寄ってきて、耳打ちをした。 「御新造様の、勝ちだな。」 お初はくすん、と鼻を鳴らして、 「もう。」 と言うと、そそくさと台所の方へ行ってしまった。甚七は腕を組み、嘆息を漏らしている。 その頃、松枝は自分の部屋に引き籠もり、うなだれて座っていた。放心したように、ひ っそりと涙を流していた。その顔は、誰も見る人はいないが、急に年寄りじみて弱々しい 表情に変わっていた。 おりつの祖父である老医師の順徳が診察を終え、別室でおりつと話をする頃には、冬の 夜はすでに更けていた。日頃はこの早坂家を嫌って、常備薬の工面のみを援助してきた順 徳だが、孫娘のおりつが「すぐに呼べ」と言うほどの急変であるから、夕闇に駕籠を飛ば して駆けつけたのである。 「家の近くで倒れたのが幸いじゃった。気付けを飲ませたのが早かったのが効いたな。」 「はい。」 「しかし、今回のはちと発作が大きい。当分は絶対に安静を保つこと……もちろん、出仕 は厳禁じゃ。少し持ち直したとしても、決して目を離してはならぬ。下の用も、この部屋 で済ませるようにしたがよい。急に立ち歩いて寒い厠で力を入れれば危ない。心の臓を、 なるべく上げ下げせぬほうが良いのじゃ。この時節ゆえ、風邪には万端の注意をされるよ うに。それは奉公の者にも気をつけさせる事じゃよ。」 「はい。」 順徳は熱い茶を口に含んだ後、しばらく沈黙して、それから大きく息をついた。 「おりつ。誠に言いにくいが……年が明けたら、覚悟を決めておいた方が良い。」 「おじいさま。」 おりつは驚いて目を開いた。重い病人でも容易に見放さぬ名医、という世評を得ている祖 父の口から、こうした宣告を聞くのは初めての事であった。 「桜の頃か、菖蒲の頃か……それはわからぬがの。」 年が明ければ、江戸は早春に入る。もっても晩春、或いは初夏という診立てなのだ。靖志 郎に翌年の一年は最早ない。重い沈黙が流れた。 |
| 4 |
| さて、文久二年大晦日の夜である。試衛館では掃除も済み、すっかり新年の準備が整っ ていた。沖田、神棚のしめ飾りを直していると、歳三が入ってくる。 「総司、行くぞ。」 沖田は、うへっという顔をした。 「はい。……寒そうだなあ。」 「歩いていりゃあ、さほどでもねえさ。」 暦の上ではもう間もなく春に突入するのだが、除夜の夜気はまだまだ肌を刺すほどに寒 い。玄関には、手持ち無沙汰な藤堂平助と原田左之助が見送りに出てきた。歳三と沖田は 並んで座り、草鞋を履いている。 「日野の八坂様へ、初詣でですってね。」 藤堂がにやにやして、薄い無精ひげを撫でている。ツケの掛け取りが年内最後の集金で探 し回っているので、日の出までは道場にお篭りを決め込むつもりなのであった。原田も同 様である。 「ああ。」 と、歳三は早くも笠の紐を結び終わっている。万事、細かい事は速い。 「このクソ寒いのに、わざわざご苦労なこった。」 原田が呆れたような声を出した。日影の水溜りは夕刻から凍り始めている。 「でしょう。お寺やお宮なら、江戸に掃いて捨てるほどあるっていうのにね。」 沖田が草鞋の紐を結ぶ手を止めて、ぼやいた。歳三にどやされた。 「馬鹿。正月の挨拶回りがあるんだよ。」 「わかってますよ。すぐ馬鹿っていうの、やめてほしいなあ。」 藤堂と原田はくっくっと笑っている。 「まあ、今年は特別ですからな。」 「ああ。」 「いとま乞いも兼ねて、か。沖田、御馳走責めで大変だぞ。」 「いやあ……原田さん達は、出掛けないんですか。」 「我々は他にあがり込むような所はねえしな。ま、ここらでぶらぶらしてるよ。」 「寝正月を決め込みますか。」 「いっそうらやましいや。」 「総司、早くしろ。」 気の早い歳三は、すでに玄関の外へ出ている。沖田は「はい」と返事してから後の二人に、 「土方さん、なぜあんなにせかせかしているのか、わかりますか。行く所が多すぎるんで すよ、きっと。」 「え。」 「なるほど、これのいとま乞いか。」 と、原田が小指を立てた。沖田はにっと笑って、 「お礼参り。」 と悪戯っぽくうなずいた。 「律義に回ってたら回り切れんのじゃねえか。」 「違いない。」 沖田たち、げらげら笑っている。歳三が戻ってきて、ごつんと沖田の頭を小突く。 「何を馬鹿言ってんだ。」 「痛いなあ、もう。馬鹿馬鹿って言わないで下さいったら。」 嫌がる沖田の首をつかむようにして、試衛館を出た。大晦日、江戸の繁華な通りとは反 対の方角へ向かう路上で、提灯をさげて、ぶらぶらと歩く二人連れである。夜目にも、息 で前が曇るほどに白い。 「しかし、……本当に我々が、京都へ上るんですかねえ。」 ふと、沖田が感心したような、人ごとのような声を出した。 「本当さ。近藤さんが、浪士組肝煎の松平主税介様に確かめてきた話だ。間違いはねえ。」 「よくそんな偉い方が、じきじき会って下さいましたね。」 「一介の浪人、近藤勇にか。確かに……それだけお上のご威光も揺らいでいるということ さ。だから、将軍のご上洛警護に浪士を抱えたりせねばならん。」 「十ぱひとからげ、ですか。」 「総司、口が悪いぞ。」 「すみません。しかし、本当にお役に立つのかなあ。いや、我々はともかくですよ。中に は支度金欲しさの、相当うさんくさい連中も応募するという噂です。」 「そりゃあ、そうだろう。しかし、近藤さんが行く、というのだから、それでいいんだ。」 「ええ。」 二人の話の内容は、こうである。 歳三は、先だって外出から戻って近藤の居室に呼ばれた。 「山南の言ったこと、本当だった。」 近藤は興奮すると、細かい表現を省く癖があった。しかし、外出した用向きは歳三もすで に知っている。 「ふむ。」 歳三の前には、浪士募集の檄文が置かれている。 「今日、講武所教授の松平主税介様に、お目通りを願い、真偽を確かめてきたのだ。三月 の公方様ご上洛に先立ち、京都市中の警護のため広く有意の浪士を募り隊列を組むという。 腕に覚えがあり、尽忠報国の志があれば、身分の上下は問わない。」 この頃の京都では時の帝孝明天皇が異人を怖れ忌み嫌う事激しく、逆に幕府は諸外国の 恫喝に負けて故・井伊大老の政策以来、流入する外国勢力の要求を入れてなし崩しに上陸 を許しつつあった。幕府の弱腰に対抗して、天皇主権での攘夷、を求める声が沸き起こり 遂に、十四代将軍家茂が、徳川開幕の頃の秀忠以来じつに二百年もの慣例を破って、直々 に上洛して天皇に目通りを願い上げねば治まらない、というところまで尊皇攘夷の声が響 いていたのである。京阪では、過熱した尊攘志士らが幕府を軽んじる事甚だしく、或いは 役人、公家、或いは内輪での争いの挙句、暗殺騒ぎが後を絶たないというところまで町が 荒れていた。しかし、江戸でも世相の混乱を反映して、かつてならあり得なかったほどに 脱藩の浪人らが闊歩するようになっている。将軍上洛ともなれば、幕府の警備は大幅に京 洛方面に割かれる事となる。留守居の江戸に、不逞どもを野放しにしておけばどのような 騒ぎを起こされるかわかったものではなく、幕府としてみれば、この機に得体の知れない 連中をひとまとめに取り集め、とりあえずは江戸の町から追い出してしまおう、あわよく ば京の浪士対策の手駒に、江戸の浪士で腕の効く輩を当てれば毒をもって毒を制す、の一 石二鳥である。と、そこまであからさまな内意を示してはいなかろうが、実態としてはそ んなところである。この奇策を知人のつてを通して幕府に提案したのは、北辰一刀流の免 許で、尊攘派とも交流の広い出羽郷士の「清河八郎」である。彼は薩摩藩の過激派を扇動し て寺田屋事件の内紛で頓挫し、自身もつまらぬ事で人を斬りお尋ねの身ではあったが、こ の懸案には、「身分経歴を問わず有為の人材を集め、幕府御用に活用すべし。」として、 参加者と認められた者の犯罪歴は恩赦とするという虫のいい提案も含まれていた。が、こ の時の近藤、土方は勿論そんな細かい事情などは知らない。数百年ぶりの将軍上洛という 大きな変動に際し、百姓町民であろうと、腕さえ立てば幕臣同様、警護の役に採用すると いう。かつて、実力主義で募集したはずの幕府講武所の剣術指南役の一人として候補にあ がりながら、結局は農民の出自が災いして選に漏れた近藤勇からみれば、今度こそは雪辱 の好機と奮い立った事であろう。政府である幕府が、コネも金も関係なく浪人の「公募」 を行う等という事は、滅多にあるものではない。増してやその役目は「天皇のおわす京都 に上り、将軍の御用で、剣をもって警護を勤める」という華麗な装飾がついている。この 話は、先の北辰一刀流出身の山南敬助や藤堂平助、同じく大流儀の神道無念流出身の永倉 新八などが小耳にはさんできた。最も的確な情報源は、知に優れた山南敬助であった。 「ふん……広く、といったって……北辰一刀流や神道無念流のような大道場にはこんなも のを回して、試衛館にはなしのつぶてじゃねえか。」 歳三は、鼻であしらうように檄文を見て不平を垂れた。いくら公募といっても、人数に限 りのある話でもあり、江戸の通津浦裏まで瓦版売りがばら撒いて歩いたわけではない。勇 ましい美辞麗句を漢語で並べた募集の広告は、江戸でも有力な道場筋を通して配られ、人 に広まったのである。天然理心流には、宗家の近藤勇のところにすら来なかった。 「それは、いいではないか。山南や、藤堂、永倉……彼等のお陰で、この報にいち早く接 することが出来た。俺は、嬉しいと思う。」 近藤は、まだ幕府内部の人間と面談してきた晴れがましさのほうが気分的に勝っているの か、歳三が差した図星にも乗らずに、鷹揚に答えた。 「まあ、あんたの人徳さ。」 歳三の悔しさは、いくら自分が早耳の世間通であっても、こうした大流派間での情報は そうそう集めようがなく、他流出身の食客たちが近藤の耳に直接入れ、自分が後手に回っ たという負けず嫌いから来ている。話の本意はともかく、江戸中でぶらぶらしている浪人 剣客たちにとって、これが大きな転機になる機会であるかもしれない、という事は、独特 の勘でわかっている。何しろ幕府の金で、今政争のまっ只中である京の都へ行けるのだ。 再々ある話ではない。 「人づきあいは、しておくものだぞ、歳。」 「………。」 「微力ながら、我らが上様のお役に立てる、千載一遇の好機が来たのだ。松平様は、お手 前なら申し分なしとまで仰せになった。大樹公(将軍のこと)のご連枝が、もったいない ことだ……」 近藤はその時のことを思い出したのか、感激のあまり目がうるんでいる。歳三は、ひそか に苦笑した。 「道場の連中は、何と言っている。行くのか。」 「相談は、お前が最初だ。」 歳三は目を細めた。内心は近藤のこういう信頼を嬉しく思っている。 「歳。どうする。」 近藤は大きな口から息を吐いて、ぐいっと角張った顔を突き出した。 「あんた、行きてえか。」 近藤はぐっと考えて、再びはあっ、と息を吐ききった。 「……行きてえ……。」 大きな口がへの字になった。 「じゃあ、決まりだ。俺も行くよ。」 歳三が答えるにはひと呼吸ほどの合間もなかった。かえって、近藤が拍子抜けをした。 「おい、随分かんたんに言うな。」 「ごちゃごちゃと理屈を言ってもはじまらんさ。あんたが、道場主の座を置いても参加し たいというなら、従うまでだ。俺だけじゃねえ。総司も行くだろう。井上さんも……それ に山南敬助、藤堂平助、永倉新八、原田左之助、たまに顔を出してた斎藤一。俺のみたと ころじゃ、ついて行くのはこの連中だな。」 「それだけの人数が出て行ったら、この道場は……」 道場主は近藤勇、塾頭は沖田総司。実質的な運営補佐としては土方歳三、山南敬助が動い ている。井上は最古参の古株の一人で、道場周辺の事情もよく知っている。永倉、原田、 藤堂は居候だが、天然理心流とは違う当世風の技術を身につけているから、町人の弟子等 には人気がある。もっとも、他流の彼らは居候歓迎、という太っ腹の近藤勇がこの家を出 れば、妻子が留守をする試衛館に居座る理由すら成り立たない。歳三はあっさりと、 「もぬけの殻さ。まあ、すっぱりと畳むんだね。」 「ううむ。」 近藤は、また考え込んだ。 「養父上が、寂しがるだろうな。」 「何、周斎先生なら分かって下さるさ。別に今生の別れってわけじゃねえんだ。」 「京は、遠いぞ。」 一度ははりきっておいて、後からは悲観的な要素を思い出して口にするような、案外細か い面が近藤にはあり、それが短所でもあり長所になる時もたまにはあるのだが、歳三は一 蹴した。 「遠いもんか。あんたが行く気なら、俺ぁ、アメリカでもオロシャでも行くぜ。」 近藤が、カッ、というような音を出して吹き出した。 「お前、オロシャがどこにあるか知っとるのか。」 「知らねえ。まだ行ったことがねえからな。」 二人はからりと笑った。 近藤は、決意してきっぱりと、 「よし。歳、行くべえ。」 と、拳を突き出した。 「おお、行くべえ。」 歳三も、多摩言葉になって拳を突き返した。 と、いう経緯があって、場面は再び、歳三と沖田が歩く大晦日の道に戻る。 「土方さん?」 「ん?……ああ。」 回想から戻って、歳三は横の沖田に返事をした。 「弱りましたよ。」 「何が。」 「実は……林太郎義兄さんまで、浪士隊に加盟するって言い出したんです。」 「ほう。」 沖田林太郎というのは、総司の長姉ミツの婿である。これも多摩の井上家出身の天然理心 流門人で、今は沖田家の微禄は藩籍を離れており、浪人である。子供もいる。 「お光姉さんが、文で知らせて来ましてね、……弟も亭主も他国へ行くんじゃ、心配らし い。もしかしたら怒っているかもしれない。」 「おのぶ姉も、似たようなものだ。しかし、お前の姉さんは武家の人だからな。うるさく は言わんだろう。」 二人とも親がなく末っ子だから、何かと面倒を見てくれた姉にはどうも頭が上がらない、 という共通項を持っている。男の兄弟は出世の好機と喜びもするが、女きょうだいは何で も心配が先に立ってこまごまと小言を言うものである。林太郎は篤実な人柄で婿養子とし ては何も問題がないが、義弟とは違って剣の腕はさほどではない。お光は聡明な女だから そうは言わないが、一家の柱の単身赴任はやはり危ぶむであろう。 「言わない方が、気詰まりですよ。」 「ふふ……。まあ、お前がそそのかしたんじゃないってことは、言ってやるよ。」 「よろしくお願いします。まさか京都へ行ったきりってことはないんでしょう?上様の御 滞在は、どの位になるんでしょうね。」 「行く前から、帰りの事を心配したって始まらん。」 「それはそうですが。」 沖田がぼんやりと答えた後、どこからか、除夜の鐘が聞こえ始めた。遠いが、空気が澄ん でいるからよく通る。 「あ……始まった。」 「うん。」 二人が、立ち止まって耳を澄ました。沖田がいつになくしみじみとした声で、 「今年も、暮れますねえ。」 「うん……暮れるな。」 「思えば、この一年はいろいろありましたよ。」 「年寄りみたいな事を言うな。」 再び歩き出した。 「世の中が騒がしかったですからね。攘夷だ攘夷だって……お題目みたいにかまびすしく なった。まずご老中安藤様が坂下門外で襲われた。やっと上様のご婚儀(和宮降嫁)が整 ったと思ったら、今度は生麦の事件、京都では、寺田屋の騒ぎ……それだけじゃない。こ の所、お公家様や役人の暗殺がひっきりなし。ついこの間は品川で異人の屋敷が焼きうち にあったし……いやあ、物騒な年でしたね。」 沖田は指を折って数えながら、しかしさほど世を憂えているというような深刻な声音では なく、あっけらかんと歩いている。 「ふん。山南にふきこまれただけあって、だいぶん詳しいな。」 「……聞いてあげると、嬉しそうだから。」 「は、は。」 歳三は笑った。確かに、山南がその手の話をしだしても沖田ならうんうんと言って素直な 生徒でいられるだろう。大体、人の話をなんでも面白がって聞く癖がある。しゃべる相手 がいないと、買い物に行った先の青物屋のばあさんとでも話し込んでいる。 「まだあるだろう。……そういうお前の、麻疹。」 と、歳三はその年の事件簿の一つに、沖田の大病を挙げた。 「ああ、あれは……いやだな、あんな風に寝込むのは、二度とごめんだ。」 なぜか運悪く沖田だけが大流行中の麻疹に罹患して、当時は死病の一つであったがからく も助かった、という事がある。出稽古先の小野路村で発病したから、関係者を巻き込んで えらく心配をかけたものだ。 「麻疹は一度かかれば、一生ならねえそうだ。」 「そう願いたいです。今年は麻疹とコロリ(コレラ)で何千と死人が出ましたからね。私 も駄目かと思った。」 「お光姉さんの手を握って、泣きべそをかいてたものな。」 「うそですよ、熱でうなされていただけです。」 歳三はにやっと笑った。 「そうかね。」 沖田は、ぷん、と口をとがらせている。しかし、急に思いついたらしく反撃に出た。 「土方さんだって、今年は重い病にかかったじゃないですか。」 「俺が?」 歳三はきょとんとして、 「……何の。」 と言った。麻疹もコロリも、この男には寄り付きもしなかった。風邪で寝たくらいである。 沖田は他の事を言いたかったらしく、ふふっ、と笑ってから、 「お医者様でも草津の湯でも、ってやつ。」 「……馬鹿野郎。」 歳三は照れたような、怒ったような顔で口元を歪めた。勿論、この文句の後には「恋の病 はなおりゃせぬよ」という歌詞が続く。確かに、歳三が病に近い思いでおりつを求めた日 々がある。あんな事は初めてであった。 「大丈夫。誰にも言いませんよ。」 「うるせえ。」 二人は、遠い鐘の音を聞きつつ歩いた。 やがて多摩川の近くで、うっすらと初日がさしてきた。東の空を沖田が指差す。 「土方さん。」 「うむ。」 二人は、無言で日の出を待っている。文久三年、やがて新選組誕生の年が明けようとし ていた。もちろん、歳三も沖田も、この年から始まる運命の急変を知るよしもない。ただ 朱に染まりくる光を見つめている。太陽がぽっこりと丸い姿で現れると、沖田は深呼吸を し、くるり、と振り返って、やや改まって頭を下げた。 「新年、あけましておめでとうございます。今年も、どうぞよろしく。」 沖田は朝日を受けて、清々しく笑った。歳三は眩しげに目を細め、ややてらいながら、 「おめでとう。こちらこそ、よろしく。……総司。今年は、大変な年になる。忙しいぞ。」 「はい。まず、年始回りがね。」 沖田はくすくす笑っている。歳三は一瞬力が抜けてまたむっつりとした顔になり、まずは 日野宿への道を急いだ。 |
| 5 |
| 年明けも松の内が過ぎて、やや静けさを取り戻した江戸は馬場下町穴八幡宮の門前であ る。あるじが床に伏せており、おりつは儀礼上の年賀や見舞いの答礼に何軒かの知人の家 を忙しく回った後であった。供はお初一人である。例の、茶店の前を通り掛かった。ここ ですでに歳三の姿を見なくなってから、もうしばらく経つ。 「休んでいきましょうか?」 お初に声をかけた。 「いえ、私は……」 勿体無い、というふうにお初がかぶりをふった。おりつは「そう……」と言って、何気な く店の前を通り過ぎた。近頃は靖志郎の病状がおもわしくなく、どこへ出ても歩みが急い で、あまりゆっくりとしていくことはなくなっていた。ここから曲がれば、あの藤吉の店 へも通じるという静かな小道にさしかかった時、お初がためらいがちに呟いた。 「近頃、……お見掛けしませんね……。」 おりつは複雑な表情で黙っている。 「あのお方……」 「お初。」 その言葉が誰を指しているのかわかった時、おりつは立ち止まり、静かに振り返った。 「そなた、あの時……」 あの日、お初が忘れ物に気づいたと言って、急に社のほうへ引き返した事を思い出してい る。恐らく、近くにいた歳三に気づいて、それとなく場を外したのだろう、と思い当たっ たのはその後の事であったが。お初は、うつむいている。 「あの方とは、関わりはないのです。気の回し過ぎですよ。」 「でも。……いいえ。」 お初がまた、やや強めにかぶりを振った。 「お初?」 「あの方は、若奥様がお好きなんです。きっとそうです。」 「………。」 「もしかしたら、若奥様も……なのにお二人とも私の前ではひとことも口を……目を合わ せようともしないで……だから私……」 「お初。」 たしなめるような声を出した。いくら気配をさとっていても、主人に対して言ってはなら ない事がある。あの日思わず立場を忘れ、心を奪われた事がおりつの罪だとしても、お初 を共犯にしてはならなかった。 「だって、だって、あんまり、お気の毒で見ていられなくて……せめて、その位は……」 お初は立ちすくんで、急に泣き出した。 「そのくらいは、許されてもいいと思いました。だって若奥様がおかわいそうです。」 お初は、子供のようにしゃくり上げている。 「……馬鹿ね。」 おりつはそっと近寄り、お初の髪をなでてやった。 「そなたが泣く事はないのですよ。」 悪戯でした事ではない、のもわかっている。 「あの方は……私に会うより他に大切なことがおありなのです。私も……」 おりつは、ふと黙った。 「いいえ。お初にそんな気持ちを持たせるようでは、いけなかったのですね。」 懐紙を取り出して、お初の顔をふいてやった。静かに微笑して、行きましょう、と帰路を 促した。 その夜、おりつは、靖志郎の病室とは別の間で、夜具の中にいる。疲れているのに寝つ けないまま「たつ次」の小部屋での歳三の言葉を思い返していた。忘れよう、と思いなが ら何度蘇った場面であったろう。 ―――俺は、あんたに惚れている。――― 歳三の胸に抱き寄せられた時の光景は、忘れようとして忘れられるものではなかった。恋 らしい恋もせずに、真っ白なまま嫁いできたおりつにとって、男の腕に身を投げ出して激 しい心の揺れを感じたのは本当に、あの一夜きりであった。 ―――あんたが、好きだ。ただ、会いたかった。顔を見たかった。こんなのは初めてだ。 嘘じゃねえ。――― 強引な口づけをされた所で、回想がとぎれた。 「………。」 おりつは夜具の中で、自分の肩を抱いた。歳三に引き寄せられた時、そのまま抱かれたい と思った瞬間は嘘ではない。が、拒んだ自分も嘘ではなかった。欲しいものは欲しい、そ れが男だと歳三は言った。女として、身も心も愛された体験がおりつにはない。恐らくは 我を忘れるほどの歓喜の時が襲ってくるのだろう、とその嵐の中に身を任せてしまいたい 衝動はあった。しかし、外の男に抱かれた後で身仕舞いをしてお初を連れてこの家に帰る 自分を、おりつは想像する事が出来なかった。ただ一時の事であっても、激しい後悔に苛 まれたに違いない。一度抱いてしまった後の歳三がどうなるのか、その事にも想像が及ば なかった。 (あの言葉だけでいい……あのひとときだけで……よかったのだ……) おりつは目を閉じた。明日はまた、朝からの雑事が待っている。 初春というのにしんしんと寒い、という日が戻った。昼さがりに、おりつは紅梅の花を 生けた花器を持ち、靖志郎の病間に入ってきた。病人は静かに目をあけて、尋ねた。 「……雪が降っているのか。」 「はい。」 靖志郎は朝早くに薬を飲み、飲むと急に眠くなる、と言っていた通り午後までこんこんと 眠っていた。午前のうちに降り始めた雪は粉雪からぼた雪に変わり、今ではうっすらと積 もり始めている。靖志郎は障子の方を見て、 「開けてくれ。」 と言った。 「寒うございますよ。」 「いい。」 おりつが障子を開けると、靖志郎は首を横に回して、じっと雪の庭をみつめている。おり つはそのまま枕元に回り、持って来た梅を飾った。 「それは……どこの?」 と尋ねた。この家の梅は淡紅色と白で、まだ蕾が固い。 「はい。お初が、買い物の途中で見つけて、人からいただいてきたのでございます。」 「早咲きだな。」 おりつは微笑してうなずいた。 「その家は、湯屋だそうでございます。その裏庭に梅の木があって、風呂釜の熱で暖かい ために、毎年、町で一番の早咲きなのだとか。」 「そうか。」 靖志郎が、梅の花を見ている。やがて穏やかな声で、 「美しいな。」 と言った。 「……お初が、喜びましょう。」 雪が少し風に揺らぎ始め、おりつは、そっと障子を閉めた。 「りつ。」 「はい。」 「それを……」 と、靖志郎は文机の上にあるかなり厚い三冊の書き付けを指した。靖志郎の筆跡によるも ので、几帳面に紐で綴じてある。おりつが手に取った。 「勘定方の松本左馬之介に届けてくれ。」 「はい。これは……?」 「お役目の引継ぎ、申し送りの事柄がまとめてある。左馬之介は、私の後任だ。それを読 めば、大体は事足りるはずだと伝えてくれ。」 「はい。」 「うむ。……勤めている間にまとめるつもりだったのだが……遅れた。」 その夕刻、藩邸の勤めが終わる時刻を待って、おりつは勘定役の松本左馬之介の家を訪 れた。松本は靖志郎と同じく江戸定府の家に生まれた朋友だが、国許の娘と縁組をして養 子に入り、ここ数年は藩領の勤めとなっていたが、昨年の秋にまた役替えで江戸の藩邸に 戻っている。靖志郎の後任として呼び返されたというのが本当らしい。年は同じだが、国 の妻女には既に二人の子をなした父親である松本のほうが、夫よりいくつか老けて見えた。 実直な人柄は同僚の間にも評価が高い。 「左様か。……靖志郎が、これを……」 松本は真剣な顔で手にとって読み始め、途中でいたたまれなくなりぱたりと閉じた。 「かたじけない。大いに助かる、と礼を申していたと、お伝え下され。」 おりつがうなずく。 「靖志郎はこのために、また無理を重ねたのではござらぬか。」 と、松本は旧友らしく、まずは体を気遣った。 「秋頃からひそかに何か書き綴っていたようでございます。ただ、私には何も申しませぬ。 気のつかぬことでお恥ずかしいようでございますが、そうかも知れませぬ。」 「………。」 松本は、沈痛な表情で絶句している。 「松本様……?」 「りつ殿。……それがしと靖志郎とは、親友でござった。」 「………。はい。」 「少なくとも、それがしは今でもそのつもりでおります。あいつは……言葉が少なく、時 には切れ者すぎて、快く思わぬ者もあった。しかしそれがしには、尊敬すべき大切な友人 でありました。」 「……ありがとうございます。」 おりつは頭を下げた。 「どうか、いたわってやって下され。あの才気ある男が、思うように働く事すらできぬよ うになるとは、さぞかし無念でござろう。」 「はい。……。」 松本は書き付けを丁寧に文机の上に置き、それからは火鉢を囲んで、茶飲み話のようにな った。聞いてもらいたい事がある、という松本の申し出を、おりつは断らなかった。 「りつ殿。靖志郎は、昔から一種近寄りがたいところはあったが……決して性根の悪い男 ではござらぬ。それなりに人と交わり、勤めをこなし、時には、遊びもした。それが、あ る時を境に、人が変わった。さよう、もう五、六年も前になろうか……」 「それは……千代乃という人のためでございましょうか。」 「ご存知であったか。」 「はい。つい、先頃……早坂の口から……」 おりつの顔にかげりがよぎった。同様に、松本も沈痛な顔をした。話というのはこの事だ ったらしい。 「実は、千代乃と手を切らせたのは……それがしでござる。」 「えっ?」 「それがしが、靖志郎の惚れた女を引き離したのだ。」 松本の話というのは、こうである。 その頃の靖志郎は、千代乃にのめり込んでいた。正式の妻にするのは無理としても、ゆ くゆくは女の年季が明けるのを待ち、どこかに住まわせるつもりだとまで漏らしていた。 しかしその打ち込み様は……はた目にも危ういものをはらんでいた。ある時、靖志郎の母 から頼まれ、もう知らぬ顔もできず、まず女のことを調べるうちに、千代乃には、たちの 悪い兄のいる事がわかった。妹を借金のかたに売り、行方をくらましたようなならず者だ が、いつまた舞い戻って、千代乃に食らいつくかもしれなかった。まして、靖志郎は藩の 公金を扱う身。どんな後難がふりかかるかもしれん、と、松本はぞっとした。靖志郎は仕 事上の才覚が抜きんでている。このままいけば、必ずや我々の先に立って、もっと上を望 めるはずの男だ。遊所の女などにかまけて、みすみす将来を棒に振るなどということは、 あまりに勿体ないと思った。靖志郎が病を得て伏せった時、松本はひそかに託された文も ことづけもすべて握り潰し、その上で、千代乃に話をつけに行った。 「……会ってみて、これはまずい、と確信を抱き申した。」 「なぜでございます。」 「女は、本気だったからでござる。」 「………。」 「女郎の手管ではなく、ただ一途に、靖志郎に惚れぬいていた。千代乃というのは、あん な所には似つかわしくない、おとなしい……しかしどこか、男を引きつけてやまぬ、暗い 美しさがあった。それでいて、思い込んだら後へひかぬような意地の強さがござった。そ れがしは言葉をつくして説得したが、靖志郎のことはあきらめぬ、と女はかえって必死に なった。それがしは切羽つまってついに、抱え主に掛け合い、そして、いや……」 松本は、これ以上はおりつに聞かせられぬ、という顔で黙った。 「かまいませぬ。……聞かせて下さいまし。」 「……千代乃は、靖志郎に会おうと……足抜きをはかったのでござる。」 「足抜き……?」 「遊里から逃げようとしたのだ。」 足抜き、とは遊女、女郎の脱走の事である。無論のこと、金で抱えられている女が無断で 逃げ出そうとすれば、捕まったが最後、手ひどい折檻を受ける。 「………。」 その一事で抱え主も見放したらしく、千代乃は間もなく鞍替えといって、よその町へ移 された。女の転売である。その後靖志郎は回復し、お役目に戻った。松本は正直、ほっと し、ちょうど役職が変わって国許へ赴任した。しかし靖志郎はひそかに女を探し続け、そ してようやく消息がわかった時には、千代乃はすでに死んでいた。 「それ以来、靖志郎は変わった。誰に対しても、……決して胸の内を見せようとせぬよう になった。それがしの裏切りを知り、憎んでいるのかもしれぬ。」 「裏切り……」 「左様。」 「………。」 「もしやそれがしのした事が、あいつに生涯癒えぬ傷を負わせたのかもしれぬ。それを思 うと……」 「松本様。それは、違います。」 おりつは顔を上げた。 「違う、とは。」 「もし早坂が、今もあなた様を憎んでいるとしたらこのようなものを託すでしょうか。」 「………。」 おりつには、松本の知らぬ五年間の靖志郎を見てきたという点がある。 「あの人は確かに……素直に心を表すことができない人でございます。でも、ただお役目 のためだけに書き残したとしたら……真っ直ぐ上役のかたへお届けすると思います。わざ わざ松本様にと名指しするようなはずはありませぬ。これは、恐らく友にあてた遺書のつ もりかと存じます。」 「遺書?」 松本が驚き、おりつは黙ってうなずいた。 「では、靖志郎は。」 「祖父、いえ医者は……この夏は越せまいと……」 いずれ人の口から耳に入るよりは、と、おりつは正直に言った。 「………。」 松本が、膝の上の手をぐっと握った。 「どうか、一度会ってやって下さいませ。……あの人は、きっと自分の口から会いに来て くれとは申しますまい。」 松本は、しばらく考え込んでいたが、 「必ず、見舞いにお伺いいたす。」 と言っておりつの顔を見た。松本は、この五年間心にわだかまっていたことを人に聞いて もらい幾分心が軽くなった、という謝辞を述べた。それはおりつも同様であった。 「それは、私も同じでございます。今さら、遅すぎるようですけれど……近頃やっと、夫 のことがおぼろげにわかってきたような気がするのでございます。松本様にお聞きして納 得がゆきました。」 松本は嘆息した。 「あなたは、お強い。」 「そうでございましょうか。」 男は、女の内面にまでは踏み込まず、しっかりしている事を「強い」の評価で済ませてし まう事がある。最も、おりつの心の動きや揺らぎの真のところは、夫にも理解出来ていな いのだ。 「このように立派な妻女がありながら、鬱々として楽しまず、子も成さず……靖志郎は馬 鹿者だ。もっと、人生を前向きに進むべきであった。」 「………。」 それは、長く離れている間に陰鬱な暮らしに落ちていた友への正直な憤慨の言葉であった が、同時におりつの胸を刺す言葉でもあった。夫との五年間を無為に過ごした事は、妻で あるおりつの力のなさにも責めを受けているような気がした。 「いや、失礼。病気ゆえ、己の生き方に投げやりになったとしても、いたしかたのないこ とかも知れぬ。しかし、惜しい。」 「いいえ……私はまだ、あきらめてはおりませぬ。」 おりつは、一度伏せた目を上げた。 「え?」 「早坂の命が、残りわずかと知って……何とか、少しでも人らしい心を取り戻させてやり たいと……できる限りのことをして送り出してやりたいと存じます。」 「何と……」 「遅きに失した、という気はいたしますけれど。」 「覚悟のできた方だ。あなたは……」 「自分に悔いの残らぬようにしたいだけかも知れませぬ。」 立派な心がけ、と誉められたほどの事ではなかった。靖志郎の心の傷も闇も、見ぬふりを して来た自分に出来る事はないのか。限られた日々と知り、人の口から過去の事情を知っ てしまえば、不思議とおりつの心には、夫に対する憤りは消えて、静かな覚悟のようなも のだけが生まれつつあった。 松本は感心したらしい。 「あなたは、まだお若い。及ばずながら、これからはそれがしも、お力になりたい。」 と、言ってしまってから軽く咳ばらいをした。 「いや、もちろん、変な意味ではなく……」 「はい。」 おりつは微笑した。 数日後、松本は言葉通り早坂家に見舞いに訪れた。靖志郎は病勢が進み、ほとんど寝た きりになっている。痩せて、肌が青白い。 「左馬之介か……」 靖志郎が体を起こそうとした。 「ああ、起きんでいい。」 「いや、この所大分、楽なのだ。」 「いいから、横になっていろ。」 「うむ……」 再び仰臥した。松本は傍らに先日の書付を包んで持参していた。これを読破する為に数日 の日数を必要としたのである。 「先日は、貴公直々の秘伝の書を頂戴し、かたじけない。」 「役に立ちそうか。」 「もちろんだ。」 「お役目は、順調か。」 松本は苦笑した。 「何しろ、早坂靖志郎の後を引き継ぐのだからな。結構気骨が折れる。おぬしと仲がよか ったからといって、頭の出来が同じわけではないぞ。」 靖志郎は淡々と答えている。 「おぬしなら、うまくやれるだろう。」 「そこで、だ。これを読んで、分からぬ所を聞きに来た。具合が良ければ、少し教えてく れぬか。」 「ああ……」 松本は風呂敷を解いて、矢立て、帳簿などを取り出した。病人の体調を気遣いながらの聞 き書きであったが、靖志郎はまるで今も藩邸内にいるかのように、よどみなく公務の端々 まで答えた。松本はいちいち真剣に聞き、或いは記録をとり、やがて茶を飲んで一服した。 「話は変わるが……」 と、ふと床の間の紅梅に目を移し、手あぶりの上に手をかざしながら、松本が話し掛けた。 「ん……?」 「おぬしの女房殿は、いい女だな。」 「そうか。」 照れるでもなく、抑揚の少ない声で靖志郎が答えた。 「うむ。あれなら俺がもらいたかった。うちのやつとは大違いだ。」 「三人目が出来たと聞いたぞ。」 「我が女房は、元気だけが取り柄だ。一人産む度に肥えていく。」 今度は、靖志郎がかすかに笑った。国許の松本の妻女には会った事がないが、そう言う松 本のほうも五年の間にすっかり顎や肩、腹のあたりに丸みをつけて戻って来たのである。 妻女の食の好みがうつった証拠であろう。子供らの年が近いのも、次々と健康な営みが繰 り返される家庭をあらわしているようでさえあった。おりつは、この家に嫁ぐ前には娘ら しい体つきをしていたが、今はその当座より痩せている。 少し、沈黙があった。 「りつには、すまぬと思っている。」 思い掛けぬ言葉に、松本は一度目を見開いたが、夫らしく一家を経営している手本のよう に、やや諭すような口調になって、答えた。 「そう思うなら、少しはやさしくしてやれ。」 「俺に、そんな事ができると思うか。」 「………。」 再び少しの間があって、今度は松本から口を開いた。 「もう一つ、おぬしに言いたいことがある。」 「何だ。」 「千代乃の件だ。今さらだが……すまなかった。」 そう言って、頭を下げた。 「何を謝る。」 「俺のお節介で、おぬしを傷つけた。それだけは、今もひっかかっている。」 靖志郎は遠い表情をして、それからまた淡々と首を横に振ってみせた。 「……いや。逆の立場だったら、俺は同じ事をした。」 「そうか……許してくれるか。」 「許すも許さぬも……」 と、靖志郎は一度言葉を切ってから、 「千代乃が、なぜ死んだか知っているか。」 「いや。」 国許での新生活が忙しく、思い立って江戸の旧知に文をやり、一通りの事を知らされただ けである。足抜けで楼主に睨まれた女郎の鞍替えであるから、移された先の条件が良いは ずもなく、恐らくは過労で死んだのだろうと思っていた。ああした場所にとって女は商品 でしかなく、昨日まで濃い衣装の服を着て客をとっていた女郎が、死ねば無縁仏として寺 の境内に投げ込まれる、という話はざらにある。 が、靖志郎の答えは簡潔であった。 「客と心中したのだ。」 「えっ……なんと。」 「表向きは病死だがな。」 「…………。」 「……あの女は所詮、誰か男にすがっていなければ、生きてゆけなかったのだろう。不思 議と、男を暗い淵に引きずりこむような所があった。あのままいけば俺がその相手になっ ていたのかもしれぬ。」 「………。」 確かに、という顔で松本は黙ってうなずいた。この怜悧な男が、一人の女郎になぜそれほ どのめりこみ危ない橋を渡ろうとするのか、これも若かった松本には理解が出来なかった 部分がある。 「だがそれを知った時……俺は……空しかった。あれほど俺一人だと誓った女が他の男と 死を選んだということに、ひどく裏切られた気がした。千代乃は、俺を待ってはいなかっ たのだと。もはや、誰も信じられぬと思った……」 「若かったのだ、おぬしも。」 「その時以来、何もかも、面倒になった。……心が動かなくなってしまった。」 「しかし、それでは……りつ殿が哀れではないか。」 「そうだ。俺は、頭ではわかっていながら……りつにも母にも、冷たくあたってきた。も ともと人としての情が薄いのだ。これでも多少は悩んだのだがな。」 「靖志郎。」 「しかし、もうすぐ終わる……。」 「………。」 「不思議だな。死ぬと思えば、いっそ気が楽なのだ。」 「死ぬなどと。そう思い込んでいては、治るものも治らぬぞ。」 「自分の体だ。わかっている。」 靖志郎は、気負うでもなく悲嘆するでもなく、淡々とそう言った。松本はそれ以上、強い て空言の激励をする気を失った。長い病に苦しんだのは靖志郎本人なのである。確かに、 自分の体に流れている命の終わりを悟るのは本人のみなのかもしれない。 「左馬之介、頼みがある。」 公務の時と同じような口調で、靖志郎が言葉を発したので、松本は我に返った。 「何だ。」 靖志郎は病臥の顔を松本へ真っ直ぐに向けて、こう言った。 「俺の死後、母が何と言おうと……りつを里へ帰してくれ。」 「……む。」 松本はかすかに唸った。当主の妻であれば、未亡人となっても婚家に留まる例はある。貞 女二夫に仕えず、という言葉は、町家では通用せずとも、武家の古い道徳の中にはまだ残 ってはいた。おりつのような慎ましい女は尚更である。 「早坂は乙弥が戻ってきて継ぐだろう。母には針のむしろかも知れぬが……りつには、関 わりのないことだ。この家にとどまらずにすむよう、見届けてくれ。」 「うむ。」 たっての頼み、という事なら引き受けざるを得まい。松本は松枝がどのような気性か、千 代乃の件で世話をした時に知っている。おりつが気に染まない嫁ではあっても、おとなし く自分を立てて従ってくれた事には違いない。それに反して、異母弟の乙弥はまったくの 敵視をしてきたといってもよい。妾が生んだ次男との確執、も、松本ならば知っている。 松枝が自分を守る為に、前当主夫人となるおりつをこの家に引き止め、乙弥との間で盾に するくらいの事は考えそうである。 靖志郎は起き上がり、手文庫の中から、一通の封書を取り出した。 「これを……」 きっちりと折り目をつけ、奉書の白も眩しい。 「もしや、遺言状か。」 「まあ、そうだ。」 松本は、わかった、と言い、複雑な表情で封書を懐にしまった。靖志郎はそれを見て安 堵したのか、嘆息まじりに細く息を吐きながら、また横になる。 「……疲れたか。」 「少し、眠い。」 「では、失礼しよう。」 「すまぬ。」 「いや……大事にしてくれ。また、来る。」 「ああ……」 松本は、静かに部屋を出た。障子が閉じられると、靖志郎はそのまま目を閉じて、深い眠 りに入っていった。 八へ続く |