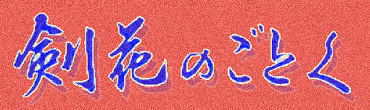 |
| 第 4 回 |
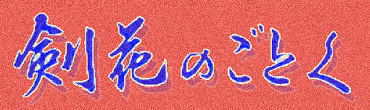 |
| 第 4 回 |
| 第 一 部 暁 闇 |
| (一) 歳三あらわる |
| 1 |
その男は今、江戸の闇の下にいる。 いや、正確にいえば灯りは薄くひとつともされてはいるのだが、あえてそこではなく、 屋内の闇に顔を向けて、目を凝らしていた。あと一刻のうちには暗闇の中での喧嘩が始ま るかもしれず、夜目を慣らしておく必要があったのである。 文久二年の春、気の早い市中の桜の花びらを容赦なくなぶるように散らす風の強い晩で、 しっかりと閉められた商家の表戸でさえ、がたがたと木の揺れあう音を立てている。 場所は、本所にある「大黒屋」という、大きな両替屋の店内である。少し冒頭の男から 目を転じていくと、一見して用心棒に雇われたとおぼしき浪人者が二人、行灯の近くに、 刀を抱いて座っている。昼間はそれなりに人の出入りで賑わう場所だが、今、この店の者 たちはひとり残らず、奥の住まいにそれぞれ引きこもって、息を潜めている。つまりがら んとした店の表には、浪人二人と、「その男」の三人だけが座っている、という図式にな る。 ここで少し、浪人二人の囁き声に近づいてみたい。 「……しかし、来るのかね。」 「今夜来ると、わざわざ予告していったというんだから、来るんだろうよ。」 「押し借り、といったって、要はゆすりだろう。そんな、理不尽な者どもは、役人にでも 任せときゃいいんだ。」 苦笑が混じった。それが出来れば彼らはここにいる必要がない。 「ふっ、……幕府の役人が、まだ起こってもいない事件になど、手が回る訳がないさ。先 月は老中安藤様が坂下門外で斬られ、今月は、遂に将軍家茂公と和宮様とのご婚儀が執り 行なわれるって、忙しいご時世だぜ。」 「公武一和(公武合体)に反対する、過激な連中が、続々と江戸に流れ込んでいるらしいな。」 「江戸だけじゃない。京、大坂、横浜……どこも『攘夷、攘夷』の大音声だ。浮浪の徒が、 天誅と称していたずらに暗殺騒ぎを起こしている。実にけしからんよ。」 「浮浪の徒……と言われると、ちょっと痛いな。」 「何を言ってるんだ。我々は、そんな浮薄な連中とは違う。剣の腕ひとつで、お国のため に、力を尽くそうと志したんじゃないか。」 「こんな、商家の用心棒が、国のためか?」 「罪の無い町民を守るのは、我ら武士の本分だ。」 という話を聞くと、今夜この店に予告つきの「押し借り」が現れることになっているら しい。 「押し借り」とは奇妙な言葉だが、この当時の流行語のひとつ、といってもいい。裕福な 商家とみれば、「国事奔走のため」「攘夷御用のため」などというもったいぶった、その くせ実態のわかりようのない軍資金を、「貸せ」といって無理やりにふんだくっていく侍 (浪士、志士)どもの総称である。借りたというのは名目だけのことであるから、当然、返 ってくるあてなどは皆無で、刀の柄を叩いて営利の妨害をされるのが嫌さに泣く泣く金を 渡す、というのが商人側の事情だから、まあ、たちの悪い居直り強盗に出会ったと思うし かない。 その「押し借り」来襲への用心棒として置かれた浪人二人は、待つ恐怖を紛らわすため に、おしゃべりを続けているのが本当のところ。 さて一方の男である。こちらがこの話の主眼となる人間であるから、少し詳しい描写が 必要であろう。 まず、息に乱れがない。目を薄く開けていなければ、眠っているかと思うほど静かであ る。髪は総髪を束ねて綺麗に後ろに結い上げ、端整な顔立ちはやさ男ふうなのだが、目の 奥が鋭い。着物は、尻をはしょって紺の股引きを履き、どうみてもそこらの町人風である。 傍らに大刀を一本。同じく木刀を一本、仲良く壁に立てかけて並べてある。 浪人たちも、今日になってから仲間に加わって、無言でそこに座ったこの男が、妙に気 になるらしい。 「何者だい……あいつは。」 「別口で、雇われた奴らしいぜ。」 「町人じゃないか。刀は……使えるのかね。」 「さあ……何でも、本業は、薬売りらしいぜ。今日、来るはずだった何とかいう剣客の替 わりで、急遽助っ人を頼んだとか。」 「そいつ、逃げ出したというわけか。その替わりがあんなので大丈夫なのかね。」 浪人たちは、冷ややかな目で男を見ている。 「おい、薬屋。」 呼ばれた男は、じろりと視線をよこした。 「その木刀は何のつもりだ。」 男は、顔立ちのわりには低い声で、少し間を置いてから、 「………。あちら様の出方次第さ。ぶん殴ってすむ程度なら、これでいく。」 「それで済まぬ時は。」 「抜いてくりゃ、斬るだけさ。」 ここは即答した。 「斬る……?」 浪人たちは、ククク……と失笑している。 「おまえさん、そのなりで、真剣など使えるのかね。」 「なりで斬るわけでもなかろう。」 「剣は、何流を使う。」 男は、またひと呼吸置いて、ややゆっくりと響くように答えた。 「天然理心流。」 しかし相手の答えは拍子抜けしたようで、 「知らんなあ。……お前、聞いたことあるか?」 「さあ、知らん。」 顔を見合う二人が、次第に馬鹿にした物言いになってきている。 「どうせ、どこぞの田舎剣法だろう。道場はどこにある。」 「宗家は、牛込柳町試衛館、当代師範は、近藤勇。」 「近藤……ああ、ひょっとして……多摩の方に広がっている流儀じゃねえか。」 「そうだ。」 「百姓剣術か……よせよせ、生兵法は怪我のもとだぞ。押し借りと言っても、強盗と同じだ。 町人が下手に手向かいして、命を無駄にするな。」 「……生兵法かどうか。」 男は、微かに息をもらして、皮肉な笑いを浮かべた。 「今にわかるさ。」 その声に不遜なものが混じっている。 「何……。生意気な奴だ。」 「薬屋。名は何と言う。」 「土方歳三。」 当然のように答えた。 この男が歳三。土方歳三である。 「ひじかた……?」 浪人たちは、堂々と姓を名乗る歳三に、ちょっと訝しげな顔をした。士農工商の身分が だいぶん崩れてきた当世とはいっても、あまりおおっぴらに許されることではない。 「ふん、武士の真似ごとも大概にせぬと、痛い目にあうぞ。」 「そうだ。真っ先に斬られて転がってから泣いても間に合わんぜ。」 「………。」 歳三は、憎々しげに黙っている。 「ふん、怖じ気づいたか。」 「おしゃべりはその辺にして……」 歳三の視線だけは、さっきから油断無く店の入口の方に注いでいる。 「そろそろ、お出ましだぜ。」 「何っ。」 浪人たち、刀を引き寄せ戸口の方に耳を澄ますが、外はしんとして物音がない。 少しの間。 「(小声で)……何も来ないじゃないか。」 「しっ!」 尚も息をひそめていると、 ――- ドン、ドン、 と表戸を叩く音がする。浪人の片方が、「ひっ……」と息を飲んだ。 |
| 2 |
| 歳三は、刀を引き寄せ奥を振り返った。打ち合わせでは、この店の手代が、初めに来訪者 への応対をすることになっている。だが手代は、やっとのことで帳場までは出てきたものの、 がたがた震えながら柱につかまっている。歳三は手でしっしっと示しながら小さい声で、いいよ、 奥に逃げてな。と囁いた。手代が膝を曲げながらひっこんでしまってから、歳三は土間に降り、 くぐり戸の側まで行き、さきほどとはうって変わった、ごく柔らかな声色を使った。 「どちらさまでございましょう。」 太い声だけが返って来る。 「先日、約束した者だ。あるじはおるか。」 「お約束、とは。」 「とぼけるな。……攘夷の為の軍資金だ。先日は主人が他行中とのことだったが今度はそうは いかんぞ。わざわざ今晩と言い置いてきたのだからな。」 「それは、ご苦労さまでございます。」 「早く、開けろ。」 と、横槍を入れてきたらしいほうの声は、やや高い。 (二人……。) 歳三は、応答の合間に、相手の人数をはかっている。 「どうした。」 「それが……困りました。お金はご用立てできないのでございます。」 「何っ!」 「どういうわけだ。」 「ただ攘夷の為と申されましても……何にお使いになるのでございましょうか。」 「国事奔走の為の資金と申したではないか。」 「それだけでは、わかりかねます。」 「うるさい。早く開けぬか。」 (三人……) 仲間が苛立って口を添えるごとに、歳三は心の中で慎重に指を折っている。 「いえ、当家では代々、使い道の分からぬ勘定は、びた一文とて出してはならぬという、厳し い決まりでございまして。」 「ごちゃごちゃ抜かすな。」 「くそっ、早くせぬと戸を打ち破るぞ。」 (四……。五人、か。) これで、歳三の頭の中の薬指と小指が折れた。 「それは、困ります。」 「開けんか!」 賊徒たちは、口々に「開けろ」と、せわしなく戸を叩き続ける。 (五人。まず間違いねえ。) この間、歳三は無言。近所にももはや、押しかけ浪士どもの襲来は聞こえているだろう。 もっとも、誰も、役人に通報になどいくはずがない。とばっちりがこわいのは、商家ならど こも同じことだからである。 中の声が静まったことに、賊徒たちは業をにやして、中のひとりが脅すような口調で、や や声に押し殺すような力をこめてきた。 「……店に火を掛けられてもよいのか。」 歳三が答える。 「ほほう。火を掛けると申されますか。」 「嫌なら、開けろ。」 腹が決まった。歳三、今度はやや低く、 「……開けてもよろしゅうございますか。」 「おう。」 外では、鯉口を切る音が重なっている。 「………。」 歳三、店内を振り返り、用心棒二人に目で合図を送る。しかし、この二人役に立つのだろ うか。実は信頼していない。相手の一人か二人、受け持ってくれれば御の字だと思っている。 (まあ、やるしかねえな。) 歳三、大刀は腰に差し、木刀を片手に閂を開ける。自分の体は相手に見せぬようにし、 戸口をそろりと開いた。まず、抜き身の切っ先がぬっとその隙間から、そして一人が、不用意 にも頭から、狭い戸口をくぐろうとした。 (馬鹿め。) 歳三が、思い切り木刀を降り下ろす。 「ぎゃっ!」 賊徒は後頭部を殴られ、そのまま土間に昏倒する。残る数人にどよめきが起こり、次々と 抜刀して飛び込んで来る。 が、そこにはすでに歳三はいない。いきなり、かたわらに用意しておいた手桶の中身を、 三人の賊に浴びせ掛けた。たっぷりと、唐辛子をすり入れた水が入っている。 「うわっ」 なんだこれは、という意味の、声にならぬ悲鳴が起きた。顔に真っ赤な液体を浴びた者が、 目を押さえる。 (特製の辛子汁さ。) 歳三は声を出さない。 それでも免れた者はいきり立って、 「おのれ、逆らう気か!!」 運悪く、明りの届く範囲にさっきの用心棒浪人たちがいた。それに向かって殺到する。 「う、うわーっ」 と、情けない声を出してあとずさっているのは用心棒の一人らしい。 歳三はそっちの斬り合いには構わず、暗がりの中をだっと帳場の方に駆け上がっている。 その影の動きに気づいたらしい浪士が、 「おい、こっちにもいる!」 「ぬ!」 こちらを振り返った。 歳三はそこで初めて両足を踏まえて正面に立ち、明らかに用意しておいたような科白を、 高々と吼えている。 「おう、食い詰め侍ども。火つけ、盗賊は天下の大罪と決まっていらあ。当節、馬鹿の一 つ覚えで攘夷だ攘夷だと御託を並べりゃ金を巻き上げられると思ったら、大間違いだ。 怪我しねえうちに、とっとと尻尾巻いて田舎へ帰りやがれ!」 敵も、一瞬あぜんとしたらしい。はっと我にかえって、 「小癪な!」 激昂した賊徒、歳三に斬りかかって来る。この時を待っていたのだ。歳三は、相手が 振りおろす刀を跳ね上げ、そのまま返して、相手の肩口から袈裟がけに斬る。 「ぎゃあっ……」 初めて血しぶきがあがった。 歳三はちっ、と舌打ちをした。存分に振り下ろすほど足場が定まらず、致命傷にはなって いない。 もう一人、背後に回ろうとした賊徒が、勢い良く転倒し、はずみでそばの障子を突き破 った。奥へ通じる板の間、廊下には、歳三の指示で油がまんべんなく塗ってある。 歳三はにっと笑って、 「お客さん。そっから先ゃ、行き止まりだよ。」 言いざま、すかさず男の太腿目がけ刀を突き刺す。絶叫。 「う……」 残る賊の一人が、泡を食って戸口からほうほうの体で逃げ出したらしい。表に見張りでも いたかどうかは、わからない。追加の人数が入ってこなかったのは、この夜の場合幸運だっ たといえるだろう。 歳三は今太腿を刺した男の襟がみをひっつかみ、ごん、と頭を床に打ち付け、気絶させた。 とにかく、反撃させてはこっちの身が持たない。 「ふう……」 ようやくしん、となった店内に新しい明かりをつけてから振り返ると、こちら用心棒側の 一人は階段で転げてひっくり返っているし、一人は、相手の初太刀をよけ損じて、やはりど こか打ったらしい。斬られずに生きているのが不思議、という顔で放心している。 「生兵法は、怪我のもとだそうだな。」 歳三、にやりと笑う。 「………。」 さすがに返す言葉がない。 歳三は用意していた縄の束を三つ持ってきて、 「縛るのを手伝えるか。」 「ああ……。」 男たちは、やっとのことで動き始めた。 朝になった。奉行所の役人たちが店に呼ばれて、賊徒三人を引っ立てて行く。同心に事情を 尋ねられているのは、あの用心棒たちである。 「さよう。話し合いで済ませるつもりだったが、一味の者が確かに、店に火を放つと申した。 しかも抜刀して乱入してまいったので、やむを得ず、応戦したのでござる。」 「なるほど……それは、ちとタチが悪うござるな。」 同心は、最近この手の「軍資金押し借り」「攘夷盗」なるものの頻発にはうんざりして いる。あくまで「金を貸せ」という建て前で商家に強要するもので、公の事件としては扱 いにくいのだ。 やがて同心が行ってしまうと、用心棒二人は所在なさげにその場に残された。 「あいつは、どうしたんだ?」 聞かれたほうは苦い顔をして、 「面倒はごめんだ、と言って、金だけもらってさっさと消えやがった。」 「くそっ。」 「しかもこんなものまで、買わされた。」 「え?……何だこりゃ。」 懐から出した薬袋の表に、「石田散薬」と書いてある。 「……打ち身の薬だとさ。」 二人は、いまいましげに顔を見合わせている。 いっぽう、店の中では奉公人たちが、後片付けに精をだしている。女中たちが、せっせ と拭き掃除をしながら、 「ほんとにねえ……油だの、唐辛子だのを山ほど用意しろって言われた時は、どうなる事 やらって、思ったけどさ……」 「顔だけじゃなくて、頭もいいよ、あの男……」 女中たちは、おかしくてこらえきれない様子で、くすくす笑っている。 |
| 3 |
その頃、歳三は小ざっぱりした着流し姿に着替え、遅い朝を迎えた遊郭を歩いている。 遊郭といっても岡場所(私娼窟)で、吉原のような格式ばった店の並びではない。一見、普 通の宿屋のようにも見えながら、どこか脂粉の匂いが漂ってくるような、そのうちのひと つの女郎屋に上がった。 帳場でやりとりをすませたあと、安物の障子にきつい色の花柄の切りぬきが、破れ隠し に貼られていて、それも模様のひとつ、にしてしまっているらしい二階の部屋に入った。 ここには、他流北辰一刀流の剣客で、今は歳三の通う試衛館道場に居候している、藤堂 平助という若い江戸浪人がいる。その藤堂の傍らには、布団をはねのけたまま、女郎が襦 袢一枚でぐっすりと寝ている。 藤堂は、女の腰にまわしていた手をのけて、むくりと起き上がると、待ちかねた声とい う声で言った。 「いやあ、土方さん。どうでした、首尾は。」 歳三は平気な顔で、畳の上に脱ぎ散らした女の湯文字や腰紐などをちょい、とどけて座る と、 「五人来たよ。」 「五人。そいつはちょいと、骨が折れるな。」 藤堂は目を見開いて、歳三が傷ひとつない無事でいることが、かえって不思議そうな 表情になった。歳三はうなずいて、 「しょうがねえから、なりふり構わずさ。ま、三人はとっ捕まえたから、上出来だろう。」 「そりゃあ、すごい。……で?」 藤堂は、ひとさし指と親指で丸を作っている。本来、そっちの話のほうが気がかりだった らしい。 「ここの勘定は済ませて来た。……別に、紹介賃。」 歳三は、小判を一枚、気前良く渡している。藤堂は拝むようにして受け取り、 「ありがてえ。だが、いいんですかね。」 「何、多少色をつけてくれたからな。」 「あのケチな大黒屋がねえ。」 実は、昨夜の用心棒の仕事は、この藤堂が同門の仲間から聞き入れて請け負ってきた 内職だったのである。ところが、ついここの馴染みの女郎と数日流連(居続け)して遊ぶう ちに、持っていたわずかな小遣いはあっという間に底をつき、「今夜ひとばん、稼いでく れば きっと払えるから」と店に頼みこんだものの頭から信じてもらえず、勘定を踏み倒さ れる恐れがある、と足止めをされていたのである。そこで仕方なしに歳三を呼んで、内緒 の代理人を頼んだ、という顛末だった。ところが、この得体の知れない代理人のおかげで 賊の捕り物は済み、金品も店の者も無事だった、ということで、依頼主が約束より少し報 酬をはずんでくれた、ということになる。もっとも、これで関わりあいはご免こうむりま すよ、という商人らしい計算もあるだろう。このことに恩を着せて何度も押しかけてこら れてはたまらない。大体、堅気の商家から見て浪人者などは十把ひとからげでそういうふ うに思われている。 歳三は報酬のことをふん、と鼻で笑って、 「百両二百両とゆすり取られる事を思えば安いもんさ。」 「へへ、これで足留めともおさらばだ。こんなちんくしゃと寝ちゃいられねえ。」 藤堂は小判を口にくわえ、喜々として身支度をし始めている。女郎が、寝床の中から眠 そうな声で、 「なんだい……帰るのかい、平さん。」 「おう。もっといい所で、ゲン直しさ。」 歳三が苦笑した。 「たいがいにしとけよ。」 女はやっと目をあけて、 「何さ……あら、こちらちょいと、いい男。」 むっくりと起き上がり、歳三を見て、はげて色の薄くなった紅の口元をにっと横に開いた。 そのはだけた胸元のあたりに、前夜ま での遊びのあとが忍ばれる。女は若い藤堂など眼中に なくなった様子で、 「ねーえ、旦那。こんなスカンピンはほっといてさ。……あたしと、どう?」 と、歳三に流し目を送った。 「ちぇっ。いい加減にしやがれ。」 藤堂が、女のおでこを手でつん、と押すと、女はそのまま布団の上にたわいなく転がっ てしまう。まだ眠くてかったるいのだ。つっぷしたまま何がおかしいのかくっくっと笑っ ている。安女郎だが、藤堂とは客というより気のあう友達みたいなところがあるらしい。 歳三は先客に気をつかったふりで、わざとそっけなく、 「あいにく、人の敵娼(あいかた)に手を出すほど困っちゃいねえよ。」 と、言った。確かに、同じ道場の仲間とこんなところで「兄弟」になってもつまらない。 「そうそう。さあ、行きましょう行きましょう。」 藤堂が歳三の背を押すようにして、女郎部屋をそそくさと出た。 |
| 4 |
| その日の八つもとうに過ぎた、という午後の時刻である。 牛込柳町・天然理心流道場、試衛館。雑多な流儀の剣客たちが、現在の道場主・近藤勇 の人物に魅かれて、そのまま居着いてしまっているという不思議な道場である。中では、 今日も近藤たちの激しい稽古が続いている。その顔ぶれは同門の井上源三郎、他流からは 山南敬助、永倉新八、原田左之助、比較的新参者で、ごくたまに顔を見せる斎藤一。 そして今、若くして筆頭師範代の 天然理心流・沖田宗次郎(のちの総司)が、歳三の寝て いる部屋の前に一人でやってきた。 「土方さん。入りますよ。」 中からの返答はない。 沖田は、からりと障子を開けて入った。歳三が、身動きもせず寝ている。 「………。」 沖田はツ、と布団の横にしゃがみ、やおら、その中に手を差し入れた。 「お、は、よ、う、ござい、ます。」 脇の下をくすぐった。がばっと、布団の主が起き上がった。 「何すんだ、おめえは。」 「たまには、笑わないと体によくないと思ってさあ。」 「ガキみてえな真似するんじゃねえよ。」 この青年は、まるで歳三をからかうために後から生まれてきたのではないか、と思える ことがあるほど、たいがいこの調子であって、 「朝帰りして今頃までぐうぐう寝てるのが、大人ってもんですかね。」 「馬鹿。」 沖田はちょっと口をとがらせて、 「御飯を持ってきてあげたのになあ。朝飯、いや昼飯……このままほっといたら、晩飯に なってしまうかな。」 「……そういや、腹が減った。」 ふと見ると、盆の上に、握り飯、味噌汁、漬物、お茶と、質素だがひと揃えの飯のした くが乗っかっている。 「気がきくでしょう?」 「すまん。」 歳三は、ほとんど顎だけをひいて会釈をした。 「実は、近藤先生にね、持っていけって言われたんです。」 「なんだ。」 「ご新造に叱られますからね、まったくここの人達は、いついるんだかいないんだか、お 膳の支度の都合がつきやしないって。」 「………。」 この道場の中で、唯一近藤勇だけは妻帯している。あとは歳三以下、皆独身。お互いに あまり干渉はしないようにしているが、それでも居候は皆、内儀のおつねには頭があがら ない。 「で、食いっぱぐれるとかわいそうだから、わざわざとっておいてさしあげたんですよ。」 「わかったよ。」 歳三は、むすっとして大根の味噌汁を飲んでいる。せっかく温めてきてくれたらしいが、 やはり味噌汁だけは温めなおしではなく、煮えばなでさっと火からおろしたような作りたて が旨い。だいいち、大根は味噌汁の具ではなくて、金でおろして醤油をたらし、ツンと鼻に 辛さがたちのぼってくるほうが好きなのである。とは、沖田の手前言えず、黙っている。 「何か、ずいぶんお疲れのようでしたけど……」 「寝てねえからな。」 「藤堂さんに呼び出されて、また夜遊びですか。女郎屋から使いが来たって聞きましたけ ど。」 「平助は、帰ってきたのか。」 「いいえ。もう四日めですけどね。好きだなあ。」 「………。」 歳三は、あきれている。女郎屋の金が払えなくなって足留めされ、歳三にこっそり用心 棒の内職を肩代わりさせたくせに、金が入るとまたどこかへ遊びに行ったらしい。 沖田のほうは、年頃も変わらない藤堂の女遊びの話にはさほど興味がないようで、違う 話題を切り出している。飯の給仕よりも、この兄貴分と無駄話がしたくて来ているという 顔をしていた。 「しかし、夜の一人歩きは物騒ですよ。ゆうべも、本所の両替屋で人斬り騒ぎがあったら しい。さっき担ぎ売りの六さんが来て話していったんですがね。」 「ふうん。」 歳三、とぼけている。 「また、例の攘夷党の押し借りだそうです。たちの悪いやつらで、数人で刀を抜いて押し 込んできたらしい。こうなると、まるっきり強盗ですね。」 江戸者の噂話の速さというのは、ちょっと驚くほどである。ちなみにこの沖田は奥羽白 河浪人、ということにはなっているが、生まれ育ちはほとんど江戸っ子侍というのに近く 男にしては口数が多い。毎日、歳三の五倍や十倍の数の言葉を扱っているのではないか。 「くわしいな。……それで、大黒屋の方はどうなったんだ。」 と、歳三が合わせて聞き返すと、沖田はどこか楽しげな口ぶりで、 「ところが、両替屋も用心棒を何人か雇ってましてね。三人まで叩きのめして、役人に引 き渡したそうです。迎え打つ方に一人、滅法強いのがいて、いろいろと下知したというこ とですが、これが、事が済んだらふいと消えてしまって、ちょっとした評判らしい。何で てい も町人体で、役者のようないい男だったとか。」 「ふうん……」 「店の者は、危害を恐れて全員奥に隠れていたという話ですから、斬り合いの修羅場は見 ていなかったそうですが、ひょっとしてその男ひとりが、三人ともやっつけたんじゃない かと。それで名も告げず去ったとなると、ちょっと英雄気取りですね。きっと、腕は立つ がキザでいけ好かない奴かも知れませんよ。」 沖田はキザ、というあたりに少し力をこめた。歳三はつとめて何気なく、 「む……そりゃ、後で騒がれる面倒を嫌ったんだろうよ。そういう奴もいるさ。」 「そんな、奥ゆかしい人ですかねえ。」 沖田は、ふいにくすくす笑い出した。いたずらっぽく目を向けて、 「土方さん。」 「なんだ。」 「わたしは両替屋とは言いましたけど、『大黒屋』とまでは言ってませんよ。」 「………。」 歳三、しまった、という顔をする。 「ほうら、黙った。」 沖田は、手を打って喜んでいる。ひとしきり笑ったあとで、 「危ない内職だなあ。いくら土方さんでも真剣で斬られたら、石田散薬だけじゃ無理って もんですよ。」 「……血止め位、持って行ったさ。」 歳三は観念して、顔をしかめつつそう言った。 「ふふ。」 「他の皆には、内緒だぜ。もちろん、近藤さんにも。」 「わかっていますよ。」 「宗次郎。」 「はい。」 歳三、枕の下から財布を出し、小粒金を沖田に渡す。沖田はすっとぼけて、 「おや?」 「握り飯の、駄賃だ。」 「ずいぶん高い飯代だ。」 それでもちゃっかりと拝んで金を受け取り、歳三の飯が終わると同時に、 「毎度、ありがとうございます。お客様、こちらはおさげしてもよろしゅうございますか。」 「ああ。頼む。」 歳三は、ぶすっとした顔をしている。一分もやったのだから、片付けまでさせてもお釣り が来るだろう。沖田はちゃっちゃっ、と器を重ねて盆に乗せると、 「何か、足りませんよ。歳三さん。」 歳三はますますむっとした顔で、 「ご馳走さま。」 と、ふてくされた声で挨拶をした。 「結構です。」 沖田はここの内弟子だけに、ちょっとした躾にはうるさい。笑いながら行ってしまった。 数日後。歳三は、薬売りの格好になって、道場主の近藤勇の居室に挨拶に行った。近藤 はいかつい体のわりには、文筆のほうにもわりとまじめな男で、稽古のあとは、史書など 読んで勉強していたらしい。 「おお、家業の石田散薬の行商に早がわりか。また行くのか。」 「ああ。日野からまた、順番にね。姉に頼まれている薬もあるんで、ちょいと、問屋で仕 入れをしてからその足で。」 姉、というのは前の章にも書いたが、日野宿名主の妻になっているおのぶのことである。 「おのぶさんか。佐藤家へ行ったら、皆さんによろしく伝えてくれ。」 「もちろん。」 「仕入れの金は、あるのか。」 「ああ。それは、ご心配なく。」 「気をつけて行けよ。まあ、お前なら大丈夫か。」 近藤はにこっと笑った。 歳三は一礼して部屋を出ている。先日の騒ぎを、近藤は知らないはずだった。 (二)おりつ へ続く |