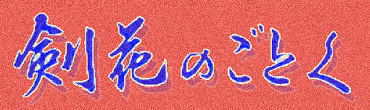 |
| 第 5 回 |
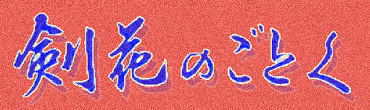 |
| 第 5 回 |
| 第 一 部 暁 闇 |
| (二) お り つ |
| 1 |
歳三が試衛館を出たあと、いくつか寄り道をして、音羽町のこじんまりとした薬種問屋、 松代屋に入る時には、いくらか日が落ちかけていた。ここは、人の紹介で何年か出入りして いる店だが、歳三の接客担当は手代の直次郎という男に定まっている。 歳三の売り物は、石田村の生家で作っている「石田散薬」という飲み薬で、近在の河原で とれる牛革草という植物を干して散薬にし、酒とともに飲むと打ち身に効く、という品であ ったが、その一種だけでそうそう、立ち回り先に需要があるとは限らない。時には、「風邪 薬を」「腹いたの薬はないか」などと頼まれることもあり、江戸にいる間に数種揃えておく ことがある。江戸で評判の薬、というだけで、田舎では有難いような気がするらしい。 暖簾をくぐると、ちょうど直次郎ひとりが帳場に座っていて、親しげな声をかけた。 「おや、歳さんじゃありませんか。お珍しい。」 「ちょっと入り用が出来てね。」 「どうぞ。ええと、取り合わせはいつものでようございますか。」 「うむ。それと、滋養丸を少しもらおうかな。」 「へい。これ、松どん、おりきに言って、お茶をね。」 と、直次郎はそばにいる小僧に声をかけておき、慣れた様子で歳三のために売薬を用意しは じめた。パチパチ、と算盤を弾いているときに女中が茶を運んでくると、 「ああご苦労さん、もう奥へ行っていいよ。松どんも、ちょっと早いがおまんまにしてもら いな。」 もののしゃべりかたが柔らかい男である。と、いうより見た目もすんなりして、男としては やや、頼りない。女子供からすると、あまりこわくない上役なのだろう。女中と小僧は、返 事をしてさっさと晩飯のために奥にひっこんでいった。小僧から見ても、歳三のような、ご くたまに来るだけの小口の客は、直次郎が好んで相手をしているのだからつきあうこともな い、とタカをくくっているかもしれない。その通りで、直次郎は店が仕舞ってから歳三と夜 の町へ遊びに出るのを楽しみにしていた頃がある。勘定はほとんど向こうが持つのだが、自 分がなよっとしているせいか、歳三のような骨っぽいのと遊ぶのが嬉しいらしい。 「もう、仕舞う所だったんじゃねえのかい。」 がらんとなった店さきで茶をすすりながら、歳三が聞いた。 「何、いいんですよ。丁度今日は暇でござんしてね。主人の親戚で祝言がございまして、揃 って他行中なもので、あたしはお留守居というわけで。」 「鬼の居ぬ間、というやつか。」 直次郎は、人聞きの悪い、とくすっと笑ったが、 「ま、泊まりがけで行ってくれましたんでね、ちっとはのんびりしたのは確かですがね。」 そとで 「しかし、外出はできんな。」 「そうなんですよ、女子供がおりますんで。近頃は何かと物騒ですからな。」 と、歳三との夜遊びに行けないのが残念な顔をした。歳三はにやっとして、 「頼りねえ用心棒だな。」 「それは、とても歳さんのようにゃ行きませんがね。いないよりましって位なもので。」 そういえば、飲み屋で直次郎がからまれた時に、歳三が相手を叩きのめしたことがあった。 ひょっとして歳三は用心棒がわりの役にたつから、おごられているのかもしれない。 「まあ、おっつけ若いのも戻ってきましょうから。それにあたしはもともと、金と力は無い ほうの人間なんでございますよ。」 色男、というのである。 「なるほど、旦那がいねえとよく舌が回る。」 直次郎は声をひそめて、 「あたしはね、親が奉公先を間違ったと思う事がございます。何しろ薬問屋なんて、鹿爪ら しくて地味な商売でございましょ?あたしとしてはもっとこう、艶っぽい……そうだねえ、 湯屋とか、着物屋とか、いっそのこと、ナカのギュウ太郎でもいい位。」 ナカ、というのは吉原遊郭、ギュウ太郎、というのはそこで働く男衆の一種のことである。 「親の見立ては当たってるよ。」 「どうして。」 「あんたをそんな女っ気の多い稼業につけたら、とても間違いの一つや二つじゃ済むまい、っ てことさ。」 「違いない。今の女房だってそもそもひょんな間違いで貰っちまったようなもので。」 「いい女らしいじゃないか。」 「へっ、あんなのは、どうでもいい女、いない方がいい女っていうんですよう。あーあ、あた しもこんな色気のない勤めなんぞやめて、歳さんと一緒に薬売りにでも歩こうかしらね。」 「おい、石田散薬は打ち身の薬だぜ。女客なんざ縁がねえよ。」 「ですから、お前さんが剣術の稽古をしていなさる間に、あたしは血の道の薬を売って歩いて ね、そのうち、どこぞの後家さんなんかに見そめられてしっぽりと……」 「馬鹿言ってやがる。」 「冗談に決まってますよ。あたしは臆病者でね、そう簡単に今の暮らしを変えられるものじゃ ございません。まあ、番頭に上がるまで辛抱、辛抱。おや、お茶が冷めちまったかな。」 その時、店の表に一人の若い女がたたずみ、中をうかがっている。遠慮がちに暖簾を少し越 すと、「あの、もし」という声をかけた。 「おや、まあ。早坂のご新造様ではございませんか。」 直次郎ははっ、と立ち上がった。 「申し訳ございませぬ、まだ、よろしゅうございますか。」 「ええ、ええ、どうぞ。お入りになって下さいまし。」 直次郎が、女を迎え入れる。武家の若女房らしい。歳三を見て軽く会釈をした。 歳三はほとんど目だけで礼を返したが、薄暗い土間に立った女の姿に、わずかに息を飲んだ。 美しい。 と、いっても道で振り返るほど派手な美人、というのではない。 ごく慎ましい淡い灰紅色の小紋に、小桜の型染めがほどこしてある。衣装も髪も、その美貌 を押し包んでいるかのように控えめではあるが、中背の細身に似つかわしく、さりげない品が ある。武家としても、藩士であればまず中程度かそれ以上、というところの内儀と思われた。 「お客様のところを、申し訳ございませぬが……」 「いえ、こちら様のご用は済んでおりまして、ちょいと今、お茶を頂いていたところですので。 今日はいかがなさいました。」 「主人のいつも頂いているお薬はございましょうか。」 「はい、はい。しかし、ご新造様みずからお越しとは……」 「先ほど、主人が少し具合が悪くなりまして、残りのお薬を使ってしまいましたの。」 「それはいけませんな。で、ご容体の方は?」 「お陰様で、今は落ち着きまして。それでも、お薬が切れては心細うございますから。」 「さようでございましょう。すぐに、お出し致しますのでお待ち下さいまし。」 直次郎が奥へ薬を取りに行っている間、女は黙って店の土間に立っている。歳三とそれ以降 視線を合わせようとしないのは、武家らしいたしなみであろう。薬は言葉通りすぐにみつかっ たらしく、歳三が女を観察する時間は案外短かった。 「お待たせをいたしました。いえ、また近いうちに甚七さんでもお見えになるかと思いまして ね、奥へご用意しておきましたので。」 と、いうのは奉公人の名だろう。確かに、商家への走り使いなどはどこでも奉公人がする。 「今日は、あいにくと外へ出しておりましたので……助かりました。有り難う存じます。あの、 代金の方は……」 「いえ、順徳先生から頂戴しておりますので、結構でございますよ。」 「さようでございますか。お世話をかけました。」 女は丁寧に辞儀をして、店を出ようとした。直次郎は再び腰を浮かせた。 「あの、お一人でお帰りになられますので?」 「はい。」 「それはいけない。もう暗うございますよ。」 「大丈夫でございます。」 「夜道は物騒でございます。今、松吉に言って駕籠を呼びにやりますから。」 「いえ、駕籠を待つより、歩いた方が早うございますから。」 「弱りましたなあ、うちもあいにく、男衆が出払ってしまって……そうだ。」 と、ここで直次郎は初めて思い出したように、 「歳三さん。申し訳ないが……」 と言って、先客のほうへ振り返った。 「いいよ。」 歳三は何気なくうなずいた。そのふたことで言葉は通じる。直次郎は喜んで、 「ありがたい。おりつ様、こちら様が送っていって下さるそうで。」 「え?」 女も、あらためて歳三を振り返った。 「住まいは、どちらだね。」 「駒塚橋のお近くでございます。ね。」 と、相槌を求める直次郎に、女は、 「直次郎さん。……せっかくでございますが、結構でございます。」 「え?奥様、なぜでございますか。」 「お気持ちはありがたく存じますが、見ず知らずのお方にご迷惑をお掛けするわけには 参りませぬ。」 「いえ、こちらは手前どものお得意様で、牛込柳町にお住まいの、剣術の先生でござい ますよ。」 「剣術の……?」 先生というのは多少の誇張も入っているが、女は、ちょっと訝しい顔をした。歳三は そのことにカチンときている。初めて直次郎にではなく、女に直接ものを言った。 「もっとも、そちら様のような歴とした武家じゃないがね。」 「歳三さん。」 直次郎が困った顔をする。 「直次郎さん。俺みたいなうさん臭い男の連れは御免こうむるとさ、こっちも別に下心の ある訳じゃねえ。お一人でお帰り願ったがいい。」 「ちょ、ちょっと歳さん。」 「そのようなつもりで申したのではございませぬが、ご気分を害されたのであれば謝りま す。申し訳ござりませぬ。」 「おりつ様。そんな、めっそうもない。」 「直次郎さんもご親切に、ありがとうございます。急ぎますので、失礼いたします。」 抑えてはいるが、女のほうもわずかに、言葉つきが早くなっている。歳三の無礼にいく らか腹を立てているのだろう。 「………。」 歳三は無言。こういうところが、意地が悪い、といわれる。 「ごめん下さいまし。」 |
| 2 |
女が出て行くと、直次郎はあわてて見送って、戻って来た。 「いや、参ったなあ、もう。」 「気の強い女だな。」 むっとして言った。 「そんな、怒らないで下さいよ、歳さん。」 「どこのご新造だね。」 「さるご家中の、江戸定府のかたのご妻女でしてね。手前どもはあの方のご実家の方とお 付き合いが永うございます。」 「ふうん。」 「何しろ、あのご器量でございますからな。ご上司の筋から、強く望まれて嫁がれたと聞 いておりますが…ところが、お気の毒な事で。」 「亭主が病人か。」 直次郎は渋い顔でうなずいた。 「それも、お嫁に行かれた途端に……寝込まれたらしゅうございますよ。」 「ほう。」 直次郎の話によれば、さきほどの妻女は――おりつ、という。 そのおりつの亡母というのが、今は小川町で開業している、かなり裕福な町医者の娘だ ったという。父親が先代藩主の頃に藩医の一人を勤めていた経緯で、家中から縁談の申し 越しがあり、形式上は藩内の他家の養女にして、武家の娘ということにしてから嫁いだ。 その手の結婚形態は、身分制の世の中といっても、抜け道として珍しくない。 つまり、その結婚によって産まれたおりつは、父を武士、母を町家の人に持つ、という ことになる。町家といっても相応の身分や資産のあるところであれば、かえって外戚とし ては頼りになる。実際に、おりつの実家は今も小川町の祖父とは親密で、以来一家は医者 と薬には事欠かない、ということだった。 「病弱な夫にはもっけの幸いというやつか。」 と、歳三は勘どころよく話をつないだ。 「ええ。だから祖父の家業を当て込んでわざわざ縁組したのじゃないか、という噂ですが ね。でも、いくらおじいさまが名医だといったって、あのお方が別に医者の心得があるっ てわけじゃない。いそいそと嫁いでみたら亭主は病人で、殆ど看病に来たようなものだっ ていうんだから……お可哀相でしかたありませんや。……かといって、一端入った家をお っぽり出して逃げ出すってわけには行きませんしねえ。双方とも体面ってものがあります から。」 この時代、既婚の女性が皆「貞女は二夫にまみえず」という思想にがっちりと束縛され ていた、と思うのは大きな誤解で、江戸では元来女の数が少なかったという歴史からも、 町家では女の力が強い。亭主が気に入らなければ、さっさと見切りをつけて再婚、再々婚 というつわものの女たちもいる。よほど強情な男でなければ、親族、大家、仲人たちが周 辺から援護して離縁に承諾させてしまうことができる。臨機応変ということがきくのであ る。ただし、やはり武家の社会では婚姻、離縁ともに手続きや互いの家のかねあいも複雑 で、そうそう気楽にはいかない。 「武家というのは七面倒なものだな。」 「ええ、あたしの娘や妹だったら、こんな先のねえ暮らしをさせちゃいられねえって、首 に縄つけてでも連れ戻しますがねえ。それにまあお姑様というのがきついお人でね。女手 ひとつで今のご当主を育てたもんで、いつまでも息子べったりらしいんですな。こんな惣 菜じゃ滋養がつかないの、寝間着は毎日陽に当てろだの、その簪は派手過ぎるだのって、 いちいち細かい事まで口出しするらしいんで。全く、あんなにお綺麗で良くできた嫁御の どこが気にいらないのかね、罰当たりにも程がありますよ。」 「いい嫁だから、余計カンにさわるんじゃねえのか。」 お堅い武家でも、中にいるのは女どうしの嫁姑である。 「なるほどねえ。……今だって、こんな夜道を使いに出したりして、どういうつもりなん だか。下女だっていない事もないのにね。それにさっき駕籠を断りなすったでしょう。あ れだって、きっと婆さんに贅沢だって文句言われるからに決まってますよ。」 直次郎は、自分がおりつの身内ででもあるかのように、口をとがらせている。 「何だか、随分いれ込んでるんだな。」 「そりゃ、あたしはおりつ様には若い時分から……おっと、いけない。ついつい喋り過ぎ てしまいました。」 やや、照れたような顔をした。本来、客の噂話を他の客にぺらぺらとしゃべるのは慎む ものだが、周囲に人のいないこともあり、いつになく気が緩んだのだろう。これで、一杯 飲みに行って舌がなめらかになれば、直次郎の話は半刻や一刻でも続くかもしれない。 「あんた、確かに商売変えしたらいいかもしれんな。話が面白い。」 「たまさかの事ですよ、日頃はむつかしい顔をしてちゃんとやってます。」 「そうすることだ。じゃあ、また来るぜ。」 歳三が立ち上がると、直次郎は毎度有り難うございます、と言ったあと、小声で、 「今度また、例の店でも冷やかしましょうや。」 と、囁いた。 「へ、しょうがねえな、かみさんに締め殺されるぜ。」 歳三が店の表へ出て歩き出すとまもなく、背後に松代屋の小僧が出て来て、戸締まりを 始めた。通りの主立った店は殆ど閉まっていて、少し離れた居酒屋、小料理屋のたぐいだ けに、灯が洩れている。人通りは少ない。 (……駒塚橋と言っていたな。) ああは言ったものの、何となく気に掛かっている。音羽町を、急ぎ足で南に下り始めた。 小さな草履を履いていた女の足と、歳三の速足との差を考えれば、ひょっとまだ道筋に、 その背中を見つけることがあるかもしれない。 |
| 3 |
歳三は表通りを足早に歩いて行く。宵闇の中、かなり前方にぽつん、と一つ、提灯の明り が見えて来た。 (……あれか。) 歳三は、一定の距離を保ちつつ、後をつけてゆく。と、その前方、町角の居酒屋からふいと 暖簾をくぐって出て来た一つの影が、同じ方向へ明りを追って歩き始めたのが見える。 歳三の夜目で見ると、その影は素浪人らしい。腰から下が、袴の形に揺れている。不審な ものを感じながら、歳三はそのまま、一定の距離を保って歩いた。 先頭に提灯を下げた女、中間に浪人の影、最後に歳三、という俯瞰になる。 ふと、提灯の明りが横道へそれた。前方の影も従うように同じ角で曲がってゆく。 (近道する気か、馬鹿な。) 歳三は足を速め、曲り角を折れたが、広い屋敷の練り塀で二つの姿が見えない。駆けた。 少し離れた空き地裏の木立ちの近く。先ほどまでの町並から、ちょっと裏手に入っただけ というのに、木々の近くは人気がなく、合間の闇が濃い。しかし、ある一点だけがあかあか と照らされている。提灯が一つ、地に落ちて燃えているのだ。しかしその火は間もなく消え 薄い月明かりだけになるはずである。その提灯からほど近い場所には、先ほどの女おりつが、 酒気を含んだ長身の素浪人にからまれて、立ちすくんでいる。 「そこを、お通し下さい。」 あごをひき気味にして、気強く言った。が、声がわずかにかすれている。 「まあ、いいじゃねえか、ご新造。」 酒で荒れた声を出した浪人は、懐手のまま、にやにや笑っている。 「何ゆえ、道ふさぎをなさいますか。」 「なにゆえ、ときたかね。こんな暗え所で別嬪が一人っきりで歩いていちゃ、何ゆえもかに ゆえもわかりそうなものだぜ。」 「先を急ぎます。お退き下さい。」 「命まで奪ろうとは言わんよ。……なあ。」 「………。」 女はそっと、胸元の懐剣に手をやった。袋の口紐はすでに解いてある。そのまま小さな足を 一歩引いて、きびすを返そうとした。と、浪人は、行く手をふさぎ素早く女の手首を掴んだ。 「何を……おやめなさい!」 振りほどこうとした。が、細い手首に男の汗ばんだ指がきつく巻き付いている。男は、くっ くっと肩で笑っている。 「無礼は許しませぬ。」 「いいねえ、やはり、武家の女はこたえられん。」 浪人は獲物の生きのよさに却って喜びを注がれた形で、力ずくで女の体を両の腕に抱え込ん だ。おりつは必死で離れようとするが、両肘のあたりを押さえられているため、身動きが出来 ない。 「……!」 すえたような酒臭い息が、むっとおりつの顔にかかった。思わず眼を閉じて、そむけた。 「やめろ!!」 浪人が背後の声に振り返った隙に、おりつは、どっとその胸を突き飛ばし、離れた。 歳三が、背中の荷を投げだし、右手に木刀を提げて月明かりの下に立っている。 「何だ、貴様。」 浪人は、当然すぎる問いを吐いた。 「そこのご新造の、用心棒さ。」 「貴様が?」 歳三はべっ、と手に唾をかけてから、女のほうに向かって声をかけた。 「ご新造、下がってくれ。」 おりつははっとして退き、震えながら漸く懐剣を取りだし、柄を握りしめて立った。 「ふん。町人ふぜいが、いきがると怪我をするぜ。」 「なりは町人でも……女を手ごめにしようなんてえ、酔っ払いの薄汚ねえ浪人ずれよりは、 ましさ。」 「何をっ。」 浪人は瞬時に激昂し、刀に手をかけた。 「やるかい。……きなよ。」 歳三は、右手の木刀をすっとさしあげ、さらに左手を軽くそえた。木刀の先は、左側の 向きに傾いている。それほど美しい構えではない。相手は、嘲笑した。 「木刀で、真剣にかなうと思っているのか。」 「充分さ。千鳥足の、よちよち剣法にはな。」 浪人は、たたっ斬ると吐き捨てながら、抜刀して突進してくる。歳三は、体をかわし、 浪人の右横面をびしりと打った。 「げっ!」 浪人が大きくよろめいた瞬間、歳三は切っ先を翻し、思い切り右籠手を打ち据えた。 刀が落ちた。歳三はその刀を蹴飛ばし、地に膝をつけた浪人の襟がみをつかみ、鼻っ柱を やや中指を高くした拳で殴り飛ばした。 「ぎゃっ!!」 蛙を踏んだような声を出して、男はひっくり返った。鼻血が吹き出している。歳三は凝然 とその無残な男の脳天を見下ろして、 「逃げ足だけは、勘弁してやる。消え失せろ、外道が。」 「う、うう……」 浪人は言葉にならぬ発音でうめき、よろよろしながら必死に立ち上がった。更に冷たい 声がそこへ浴びせられた。 「待ちなよ。」 歳三は落ちた抜き身の刀を拾い上げ、浪人の体に寄り添うほど近くに立った。 「ひ……」 浪人の顔に恐怖が走っている。歳三はにっ、と笑って、 「忘れ物だ。」 と、大胆にも相手の鞘をぐっと引き寄せ、大刀をするするとおさめてやった。浪人は、化 け物を見るように放心して、右腕をだらりとさせたまま、後も振り返らず、逃げ去ってい った。足腰を痛めつけてやらなかったのはこのためである。もっとも、さらに歯向かう気 配を見せていたら歳三はこの位でやめたかどうかわからない。 歳三は木刀を荷の脇に立てかけておいて、ふう、とひと息ついてからおりつのほうを振 り返った。 おりつは、茫然と立ち尽くしている。歳三は無言のまま薬籠を開け、ごそごそと畳んだ 提灯を取り出し、おりつに近付いて、火を打った。辺りがぽっと明るくなる。 「大丈夫か。」 「……はい。」 「言わんこっちゃねえな。」 「……かたじけなく……」 歳三の声は、時として必要以上に無愛想になる。女がやや体をかたくして頭を下げたのに 閉口して、少しなだめるように言った。 「まあ、いい。」 おりつは気取られまいとして顔をそむけるが、ほっとした気のゆるみで涙ぐんでいる。 「それ、しまったらどうです。」 歳三に指をさされて、おりつは、はっと我に返って、手にした懐剣を胸元にしまった。 「勇ましいのは結構だが……日が落ちてからこんな道に入り込むなんざ、無茶ですな。」 「はい。」 「この辺りは、百姓のかみさんだって夜は歩きませんよ。近頃、ああいうごろつき浪人が 市中にうようよしているんだ。辻斬り、強盗だって珍しくない。」 「はい。……」 「まあ、お武家の奥方じゃ、噂にうとくても仕方がないがね。」 相手が「奥方」というほどの身分にあたらないのは、無論承知している。こういうところ は歳三の皮肉癖である。 「申し訳、ございませぬ。」 「謝る事はない。」 「本当に、うかつでございました。……ありがとうございました。」 おりつはもう一度、美しい角度で、頭を深く下げた。 「何、いいんだ。」 歳三は照れ隠しのようにそっぽを向いた。少しの間があって、 「鏡をお持ちかね。」 「え?……ええ。」 女はきょとんとして小首をかしげた。時々、会話のつなぎめが唐突に飛ぶのも歳三の癖の ひとつらしい。 「じゃあ、髪を直して、お帰りなさい。」 あ、と乱れ髪に気づいて、おりつは恥ずかしそうにうなずき、素直に「はい。」と答えた。 さっき、浪人の腕の中で抗ったために、鬢が少しほつれている。 「送りますよ、もちろん。」 「はい。お願いいたします。」 おりつは頭を下げた後、真っ直ぐに歳三を見つめた。初めて、この男を信頼したらしい。 「………。」 歳三は視線を外して、そこへ灯りを置き、少し離れた位置に立った。女の支度をしげしげと 見つめたりしないのが、粋だと思っている。おりつは手鏡を出し、提灯の明りで髪や着物を 整え始めた。歳三はふと数歩歩き、何かを拾い上げている。おりつは鏡のなかで、小さく口 をあけた。 「……あ。」 「これ、でしょう。」 歳三は声をかけて、平打ちの後ろざしを差し出した。吉祥の華紋を彫りぬいた細工の凝っ た見事な簪である。 「はい。」 おりつが微笑した。歳三は、初めて見る笑顔に、一瞬目を奪われている。 おりつはいったんは簪を受け取り、ややあって、 「……歳三どのと、おっしゃいましたか。」 「ああ。」 おりつはちょっと言いにくそうに言葉を選んで、てばやく懐紙の中に簪をくるむと、前 に差し出した。 「あいにくと、相応の持ち合わせがございませぬ。誠に失礼とは存じますが、これを……」 「馬鹿言っちゃいけねえな。」 また、声音に鋭いものがまじった。 「………。」 「そんなつもりはない。見くびってもらっては困る。」 「でも、それでは……」 「私はね、見ての通り、半分は薬屋だが、半分は剣術屋さ。さっきの喧嘩は私が好んで買 ったものだ。あなたが恩に着る事はない。」 「……好んで?」 「ああ。あなたのお陰で、楽しませてもらった。」 「喧嘩が、楽しいのでございますか。」 「あの程度の相手なら、道場の稽古よりよっぽど気楽だからね。技を試すには丁度いい。」 「まあ。」 おりつはくすくす笑っている。 「それに、私は、……今日はこんななりだが、武士に憧れている。いつかはなりたい、と さえ思っている。それが、女子を助けて礼をもらえますか。」 「………。」 「いや、つまらん事を言った。」 歳三は無愛想な表情に戻っている。行きずりの女に話すことでもないと思ったらしい。 ところがおりつは真面目な顔で、 「やはり、これはもらって下さいまし」 と、もう一度両手を添えて包みの中の簪を丁寧にさしだした。 「あなたもわからん人だな。」 「戦功を立てて褒賞を受けるのは、武士のならいでございます。」 歳三は、黙った。ひとりの女からこんなふうに会話を切り返されたことがない。 「……わかった。では、いただくことにする。」 苦笑してうなずき、これは片手拝みの格好で簪を受け取った。おりつは納得して再び笑 みを浮かべたが、その表情のはしにはわずかに大切なものを手放す時の寂しさが混じって いる。 歳三は懐紙の中から簪を取り出して、ふと、女との距離を縮めた。 「?」 おりつは肩をすぼめたがそのまま動かない。歳三は手をのばして、すっとその後ろ髪に 簪をさしいれ、銀色の光をもとの位置におさめてやった。数秒だが、互いの息が届くほど の近さになっている。 「………。」 おりつは驚いて息をつめながら歳三の顔を見上げている。なぜ?という質問が、おりつ の顔には書いてある。 「勝ちいくさの、振舞いかな。」 ま、とつぶやいてから、おりつは笑い出した。笑っているほうが倍も美しい女である。 「さて、遅くなる。もう歩きましょう。」 「はい。ありがとうございます。」 歳三は、荷を背負うと提灯を腰に挿し、後も見ず歩き始めた。おりつも無言で少し離れ てついてゆく。人が見れば、武家の新造を送っていく商人の先導にしか見えないだろう。 これが少しでも男女の道行きに見えては、人妻のほうは困るのだ。歳三はそこから、ひと ことも背後に話しかけようとはしなかった。 やがて、武家屋敷の塀で囲まれた町並が見えている。 先を歩いていた歳三がふと振り向いて、 「駒塚橋の近く、と言いましたね。」 「はい、その角を曲がって、一丁ほどでございます。」 「じゃあ、ここで別れた方がいいな。もう、大丈夫だろう。」 「……本当は、家へお上がり頂いて家人からお礼を申し上げたいのですが……」 「余計な心配をさせるだけでしょう。黙っていればいい。」 「……申し訳ございませぬ。」 「いや。」 「歳三どの。」 せいしろう と、おりつはきまじめな顔で、細川越中守家中、早坂靖志郎の妻と名乗り、いずれ改め てお礼に参りますゆえと断りをのべている。ただしどこどこの家中、などというあたりは、 歳三はろくに聞きとめておらず、夫の姓が早坂というのが、わずかに記憶の隅に残ったに 過ぎない。 「どうか、おところをお聞かせ願えませぬか。」 と再度言われた時に、歳三はついむっとして、 「くどいな。」 「………。」 そういう切り口上はお前の悪い癖だ、と人からさんざん言われているのを、ふと思い出 した。慣れぬ人間には誤解を受けやすい。で、この男には珍しく、言い訳をした。 「いや、すまん。私は、口が悪い。もうお会いする事もあるまいから、無用の気遣いはや めていただこう。……そういうことです。」 「はい、では……歳三どのとだけ、覚えておくことにいたします。」 歳三はまた思い出したように、あまり言わずともよい事を言った。 「私の名は、土方歳三、という。先祖の姓だがね。」 「土方、歳三どの。」 「または、ただの薬売りの歳三さ。」 苦笑した。自分らしくもない、という思いが混じっている。 「さ、もうお行きなさい。病人がおいでだと言ったでしょう。」 「はい。」 歳三は短くそれでは、と言ってきびすを返し、さっさと歩き出した。一方のおりつは、 ゆっくりとした動作でその背中に向かって深ぶかと礼を送っている。おりつはその後もし ばらく橋のほうを眺めて佇んでいたが、やがて、小走りに屋敷町の並びに消えていった。 |
| 4 |
翌日の午後になって、多摩の川べりを、薬籠に剣術道具をくくりつけ、背負って歩 く歳三の姿がある。河原の上を鳶が輪を描いて、のんきに舞っている。 歳三は実家には寄らず、日野宿名主・佐藤家の門をくぐり、屋敷内に入って行った。 「おや、来たね。」 実姉のおのぶはこんなふうに言って、別段嬉しそうにでもなく、弟を迎え入れた。 変わって、居間。歳三は黙々と飯を食っている。 「こんな半端な時分に来て、いきなり飯を食わせろだなんて、呆れた子だよ。」 もう昼飯時はとっくに過ぎたという頃で、奉公人や小作たちは、野良で茶の一服でも しているのが本当なのである。「居候、三杯目にはそっと出し」というが、そっとど ころか堂々と突き出された茶碗に、残った飯を全部よそってしまいながら、おのぶは ぼやいた。夜には女たちが湯漬けにでもして、と思って冷や飯を残しておいたのだが、 歳三の出現で計算が狂った。 「途中で食べてくりゃいいのに。」 「新宿で朝飯食って、そのまま面倒臭えから足を止めねえで来た。」 「そんなに急ぐ用もないでしょうよ。」 「なまじな飯屋より、おのぶ姉の漬け物のほうが旨いからな。」 「ふうん、お世辞が言えるようになった。」 おのぶは歳三と似たところがあって、女にしては皮肉が巧い。ひそかに自慢にして いる糠漬けの味を誉められて、まんざらでもなさそうに口元で笑った。 歳三は食事を終え、熱い茶を飲みながら、懐から薬の紙包みを出し、おのぶに渡し た。 「これ、この間言ってた……?」 「松代屋の『滋養丸』さ。冷えや、目まいに効くらしい。」 婦人用の薬であり、わざわざ直次郎の店に寄ったのはこれを手に入れるためである。 「ああ、すまないね。ありがとう。」 「なに、ついでだ。」 おのぶは薬袋を箪笥にしまいに立ち、戻ってくると、 「歳三。小遣いは、足りてるのかい。」 と言った。歳三は苦笑して、 「よせよ、子供じゃあるまいし。」 「これは、薬のお代。」 おのぶは、紙に包んだ金を渡した。歳三は、ちょっと中身を見て、 「多いよ。」 と、畳の上でおのぶの膝の近くに戻そうとした。 「いいよ。うちの人が、あんたにってくれたんだから、取っておきなさい。」 にい 「義兄さんが。すまないな。」 「どういうわけか、あんたには甘いんだから。歳は、近頃じゃもっぱら剣術の方が面白 くてたまらないらしい。薬売りには身が入らないだろうから、金に困ってやしないか、 なんて言ってね。」 「お見通しだな。」 「あんたは石田の実家を手伝うっていったって、百姓は嫌がるし、内職の薬売りで稼い だ分は皆自分で取って、気ままにさせてもらってるんだから、そんなに気を遣わなくて いいって言ったんだけどね。」 「……うん。」 この場合、金をもらう代わりに小言もついでにもらわなくてはならない、のが弟の常 である。おのぶは当然のように改めて座りなおし、 「でも、歳三、あんたももう小三十なんだからね。少しは先の事も考えておかないと。」 歳三は無言。おのぶは構わず、 「また始まった、と思うだろうけど。で、どうなの、剣術の先生で食べていける位には なりそうかい。」 「……わからんな。」 歳三は首をひねった。道場では、勇の次に位置するのは塾頭の沖田惣次郎である。勇 も惣次郎も金欠でぴいぴいしているというのに、その次の歳三の将来などということに なると、さらさらわからない。 「あたしはね、歳三。小さい時から、器用貧乏で何をやっても長続きしなかったあんた が、もう何年も一つことに打ち込めるものが出来て、そりゃあ嬉しいと思ってますよ。 だから、出来れば好きな道で一人前に暮らしの立つ木(生計のこと)がたてられるように なれば、と願ってるの。今みたいにさ、ねぐらも定めず呑気にしているのが、あんたの 性分には合っているのかなとも思うけどね。」 「………。」 「うちの人なんて、内心あんたのそういう暮らしがうらやましい所があるんでしょうよ。 でも、あたしは女ですからね。自分の弟には、せめて勇さんのようにお嫁さんをもらっ て、小さくてもちゃんとした家を構えさせてやりたいと思うのよ。わかる?」 「……ああ。」 歳三は、ちょっと苦い顔をした。歳三は四男である。自ら独立生計の道を見つけられ ない場合は、生涯総領の兄の「厄介」という身分でいなければならず、勿論女房を養う こともできない。それが嫌なら三男の兄のように婿養子に行って、新しい家に入るくら いしか道はない。 「あんた、所帯をもちたいような女のひとは、いないの?」 と、おのぶはごく女らしい質問をした。 「いませんよ。」 おのぶはふう、と軽い溜め息をついて、 「そう。どうせ、いくら縁談をもって来たって、あんたが素直にうんって言うわけない からね、見つけるんならさっさと見つけてきなよ。よっぽどのおひい様でもない限り、 あたしが何とかまとめてみせるから。」 と、胸をそらした。 「姉さんには、かなわねえな。」 「ま、あんたも馬鹿じゃないから、ちょっとは自分で考えといてちょうだい。この話は これでおしまい。……さて、」 おのぶは、ぽんと膝を打って立った。 「義兄さんは夜にならないと帰って来ないから、あんた今日は泊まりなさいよ、いい?」 「……はいよ。」 「それからそのほこりだらけの体、綺麗に洗い流さなきゃ晩飯は食べさせないからね。 ついでに子供達もまとめて風呂に入れてちょうだい。」 「ちぇっ。人づかいが荒いな。」 おのぶは、何いってんの、と言って台所の方へ歩きながら、聞こえよがしに、 「さあ、大飯食らいが来たから、たんとご馳走を作ろうかねえ。」 と、妙に生き生きした様子で去った。 歳三は、ううん、と伸びをしたまま、その場にごろりと寝っころがっている。やれやれ 今日の説教は手短かにすんだほうだ、と思っている。松代屋で仕入れた薬が思わぬ功を奏 したのだろう。腹がくちくなると、春の陽気に誘われて、ついうとうとと眠気が襲ってき た。昨夜あまり寝ていない。布団を出すのも面倒なほどのけだるさに手足の自由を奪われ て、そのまま午睡した。 つい、昔の夢を見た。それは歳三が十七の頃のことである。 「この野郎、何べん人の顔を潰しゃ気が済むんだ!」 次兄の喜六の怒号とともに、歳三は横っ面を張り飛ばされて、畳に転がった。今は亡き 兄が、文字通り烈火のごとき形相で、不祥事をもたらした末弟の顔を見下ろしている。 「兄さん。」 そばで眉根を寄せて見守っているのは、今よりもっと若かったおのぶである。男どうしで はどれほど物騒な沙汰になるかと、仲裁のために実家の一室にいたのだ。 喜六は口から唾を飛ばして、歳三を怒鳴っている。 「十一の年には店で大喧嘩して帰ってくる、今度はもう分別もついたろうと、俺がほうぼ うに頭を下げて、あんな大店に奉公先を見つけてやったっていうのに、ちっとは真面目に 勤めるかと思えば………女中をはらませて悶着を起こすたあ、どういう了見なんだ。そん なとこばっかりいっぱしに大人の真似しやがって。」 「………。」 歳三は黙っている。反省している、というよりも、正論をぶつけてくる相手には、抗弁 しないほうがよい、という事を知っているのだ。 「主人の目を盗んで、女といちゃつこうなんざ、十年早いっていうんだ。俺ァ、おらァ、 顔から火が出たぞ、情けねえ。」 「………。」 歳三は、なおも無言。 「何とか言わねえか、この。」 再び喜六の拳が飛んだ。このう、このバラガキ、このう、と言いながら、横倒しになっ た弟の体を平手で叩いている。歳三は両腕を顔の前で防禦の形に固めて、なすがままにさ れている。とうとうおのぶが割って入った。 「もうやめて、喜六兄さん。落ち着いてよ。」 ぱっと弟に抱きついてかばった。一つか二つは、喜六の手が当たったかもしれない。 「どけ、おのぶ。今度という今度は勘弁ならねえ。」 「歳三だって、もう分かってるんだから。充分に分かってますよ。」 おのぶは思わぬ強い力で兄の体を押しのけると、歳三の前にでん、と正座した。歳三が 腕の間から薄目をあけると、嫁に行って貫禄のついた、みっちりとした姉の尻がすぐそば にある。いくぶんぎょっとして、もう一度目をつぶった。 「お前や為兄貴がそうやって甘やかすからつけあがるんだ。末っ子だからってそれじゃ、 先へいってろくなもんにならねえ。」 「そんな事言ったって、出来ちまったもんはしょうがないじゃないの。」 「何を。」 「だってそうでしょうよ。この子はこの通り見てくれだけはいいんだから、女の一人や二 人、誘われたって当たり前でしょ。」 「馬鹿。」 「なりは大きくったって、歳三の方がねんねなんだもの。一端あんな事を覚えちまったら、 抑えがきかないのはしょうがないですよ。あたしから見れば女の方が無分別ですよ。本当 にこの子の事を好いてくれるんだったら、もう少し身を謹んでくれたってよかったじゃな いのよ。おかげでせっかくの勤めを台無しにしてしまって。手代さんだって、仕事の筋は いい子だったのに勿体ねえな、っておっしゃったんだから。」 「屁理屈を言うな。それは、嫌味ってもんだ。」 喜六は声を荒げたが、おのぶは動じない。 「あら、そうですか。ともかく、やっちまった過ちを責めたって、もう今さら、どうにも ならないじゃありませんか。殴って言うこと聞くような子じゃないことは、兄さんだって わかってるでしょ。」 「俺ァ、こいつの父親だと思って叱るんだ。女のお前の出る幕でねえ。」 おのぶは年に似合わぬ腹をすえた声音を出して、 「そんならあたしは、母親だと思ってかばいますよ。おっ母さんが生きてたら、泣いて止 めただろうね。乱暴な事の大嫌いな人だったから。」 喜六がぐっ、と黙った。 「あたしがよく言って聞かせますから、今日のところは勘弁して。ね、兄さん。」 得たり、とばかりに柔らかくなったおのぶの声をきくと、喜六はいまいましげに顔をゆが めて、勝手にしろ、と吐き捨てて部屋を出て行った。不思議なもので、早世した長女をの ぞけばたった一人の女きょうだいであるおのぶに、男どもは奇妙に弱いのだ。やはり、ど こかに亡母の印象を残しているからかもしれない。 そのおのぶが背後の歳三を振り返り、小さく溜息をついた。 「大丈夫?」 「う、ん……。」 歳三は手を口元に当てて、むくりと半身を起こした。その手も口元も、血がついている。 姉は手ぬぐいで血を拭き取ってやりながら、 「……まったく……」 ふいに涙ぐんだ。すすり上げている。歳三はふとこの女きょうだいが気の毒になって、 「姉さん、すまねえ。」 と、少年らしい声をかけた。おのぶはちょっと怒った顔で、 「そうやって、素直に謝ればいいんだよ。もう……意固地なんだから。」 「………。」 「兄さんだって、おんなじ位手が痛いんだからね。手ばっかりじゃないよ、」 と、おのぶは歳三の胸をにひとさし指を押し付けて、 「ここだって痛いんだよ。あたしだってそうだ。え、わかる?」 「うん。」 おのぶは同じ手ぬぐいで目と鼻のまわりを拭いて、気を取り直したらしく、 「……為次郎兄さんだけは、大笑いしてたけどさ。」 「え。」 「歳のやつ、もう色気づきやがったか、さすがに血筋だ、だってさ。どういうんだろ。」 歳三は苦笑した。おのぶもつられてちょっと思い出し笑いをしつつ、 「大きな声じゃ言えないけど、死んだお父っつぁんや、喜六兄さんだって、若い頃は女じ ゃいろいろあったんだんだから。」 「……へえ。」 歳三は驚いた。為次郎の女郎買いくらいは知っているが、くそ真面目な次兄や、ましてや 顔すら合わせたことのない父親の行状など、知るはずがない。やはり、裏話は女の得意な 領分なのだろう。 「だからってわけじゃないけど、お前が暇を出された理由が、女の事でまだ良かったと思 ったのよ、あたしは。」 「………。」 「店の中でっていうのがまずかったけどね、独り者の男と女が、好き合っただけのことだ もの。何の罪とががあるもんか。人の女房と不義をしたとか、お店のお金に手をつけたと かっていうんじゃないだけ、ずっとましですよ。」 「姉さん。」 色恋沙汰の判定も、どうやら女の領分らしい。 「ほめたわけじゃないよ。縄つきになるようなことをしでかしたら、いくらあたしだって 許しゃしないからね。」 「………。」 縄つき、という言葉で、歳三はふたたび黙った。横領はもちろん、密通も当時の法律では 犯罪のうちなのである。無論町女房の浮気なども珍しいことではないが、堅い家柄のとこ ろでは、露見すれば一大事になる。 おのぶは、今度は大きな溜め息をついて、 「……あんたも、もう子供じゃないんだから……兄さんや、まわりに迷惑をかけないよう に、考えなさい。」 「うん……。」 歳三がしおらしくうなずくと、おのぶは、じっと歳三の顔を見た後、さっぱりとした微 笑を浮かべていた。 現在に戻って、昼寝から覚めた歳三は、仰向けのままじっと宙を見つめている。 「………。」 歳三の脳裏に、おのぶの言葉が、奇妙なほどはっきりとよみがえっている。 ───人の女房と不義をした、とか……縄つきになるようなことをしでかしたら、いくら あたしだって、許しゃしないからね。 姉の顔に続いて、ふとおりつの面影がよぎった。別に姉と似ているわけではない。むし ろずっとおとなしい方だったろう。 提灯の灯りにほの白く浮かんだ、はにかんだような微笑と、つい気のゆるみで見せた涙 ぐんだ目もとなどは、今までに歳三が抱いた女たちの誰とも少しずつ違っている。 掛け値なしに美しい女だった、と思いながら、ふと、 ───人の女房と、 という姉の戒めの声がかぶさって、歳三は、 「馬鹿らしい。」 と自嘲気味に呟き、ごろりと寝返りを打った。眠っている間に、少し汗ばんでいたらしい。 西日が低く差し込んで、障子の色を濃く照らしていた。 (三) 草餅へ続く |