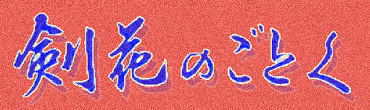 |
| 第 6 回 |
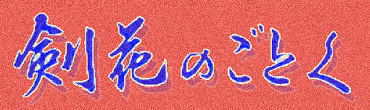 |
| 第 6 回 |
| 第 一 部 暁 闇 |
| (三) 草 餅 |
| 1 |
| それからおよそひと月ほど経って、歳三は「松代屋」に立ち寄った。顔を見るなり、手 代の直次郎があわてて帳場から立ち上がった。 「あっ、と、歳さんじゃないですか。」 「なんだい。」 「なんだいじゃありませんよ。ちっとも顔をお見せにならないんだから。一体どうしてい らしたんです。」 「どうして、って。この間仕入れた薬を持って、多摩を歩いてたぜ。」 歳三には直次郎の慌てぶりに合点がいかない。確か、仕入れの代金は支払いずみのはず である。 「もう。それどころじゃないんだから。伊之助、あたしはちょっと、出て来ます。」 直次郎は、側で大福帳とにらめっこをしている若い手代に声をかけて、ほんの少しで済 むから、よろしく頼みますよと追っかぶせるように言った。伊之助と呼ばれた若者は間延 びした返事を寄越して、そのまま数字に目を戻している。その間に直次郎は草履を履いて、 店の外へ歳三を連れ出していた。 「歳さん、ちょっと、裏へ回ってください。ここじゃあ話せないから。」 直次郎はそそくさと店の裏手、路地の人気のない場所へ歳三を誘った。しかも、積まれ た天水桶の陰にまわって、ちょっとした密談か逢引の格好である。 「なんだい、一体。」 歳三がいぶかしむ声を出すと、直次郎はほーっと溜息をついて右手で胸の上をなでおろし、 ついでにその手を自らの懐に差し入れた。 「ああ良かった、今日来て下すって。もう、あたしは、気が気じゃなくって。こんな物、 いつまでも預かっていられません。」 歳三は首をかしげている。直次郎は小声で、 「この間、歳さんが来られてから何日か後に、あの、おりつ様がおみえになりましてね。」 「あのひとが。」 歳三がつい、「あの女」と言わず「あのひと」と言ったところには、軽い敬意がある。 「聞きましたよ、こっそりと。あなた、随分いい所をお見せになったそうじゃありません か。」 「………。」 「酔っ払いにからまれて危ない所を、お助けしたんですってね。」 歳三はぽそりと、 「誰にも言うなって、言ったのに。」 「またまた、色男ぶっちゃって。それでね、どうしてもあのままではお気がすまないって いうんで、これを、お渡ししてくれって、頼まれちゃったんですよ。あたしが。」 直次郎は、懐から持ち重りのする袱紗を取り出した。 「あたしは、歳さんのお道場には行ったことありませんしね。行き違いになったら他の人 にゃとても渡せないし。今日は来るか明日は来るかって、困ってたんですよ。」 「中身は。」 「お文と、触った感じじゃ、小判で十枚ってとこじゃありませんかね。も、もちろん、封 は開けちゃいませんよ、誓って。」 「………。」 歳三は、憮然として黙った。 「こんな、大金……いや、もちろん小判の十だ百だと、店の中じゃ毎日拝んではいますけ どね。店の者や、女房にでも見つかったら、何を疑われるかわかったもんじゃない。こう して毎日、肌身離さず……冷や冷やしましたよ。」 「何だって、こんなものを。」 「そりゃあ、命を助けてもらって知らんぷり、って事ができるお方じゃありませんもの。 おそらく、旦那様やお姑様には内緒で、作っていらしたんだと思いますよ。うちの薬代だ って、お祖父様の方から立て替えておいでになる位ですから。というのもそちらの方は随 分とお内証が豊かで……」 「馬鹿な!」 歳三が話をさえぎって怒鳴ったので、直次郎は飛び上がって辺りを見まわした。 「何です、お、怒らないで下さいよ。」 「俺は、礼などいらんと言ったんだ。」 「そりゃ、歳さんの気性からして、そうだとは思うけれども……」 「俺が、金目当てで人んちにつきまとうような奴に見えるかよ。後腐れはごめんです、っ て言ってるようなもんじゃねえか。え?」 「そんな、私に言わないで下さいよう。」 困っている。その通りで、直次郎が怒られる筋合いではないのだ。歳三はぷいとむくれて、 「俺は、受け取らねえぜ。」 「そ、それはいけません、いけません。」 「こんどあの女が来たら突っ返しておいてくれ。人を馬鹿にするなと言ったはずだ、とな。」 語気が荒くなったせいで、「あの女」という呼び名に変わった。むかっ腹が立っている。 直次郎は気の毒なくらい眉を八の字に曲げて、 「ええっ、困りますよ。」 「預かったのはあんただろう。俺が受け取らんと言ったんだから、突っ返しゃ済む事だ。」 「だめだめ、それは困ります。もう、こんな気苦労はごめんですよ、あたしは。」 「おりつ殿とやらがいらねえと言ったら、おめえにやるよ。女でも買いな。」 「じょ、冗談じゃありませんよ、歳さん。あたしが、あのお方のお金を、そんな事出来る 訳がないでしょう。いいかげん、怒りますよ。」 直次郎はいつにない剣幕で、歳三の手を取り、無理やり袱紗を握らせて、珍しくきっと にらんだ。 「とにかく、お渡ししましたよ。いいですね。渡しましたからね。」 言い置いて逃げるように店の方へ去って行った。歳三は、これ以上ない位にむすっとした 顔で、袱紗を見ている。 直次郎が、店の帳場へ戻ると先ほどの手代伊之助が顔をあげて、 「おや、早かったですね。」 「すぐ済むと言ったでしょう。さあさ、いいからこの帳簿だけは急いでつけておいておく れ。あーっ、すっとした。」 「はい?」 「独り言まで、返事しなくてもいいんです。」 伊之助はぽかんとして、肩をすくめた。直次郎が帳面に目を落とし、算盤をはじき始め ていると、突然、暖簾を割ってその膝元にどさりと袱紗包みが飛んで来た。 「わっ。」 歳三がひょいと片手で暖簾をめくって顔を出し、 「今日は、仕入れはやめた。じゃあな。」 ぱっと引っ込み、消えてしまった。 「……ちょ、ちょっと、ちょっと歳さん!」 直次郎は慌てて袱紗を拾い、草履をつっかけて追いかけようとするが、間に合わない。 何しろ歳三の逃げ足が速いのだ。表に出た時は、どこの路地に折れたのか、姿すら見えな かった。直次郎が袱紗を両手で押し抱き、「ああ、あ、もう!」と歯噛みをして店に戻る と、伊之助や小僧が不思議そうな顔をしていた。 |
| 2 |
| さらに数日後の昼下がり。早坂家の玄関を松代屋の直次郎が、訪れている。 「ごめん下さいまし。」 少しあとで、奥の部屋から、先代未亡人の松枝、つまりおりつの姑が、女中を呼ぶ声 がして、お初と呼ばれた女中が小走りに現れる。まだ十五、六の娘である。 「誰か、お客様の声がしたようだけれど。」 松枝は髪は黒いほうで、まだ老いるには少し早いといった年配だが、痩せているため にいくつかの深い皺が刻まれており、実際よりは少し老けてみえる。そのくせ、いつ出 かけてもよいような隙のない着付けと髪結いを怠らず、背筋に竹の物差しでも差し込ん でいるかのように姿勢がいい。それが却って冷厳な印象を強めていて、子供っぽいお初 などは肩が一寸は持ち上がるほどに緊張する。 「あ、はい……。松代屋の、直次郎さんが。」 「松代屋?」 「音羽町の、薬種問屋で、あのう、いつも旦那様のお薬をいただいている……直次郎さ んは、そこの手代さんです。いつも直次郎さんが、お薬を用意して下さいます。」 「どうも、そなたの物言いは、前後がばらばらで筋立っておりませぬ。」 と、松枝は険のある眉根を寄せた。この顔をされると奉公人たちはぞくりとする。 「はい、申し訳ございません。」 お初は反射的に頭を下げた。早坂の家に奉公にあがって、この言葉をまず真っ先に覚え たくらいだから慣れている。 「その松代屋が、どうかしたのですか。」 「あ、はい。あの、若奥様にご用がおありだとおっしゃって。」 「りつに……?」 嫁の名を聞いて、また眉根がぴくりと動いた。 「留守だと言ったのでしょうね。」 「はい。でも、すぐにお戻りになると言いましたら、待たせてほしいとおっしゃるもの で、お勝手の方でお待ちでございます。」 松枝は冷たく、 「そなた、また余計な事を。」 「申し訳ございません。」 「何の用事だか聞きましたか。」 「いいえ、じかにでないと申し上げられないそうです。」 「不審な……」 松枝は明らかに不快な表情をして立って行き、勝手口に佇む直次郎に会った。 「直次郎と申すのは、そなたですか。」 高飛車、といったほうがよい声音である。直次郎はしまった、という顔をするが、努め て愛想良く腰を曲げて、 「あ、これはこれは、ご隠居様でいらっしゃいますか。音羽の松代屋でございます。常々 お引き立てに預かりまして、有り難う存じます。」 「そちらを贔屓にしておるのは、嫁のりつでございましょう。私は預かり知らぬこと。」 「はあ、左様で。」 「何やら、聞いたこともない不可思議な薬を買い求めては、あるじに飲ませているようで すが、さて効き目のほどはいかがなものやら……」 直次郎は内心ちょっとむっとするが、そこは本業であるからにこにこしながら、 「いえいえ、お陰様で、市中ではいささか評判をいただいているお薬でございます。どう かこちらのご主人様も、一日も早くご本復なさいますと、よろしゅうございますねぇ……。」 「お気遣いはいたみいりますが……して、当家の嫁に何用でおいでです。」 「は……いえ、……」 この逆襲にはちょっと口ごもった。 「先程も申した通り、そちらでの用足しは嫁が勝手にいたしておること。払いの催促なれ ば、急にお越しいただいても聞き入れられませぬな。その他のことであれば、あるじに代 わって私が伺いましょうが、いかがです。」 「いえ、ご催促などとはとんでもない。別のお話でございますが、ご隠居様をおわずらわ せする程のことでもございません。間もなくご新造様もお戻りと伺いましたので、ご迷惑 でなければ今しばらく待たせていただきとう存じます。」 松枝は皮肉たっぷりに冷笑を浮かべると、 「若い嫁に訳ありげな男の客ときては、いささか迷惑。」 「………。」 「私は、りつの母でもありますゆえ。その私にも話せぬとあっては……」 「はい、しかし、……」 というところで直次郎は開き直った。 「実は、おりつ様のお祖父様、古谷順徳先生からの、お言付けでございますので……」 「順徳どの?」 「はい。手前どもは、順徳先生とはご懇意にさせていただいておりますので、おりつ様に じきじきお目にかかってぜひお伺いするようにと仰せつかりまして。」 「……左様か。」 今度は松枝がひるんだ。町医者の古谷順徳は、外孫のりつの為に、結婚以来ずっと医薬 代その他を援助し続けている。早坂家としては暗黙の了解事項であり、負い目がある。 「ご承知の通り、先生はたいそうお忙しい方でございますので、……それに、藩医でいら した昔とは違い、こちらのお屋敷町にはご遠慮があって足が遠のきがちだそうでございま すねぇ。可愛い孫娘ともなかなか会えぬと寂しがっておいでで……」 直次郎も、それとなく痛烈な皮肉を込めている。順徳は先代藩主の頃は信任厚い藩医で あったが、権勢を嫌って自ら町医にくだったのである。家中でいまだにその頃の信望は残 っており、おりつの夫・靖志郎の診療にも何度か訪れたことがあるのだが、松枝の権高い 性格にとうとう嫌気がさし、来なくなって久しい。松枝は苦い顔で、 「相わかりました。ここで、りつの帰りを待つがよい。」 「はい、恐れ入りましてございます。」 直次郎は頭を下げつつほくそ笑み、松枝がつんとして行ってしまうと、ほっとして独り 言をもらした。 「ちっ、まったく、なんてえ嫌味なババアだろ。」 その時、後ろで「ふふっ」という声がして、お初が顔をだした。 「おっ、何だい、お初ちゃんか。ああ、びっくりした。」 お初は小声で、 「さすがですねえー、直次郎さん。あの奥様に、口で負けてないんだもの。」 「よしとくれよ。噂以上の鬼婆ぁだね、ありゃ。あたしゃ、背中につうっと冷や汗が流れ ましたよ。」 「そうお?あたしは、小気味よかった。お互い、しれっとして嫌味の言い合いっこなんだ もの。でも、直次郎さんの方がずっと口八丁、って感じだった。見直しました。」 「へんな感心のしかただねえ。あのね、若い娘が立ち聞きなんて、行儀よかありませんよ。」 「ごめんなさい。あたし、大奥様にも行儀作法の事でしょっちゅう、叱られてるの。武家 奉公なんて、堅っ苦しくって性に合わないみたい。」 お初は確かに、武家屋敷の薄暗がりに置いておくより、商家の店先で元気な声を響かせて いるほうがよほど似合いそうな娘である。柄が小ぶりなので幼く見えるが、横丁の小町娘に くらいはなれそうな器量で、黒目勝ちな目がくりっとして口元も愛らしい。 「よりによって、あんなのがデンと構えてちゃあね。息が詰まりそうだねえ。」 「そうそう。でも若奥様がいろいろよくして下さるから……あたし若奥様は大好き。奉公 人は皆、若奥様の味方なんですよ。大きな声じゃ言えないけど。」 直次郎がそりゃよかった、と安心しておしゃべりを始めると、奥の方から琴の音が響き 始めた。なかなか達者な音色である。 「あれ、……あの婆さんが?」 お初はうなずいて、お客に茶を入れる手を動かしながら、 「機嫌の悪い時は、きまってお琴に八つ当たりするの。始めたら、まず半時は出て来やし ませんから。」 「ふうん。」 「ね、甘い物好きですか?……若奥様にこっそり頂いたお饅頭があるんです。味方のよし みでお福分けします。」 「ははあ……お前さん、そういうわけで、おりつ様の贔屓なんでしょう。」 直次郎とお初は、顔を見合わせて笑った。 暫くしておりつが外出から戻ってきた。待たせた詫びを言っていると、横からお初が、 「直次郎さん、どうでも若奥様にお目にかからなきゃ帰らないって、大奥様の前でがんば ったんですよう。」 「これ、お初。」 「いけない、すいませ……いえ、申し訳ございません。」 「いいから、繕い物の続きをしておいでなさい。」 「はい。」 お初がにこっとして立ち去った後で、直次郎は、 「明るくて、いい子でございますねえ。」 「ええ。私もずいぶん、助かっております。」 それはそうだろう、と直次郎は思った。あの姑と顔を突き合わせての暮らしでは、お 初の持つ無邪気な可愛らしさがどれほどなぐさめになるかわからない。と、直次郎はそ の事ではおりつの為に少し安堵しながら、もう一つの気がかりの事について、おずおず と切り出した。勿論、祖父の用事で来たというのはあの場の方便で、こうして出向いて 来たのは別の理由がある。 「おりつ様、実は……先日お預かり致しました、例の物なのでございますが。」 おりつはすんなりとした顎の線を少し斜めにかしげたが、直次郎がそっと懐から袱紗 を出し、 「誠に、申し訳の立たぬ事ではございますが……」 と言うと、まあ、と驚いて目を見開いた。 「いえ、あたくしは、確かにあのお方にお会いして、お話し申し上げたんでございます。 しかしこれがいっこうに、頑としてお受け取り頂けないのでございまして……」 「………。」 「頼まれておきながら、お役に立ちませんで……」 直次郎が恐縮して頭を下げると、おりつは一度うなずきながら、 「左様でございましたか。……ですが、私も一度差し上げるつもりでお渡ししたものを、 受け取るわけにはまいりませぬ。いま一度、預かっていては下さいませぬか。」 と、素直に頼んだ。これには直次郎が慌てて、 たなもの 「そ、そうおっしゃらないで下さいまし。……あたくしも、お店者の身でございますし、 こういったものを懐に入れておくのは、その、なかなか気を遣う所なのでございます。 かといって、家に置いておきますのも、どうも心配でなりませんし。」 「ああ……それは、気がつきませんでした、申し訳ありませぬ。直次郎さん、ご迷惑で ございましたでしょう。つい、気安く……」 と、これも正直に詫びた。直次郎はさらに恐縮して、 「いえ、いえ。あたくしの気が小さいだけの事で……おりつ様にあやまっていただくな どと、とんでもないことで。」 が、おりつはその言葉を聞き流し、独り言のようにつぶやいた。 「……そう、やはり……お受取りにならなかったのですね。」 「は?」 「どこか、そんな気がいたしておりました。」 おりつはふと、わずかな笑みを漏らしたが、その意味が直次郎には把握できない。頼 まれがいのない自分を言い訳するように困った顔で、 「あのお方も、なかなか、いっこく者でございますからなあ。堅物という訳ではないの ですが、ちょっと変わったお人ではございますよ。」 歳三が普段は柔らかい頭の持ち主であることは、直次郎は別の場所でよく知っている。 しかしおりつにはその時、別の思案が浮かんだようである。 「……直次郎さん。」 「はい?」 「歳三どのがおいでになる道場の名を、ご存じですか。」 「え……?」 袱紗は、そっと取り上げられて持ち主の手に戻った。 |
| 3 |
| それからさらに数日立って、ところは牛込柳町の試衛館道場、である。さほど立派 とは言いがたい屋敷の庭も、眩しいような若葉の色が照り返って、いくぶん華やいだ ように見える晴れた昼下がり、であった。少し精を出して動けば汗ばむような、格好 の昼寝日和とでもいおうか、この時間帯は朝の稽古が終わって、仕事を持つ門人たち は帰り、昼食を終えた食客たちが依然屯している、という、どちらかといえば、一日 のうちでもぽっかりと暇な頃である。 そこへ珍しく、若い娘が質素な門をくぐって、玄関の前で立ち止まっていた。 「ごめん下さいまし。あの、もし。ごめん下さい。」 と、少しおっかなびっくり、の声を出した娘は、早坂家に仕えるお初である。そのま ま返事を待ったが、薄暗い玄関の奥はしんとして、応答がない。 お初はさすがにそのまま敷地の中を分け入っていくほどの勇気はなく、つい、独り 言を漏らした。 「『たのもう』……って言うものかしら。」 途端に、後ろで「ぷっ」と吹き出す者がある。 「きゃっ。」 驚いて振り返ると、庭木の間で長身の沖田が、くっくっと笑っている。お初はかっと 赤くなって、 「き、聞こえてました?今の……」 「道場破りにしては……」 と、沖田はひとり笑いがおさまらない様子である。お初はますます汗をかいて、 「あ、あのう、あなたが、土方、歳三さま?」 「え?……いえ。違います。」 沖田はきょとんとして、笑うのをやめた。滅多にない人違いである。 「あら、ごめんなさい。……背が高くて、様子のいい人だって、お聞きしたものですから。 いやだ、あたしったら……」 お初は自分の勘違いを恥じて、ますます赤くなる。沖田はくすくす笑ってから、 「私は、ここの門人で沖田といいますが、あなたは?」 「えっ。い、いえ、ご用のあるのは、私じゃありません。うちの、若奥様です。」 「奥様?」 「ええ、それで、その、土方歳三様とおっしゃる方が、中においでになるか、ちょっと、 聞いて来るように言われたんです。」 「土方先生なら、いらっしゃいますよ。」 と、沖田はこれも、滅多に使わない敬称をつけて呼んだ。 「ほんとですか。」 「ええ、お呼びしましょうか。」 お初は急に生き返ったように弾んだ声を出して、 「はい、お願いします!」 と言うなり、あわてて門から飛び出し、 「奥様、奥様。おいでになるそうでございますよ。」 と、やや高い声を出しつつ呼びに行った。 沖田がぽかんとして立っていると、お初に連れられ、おりつが門内へ入ってきた。お初 は先ほどは持っていなかった、重そうな風呂敷包みを両腕に抱えている。女中の粗忽ぶり を恥じるように、美しい丸髷の頭を下げながら、 「……申し訳ございません。うちの者が、お騒がせをいたしまして。」 「え……いえ……」 と、曖昧な返事をする沖田は、思いがけず現れた武家女房のおりつの美しさに見とれてい る。およそこの家に来るはずのない客だ、という顔であった。 「恐れ入りますが、こちらの土方歳三様にお取り次ぎを願えますでしょうか。」 「は……」 変わって、道場。中央では永倉新八、藤堂平助ら、食客の数人が立ち会いの稽古を続け ている。沖田はひょいと入ってきて、黙々と木刀の素振りを続けている歳三のすぐそばへ 行き、皆の気合に隠れるように小さな声で、 「土方さん。」 「………。」 歳三は振りながらちらり、と見たが、答えない。邪魔をするな、という顔なのだ。 「土方さんってば。」 と、再び呼んだ。歳三はむすっとしたまま、 「何だ。」 「いいから、ちょっと。」 沖田はふいっと歳三の腕を取り、動きを止めてしまう。歳三はその敏捷さに一瞬はっとし たが、沖田は意に介さず、そのまま腕を取ってなだめすかすように、さっさと道場の外へ 連れ出してしまっている。 「おい、宗次郎。」 「まあ、まあ、まあ、いいからいいから………」 他の者たちは、不思議そうに見送っている。 沖田は道場裏の井戸端に、せっつくようにして歳三を引っ張って来た。 「おい、いったい何の用だ。」 「道場なんかじゃ言えない用なんですよ。」 「何?」 「早く、汗を拭いて下さい。急いで。」 沖田はせわしなく井戸水を汲み、持っている手ぬぐいをじゃぶじゃぶと濡らした。 「何を、あわててる。」 「お客様ですよ。玄関に、お待ちです。」 「客?俺に……?」 沖田は手ぬぐいを固く絞りながら、 「しかも、すっごい、美人。」 と、力をこめる手に合わせて、刻みながら言った。 「美人……?」 「音羽町の帰り道に、お世話になった方だそうですよ。」 歳三が、あっという顔をする。つい、うろたえた顔になって、 「……確か、おりつ、殿といわなかったか。」 「さあ。」 と、沖田は吹き出して、 「あわててますね。」 ぽんと手ぬぐいを投げ渡した。 「馬鹿。早く言わねえか。」 沖田はおや?と首をかしげてから、自分の気働きを自慢するかのように、 「皆の前で言わない方が、よかったでしょ。あんなお客さんなんてあったためしがな いんだから、ぞろぞろくっついて来ちまいますよ。」 「………。」 歳三は濡れ手ぬぐいでごしごしと顔を拭き、 「あの人が、俺に何の用だ。」 「知りませんよ。まさか玄関から正面きって……逢いびきにしちゃ大胆だ。」 「てめえ。」 歳三、手ぬぐいをビュッと振る。沖田、素早くかわして、 「ほんと、女の噂には事欠かないなあ。土方さんは。」 もう、おかしくてたまらない、というおどけようである。 「おめえ、どこでそういう口の聞き方を覚えてきやがった。」 けい 「そりゃ原田兄、永倉兄、藤堂兄……その他もろもろの諸兄から。」 歳三は脅すように低く腹にこめて、 「……宗次郎……。」 「口の悪さはもちろん、土方尊兄から。」 「宗次郎!」 「しーっ。怒っているヒマがあったら、早く行って下さいよ。」 どうも、悪い相手が受付係に出たものである。 そのおりつは玄関の前に、立って待っていた。お初は、気をきかせるように、少し離れ て門の辺りにいる。歳三が、玄関先に仏頂面で現れると、おりつは振り向き、男の稽古着 姿に、少しまぶしそうな表情をした。 歳三は小さく咳払いをして、頭を下げ、 「どうも。」 と、愛想もくそもない挨拶をした。おりつは、こちらもはにかみながら礼を返した。 「そのせつは……ありがとうございました。」 「あ、いや。」 「先日……直次郎さんから、確かにお返しいただきました。重ねてご無礼を致しました。」 「………。」 女でも買え、と言って叩き返したことを思い出し、歳三は気まずく黙っている。まさか 直次郎も客商売の人間だから、そんな細かいことまで告げ口はするまい。 「ですが、あのままでは、私も気がすみませぬ。」 と、おりつは微笑し、 「……もしや、こういったものでしたら、お納めいただけるかと存じまして。」 と、式台の上に置いた風呂敷包みに手を添えた。 「何です。」 おりつは、美しい指で包みの結び目を解いた。段重ねにした折り詰めのなかに、どっさ りと草餅、柏餅、それから、ちまきが並んでいる。 「ほう。」 「慣れないもので、お口に合うかどうか、わかりませんけれど。」 「……あなたが?」 歳三は意外な顔をした。武家の奥様と呼ばれていてもたすきがけの台所仕事はするだろう が、目の前の端然としたおりつからは、ちょっと想像がつかなかったのだ。 おりつはうなずき、 「あそこにおります子が、こういったことが得意で、私の師匠なのでございますよ。」 歳三は顔をあげて、お初の方を見た。お初はそれとなくこちらの様子をうかがっていた が、歳三と目が合った途端、理由もわからぬままあわててぺこりと頭を下げている。 歳三は苦笑しつつ、 「こんなにたくさん……ひと苦労ですな。」 「皆様で、と思ったのですが、甘い物ではいけませんでしたでしょうか。」 ちまきを添えたのはそのための心配りなのだろう。何しろ、当主の内儀以外は、荒くれ た男所帯という事は聞き知っている。餡子を見るのも嫌、という者がいておかしくはない。 歳三は、今度は素直に頭を下げた。 「いえ、有り難く、頂戴します。」 おりつは小さくほっとして、 「……よかった。」 「え?」 「いえ。」 恐らく、また余計な真似を、と怒り出すことも少しは懸念していたのであろう。簪の件 でも、歳三のへそ曲がりは察しがついている。「三度目の正直」で、やっと謝礼のけりが ついたわけであり、歳三もそのことに気づいて、ちょっと呆れている。 「しかし、あなたも、もの堅いお人ですな。」 「意地っ張りだとおっしゃりたいのでしょう?」 と切り返されて、歳三はつい、ふっと困ったように笑った。 「……上がって、お茶でもさし上げるべきなんだが……。何しろ、むくつけき野郎どもが ごろごろしているような所でね。」 おりつはそれには答えず、くすっと笑った。 「何か?」 「私も先夜、同じような事を申し上げました。」 「ああ。」 「ですから、どうぞお構い無く。あまり時間もございませんので……」 「そう、ですか。」 と言いながら、歳三にはほっとしたような、わずかに残念なような気持ちが交錯する。 「それでは、これで失礼を。」 と、おりつが一礼して玄関を出る時、歳三は珍しく、門を出た所まで送っている。そこで 女主人は凛とした声音に戻り、女中をうながした。 「お初、参りましょう。」 「あ、はい。」 「ごめん下さいませ。」 おりつが静かに会釈して去り、お初も続けて頭を下げ、ついて行く姿を見送った後、歳三 は憮然としていたが、急にその場を取って返し、勢い良く玄関を上がり、その脇の部屋の障 子をぱん、と開けた。「わっ」と声がして、中にいた原田左之助、藤堂平助、永倉新八の三 人が窓の側から飛びのいた。道場から抜け出し、そっと覗き見ていたらしい。気まずい、引 きつった笑いを浮かべている。 歳三は低く唸るように、 「……おまえら、なあ……」 と、こちらは笑わずに引きつっている。永倉が持ち前の愛嬌のある笑いを混ぜて、 「はは、は……何だ、土方さん、気づいていたのか。」 「あのな……。」 今度は原田が隣の藤堂を指差して、 「いや、平助の奴が、すげえ別嬪が来てるっていうんでさ。」 藤堂は慌てて指を差し返し、 「そ、そしたら、左之さんが覗きに行こうって。」 「………。」 歳三の無言のあと、原田、藤堂は続けて、 「上がってもらえば良かったのによう、歳さん。」 「そうですよ。むくつけき野郎共とは、ひどい。」 皆が、「おう」とうなずき合った時、歳三、ぐっと拳を握りしめる。 「逃げろ。」 永倉の一声で、一同、驚くべき早さでどっと逃げ出した。どたばたという足音に、歳三の 怒号が追いかけている。 「おーお。」 と、沖田、のほほんとした顔で、庭の植え込みの影から立ち上がる。何気ない顔で玄関に 入り、式台の上の折り詰めの蓋を開け、草餅をひとつ、ぱくついた。にこっとして、 「うまい。」 器用に、今あいた隙間を上手に埋めなおしている。 |
| 4 |
| この家の一番奥の間(と、いうほど大層なものではないが)は、先代天然理心流の宗家、 近藤周斎老人の隠居部屋になっている。周斎は養子の勇に家督と流派を譲ったあとは、寝 たり起きたりの状態なのだが、今日は陽気もいいせいか、布団の上に起き上がっている。 おりつ持参の草餅をうまそうに食べながら、内弟子として古いつきあいの沖田と、茶飲み 話をしている。そろそろ斜めの西日が、障子に差し込んできた頃である。 「歳のやつに、女の客がねえ。」 「ええ。」 周斎は、この流派の持ち味らしく道場では容赦なく厳しい人であったが、何しろ女房を 九人持ったという逸話の持ち主であるから、元来は洒脱で砕けたところがある。対する沖 田も、道場では鬼師範とまで恐れられながら、冗談が三度の飯より好きらしい、と思われ ているくらいで、その点は師弟で相似したところがある。師弟という関係が介在していな ければ、オジイチャンと孫、というほどの年齢の開きがあるのだが、周斎はこの沖田を、 隠居後の話し相手として一番好んでいる。流儀の秘蔵っ子、という以上の可愛げが、この 若者にあるせいだろう。 「上玉か。」 と、老師匠は往年鳴らした時の言葉づかいをした。沖田は首をひねって、 「そういう言い方は似合わないなあ。……美しい人でした。」 「なぜ、俺を呼ばねえ?」 「は?」 沖田は、頓狂な声を出した。 「ぜひ、菩薩様のご尊顔を拝みたかった。」 「また……。」 ようやく意味がわかって、苦笑した。この点の伝授は、秘蔵の弟子にはとんと伝わらなか ったのである。 「武家の女房とはね。野郎、宗旨がえしやがったか。」 周斎は、歳三のことをそう言った。 「あの人、そんな間柄じゃありませんよ。」 「なぜ、わかる。」 「あのふてぶてしい土方さんがですね……変にかしこまっちゃって。まるで借りて来た猫 みたいになっているんです。とてもそんな色っぽい雰囲気じゃない。」 「そう見えたかい。」 「ええ。あんなの、初めて見ました。無理して平気なふりをしているようでしたよ。土方 さんにも、得手不得手があるんですかね。……ふふふ。そのあとは、妙にふてくされちゃ って……。」 「そりゃあ、あれだな。」 「はい?」 「歳は、惚れたな。」 「えっ。」 周斎はにやにやして、 「ちょいと遅咲きだがなあ。うふふ、いじらしいじゃねえか。あいつが照れるなんてさ。」 「そうなんでしょうか。」 「そうよ。」 「へえ……。」 と、沖田はにわかに信じがたい、という面持ちで目を丸くしている。 「ああいうやつはね、人がつっつくと余計意固地になりやがるから、宗次郎、お前さん、 からかっちゃいけねえよ。そおっと、しておきな。」 「はい。」 「たまにゃあ、いい薬さ。」 「薬?」 「いい年して女に惚れたこともねえなんて男は、どこか人間がかたよってていけないよ。」 と、周斎はなかなか含蓄のあることを言ったのだが、沖田には別の疑問が浮かんでいて、 「でも先生。……相手は、人妻ですよ。」 「うふふ。」 老師のにやにやが大きくなって、目から頬にかけての皺の影が深くなった。 「?」 沖田はまた、きょとんとして師匠の言葉を待った。 「人目を忍ぶ恋ってのは、……おつなもんでね。」 「………。」 弟子は、赤くなっている。 「ことに人妻の色気ってのは、こたえられねえ。」 「周斎先生。」 「ふふん……」 老人は茶をまたひとすすりして、笑っている。 道場では、より強くなった晩春の西日が差し込んでいる。沖田が入って行くと、歳三 が一人、木刀を傍らにぼんやり座っている。 「型の、稽古ですか。」 「ん……いや。」 黙然と思索にふける、というわけでもなかったらしい。本当に、ただぼんやりとした声 を出した。沖田は明るく、 「ごちそうさまでした。あっという間に、売り切れましたよ。」 「俺に言うこたねえさ。」 「でも、お陰様ですから。……あんなにたくさん、重たかったろうな。」 「………。」 「暗くなる前に、帰れるかな。」 「え?」 沖田も歳三も頭の回転は速いのだが、その為に時々、聞き返さないと主語が省かれてい る事がある。 「あの二人、ですよ。あれから、穴八幡までお参りに行くって言っていたから。」 「馬場下町のか。」 「ええ。といっても用事があるのは、八幡の近くにある寺のほうだそうですがね。何でも ご先祖代々の言いつけで、お参りは五日か十日のつく日と決めているそうです。あのお付 きの娘が、そう言っていた。帰りに門前の茶店でおごってもらうのが楽しみだそうで、早 く行きたくてそわそわしていたんです。」 「……宗次郎。」 「はい?」 「そんな事を、俺にしゃべって、どうする。」 「別に……ひとりごとですよ。」 「もう、かかわりはねえよ。」 歳三の声がわずかに怒っているように感じられたので、沖田はそうですか、と言って、 ちょっと肩をすくめた。 そのすぐあとで、沖田が母屋の廊下を歩いていていると、原田左之助が来て、呼び止め た。 「よ、沖田。」 と、親しげに肩をかかえこむ。これは原田の癖である。 「なんです。」 「歳さん、何て言ってた?」 沖田が不思議そうに聞き返すと、原田はぴっと小指を立てて、さっきのこれ、と表現した。 「いやだなあ。」 「まさか、本当に提灯を貸してやっただけ、ってんじゃねえだろ?」 「別に、何も言ってませんでしたよ。」 原田はてんから信じていない顔で、 「うそつけ。なんだか、わけありって様子だったぜ。」 沖田は真面目な顔で、 「夜道で提灯を落として燃えてしまったから、たまたま通りかかった土方さんが自分のを さしあげたっていう話の通りなんでしょ。」 と言って、とってつけたように、 「……多分。」 と、いうひとことを添えた。 「そうかなあ。……あの人が、そんな親切か?」 「あれで優しいところもあるんですよ。」 「女には、か?」 「さあ。とにかく、もうこれで関わりはないそうですよ。」 「うへっ、勿体ねえ。」 「何言ってんですか。」 「だって、あんな別嬪がわざわざ訪ねて来たってのによう。はい、さようならって追い 返さなくったってさあ。」 「だって、人妻ですよ。」 と、沖田は奇しくも、さっき周斎に言ったのと同じ言葉を使った。だが原田はからっと 笑って、 「子供だなあ。人妻だからいいんじゃねえかよう。一盗二婢、ってのを知らないかね。 お、そういやその両方がお出ましだったな。」 と、いうのは男から見た女との色ごとの位づけである。ちなみに、一盗(人の女をこっ そり頂くこと)二婢(使用人)、三と四には妾や遊女などが入り、五妻となる。二から四 は順序が入れ替わったり省かれたりで諸説があるが、いずれも自分のものなら最下位 に位置する妻が、他人のものとなると首位に上昇するところが身勝手ながら的を得て 面白い。 が、沖田はそういう冗談だけは受け付けずに、 「原田さん!」 と、たしなめた。 「なーんだつまらん。勿体ねえ。」 原田がぼやきながら行ってしまうと、沖田はまったく、どいつもこいつもという顔で つい、口をとがらせた。 (四) その嫁へ続く |