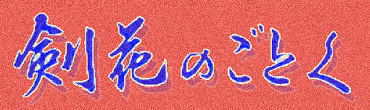 |
| 第 7 回 |
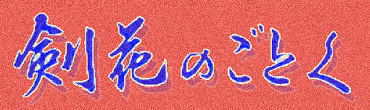 |
| 第 7 回 |
| 第 一 部 暁 闇 |
| (四) そ の 嫁 |
| 1 |
| ここからしばらく、物語は本題を離れることになる。書きたいように書いているのでやむ を得ない。 初夏と呼ぶにふさわしい日になって、おりつはお初に手をとって教えながら、縫い物をし ている。庭の青もみじが、小さな手をてんでに振っているかのような風が時折舞いこんで、 穏やかな午後であった。お初は四半時も黙っていると我慢の出来ない性分らしく、細かな縫 い目に指だけは休めないように気をつけながら、おりつを相手に色々な話をする。それが、 気ぶせりな事の多いこの家の主婦としては丁度良い息抜きを兼ねてくれるので、姑に聞こえ ない程のおしゃべりであれば、いつも大目に見ている。身分の上下がなければ、仲の良い姉 妹といった感覚に近いかもしれない。 お初は鋏で糸の端を切った音を合図にしたように、ふと思い出して声を出した。 「若奥様。」 「何?」 「……ちょっと、素敵な人でしたね。」 「え?」 お初よりは美しい仕上げの縫い目に気をとられていたおりつは、ふと指先をとめた。 「あの、沖田様っていう、お若い方。」 「……ああ……」 おりつは勘違いに気づき、急いで表情を繕った。 「気さくで、良い方のようでしたね。」 「お侍のくせに、おかしいんですよ。ひどく笑い上戸。」 言いながら、お初は自分がくすくす笑っている。 「あなたが、何か言ったからではなくて?」 「……はい。」 急に恥ずかしそうな声になった。 「何と?」 「ごめん下さい、って呼んでも、返事がなかったものですから……」 「ええ。」 「たのもう、って言わなきゃ駄目かしらって独り言を……、そうしたら、あの方が後ろに立 ってらして……」 「ま。」 今度はおりつがつい笑い出し、ごめんなさい、と言った。お初はお初で、剣術の道場などと いう場所に行ったことがないから、あがっていたことも察しがつく。先におとないを入れる ように指示したのは自分であるから、からかっては可哀相だろう。お初はあわてて、おりつ の詫びの言葉を手を振って打ち消してから、違う話題に飛んだ。 「でも、若奥様を助けて下さった、あの土方様っていうお方を見て、ちょっと驚きました。 だって役者みたいな色男なんですもの。」 「これ。はしたない事を。」 こういうところが、町娘らしくこまっしゃくれていて、姑に叱られる点なのである。 「すみません。……でも、木刀一本で酔っ払いをやっつけたっていうから、もっと弁慶みた いな豪傑かと思ってたんです。」 おりつは真顔に戻って、 「……その話は、内緒ですよ。」 「はい、もちろん。」 お初はうなずいた。嫁のおりつが、若い男に会いに行ったなどという事が隠居に知れたら どんな咎めを受けるかわからない。 「でも、あれですね。うちの旦那様も、剣術なんて荒っぽい事、おやりになったんでしょう か。」 おりつは小首をかしげた。ころころと話が飛ぶのも、そそっかしさの一つの要因らしい。 「そりゃ、今はお体が悪くていらっしゃるからあれですけど……お小さい頃は、おやりにな るものなんでしょう?」 と、お初は竹刀を握るまねをした。 「そういえば、あまり聞いたことがないけれど……。やはり、武術よりも学問の方にご熱心 だったのではないかしら。お役目柄が代々そういった事ですし。」 夫は秀才の誉れが高かったのは、よく母親の口から聞かされるが、武芸まで達者だったと は思いがたい。どちらかといえば運動とは疎遠な、繊細な肌合いをしている。 お初はまたくすっと笑って、 「すみません。なんだか、変だなあと思って。」 「何が?」 「だって旦那様のようなれっきとしたお武家様が、肝心の武芸はまるでなさらないのに、あ あいうご浪人たちが、せっせと腕をみがいているなんて。」 と、話はまた試衛館の浪人たちの事に戻ったらしい。 「………。」 「もし、異人といくさになったら、どうなるんでしょう。」 「……そう、ね。」 「きっと大奥様が代わりに『やあやあ、我こそは』って、ご出陣なさいますよ。だって、こ の家でいちばんお強いんですもの。」 おりつは苦笑して、とうとうたしなめた。 「お初。おしゃべりが過ぎますよ。」 「いけない。……申し訳ございません。」 ぺこり、と頭を下げた若いしぐさを見ておりつは、 「ここへ来た頃は、おとなし過ぎるくらいで心配したほどだったけど。」 と言った。 「……とりあえず、静かにしてなきゃいけないと思って。だって来る早々、奥からいきなり こういう方が。」 と、お初は頭の上に指でツノをかたどってみせた。 「これ。」 「ほんと、若奥様がいらっしゃらなかったら、裸足で逃げ出してましたよ。」 「………。」 その時、奥の方から「お初、お初や」と、松枝の声が聞こえる。お初飛び上がるように、 「はいっ。」 と返事をすると急に小声になって、 「噂をすれば、でございますね、くわばらくわばら。」 さっと布地をたたんでそそくさと席を立った。 おりつは、縫い物を続け、針に髪の油をつけようとして、ふと手を止めた。そして針を置 き、髪にさしたかんざしをそっと抜き、そのまま手に取り、じっと見つめた。 あの夜、歳三が拾って不愛想にさしてくれた平打ちである。ふと、その光景が蘇った。 「……お気づきになったかしら……」 独り言がこぼれた。試衛館を去る時、無言のままじっと背後から見送っていた歳三の姿を思 い出している。 「………。」 おりつは、はっとしたようにかんざしをさし直し、再び着物に目を落とした。今縫って ひとえ いるのは、この時期にあわせた夫の単である。 |
| 2 |
| その着物を縫い上げて数日後の夜。早坂家の当主、靖志郎は、日頃より二刻ほど遅れて 帰宅した。玄関に膝をついたおりつが迎えに出て、 「お食事は……」 「済んでいる。」 にこりともしない。実母と違って言葉が必要以上に少ない点は、おりつが嫁ぐ前に没し た先代当主、つまり父親似であると聞いている。 二人が部屋へ戻ると、松枝が待ち構えていて、これは笑みを浮かべている。 「靖志郎、遅うございましたな。」 「……内々の、集まりがありましてな。」 「お付き合いも大切でしょうが、お体にさわるといけませぬ。ほどほどにお断りする事も 肝要ですよ。」 「………。」 「何しろ、心の臓の病というのは、心身の安静が第一なのですから……少し体調が良いか らといって、油断はなりませぬ。」 靖志郎はそっけなく、 「わかっております。」 と言って母親の顔は見ない。 おりつは部屋の片隅に先日縫い上げたばかりの着物を用意していたが、松枝はそちらに は見向きもせず、衣桁に掛けてある着物を取り、靖志郎の背に回って着替えを手伝った。 「これは、昨日、母が縫い上げたのですよ。あなたに早く袖を通して頂こうと思って、お 帰りをずっと待っていたのです。」 おりつはなるべく、母子の視線に入らぬように気をつけながら、複雑な表情をした。が、 松枝はいそいそと息子に着物を着せつけると、少し距離をとって満足げに眺めている。た くましいとは言えぬものの、白皙の美男と言われるだけあって、艶のある風合いの着物は 確かによく見栄えがした。 「まあ、思った通り、よくお似合いだこと。わざわざ広小路まで出掛けていって選んだだ けのことはありました。本当に……」 「母上。」 「はい?」 「お気持ちは有り難いが、……私の着替えなどは、妻が考えていたします。」 「ま。」 松枝は、明らかに不快な顔をした。 「母上はご隠居らしく奥でのんびりとなさっていらっしゃればよろしいのです。倅といえ ども、当主の部屋に無断でお入りになって、あれこれとなさるのはご遠慮願いたいもので すな。りつの立場がありますまい。」 「………。」 「女子には女子の役というものがあるはず。」 「それは、気のつかぬことでした。」 と、松枝は若い当主に向かって頭を下げてから、冷ややかにおりつを見た。 「では、おりつ、頼みますよ。私は部屋へ下がっておりますから、旦那様をゆっくりと休 ませてさしあげて下さい。」 「はい……。」 おりつは身の縮む思いがする。 「私が嫁であった頃は、夫にこのようにかばってもらった事などありませんでした。そな たは良い旦那様を持って、お幸せだこと。」 「はい。」 靖志郎は眉をひそめて、これは母譲りの冷たい声音を発した。 「そう嫌味を言わずともよろしいでしょう。聞き苦しい。」 「まあ、何と言う物言いです。母に向かって……」 「私は、疲れております。母上。」 「わかりました。」 松枝がむっとして去ると、靖志郎は憮然として母が着せた着物を脱ぎ、ばさりとおりつ の前に放り出した。おりつははっとして、投げ捨てられた着物を拾った。 「そちらを、着る。」 靖志郎は、おりつが部屋のすみに畳んでおいた方の着物を指している。 「でも……」 「いい。」 逆らえた立場ではないのだ。おりつは着物を広げて、夫の背に着せ掛けた。これは、松 枝が仕立てたものよりはずっと地味で濃い藍色に染められたごく目立たぬ十字絣が入って いるものなのだが、袖を通した当人には、見慣れぬ柄であることがすぐにわかったらしい。 「これも、新調か。」 「……はい。」 間の悪いことに、と思い、おりつはすまなそうな声になった。 「我が家の女どもは、少し贅沢が過ぎるな。」 「………。」 「家で着るものなどに、よけいな出費をせずともよいのだ。」 「申し訳ございませぬ。」 「お前はそうでなくとも、いろいろと算段をせねばならぬのだろう。それとも、これも小 川町からの差し入れか。」 とは、援助者である祖父の家のことである。 「まあよい。ただ、母上はお前がこれを縫っているのを知ってはりあったのだ。きつい女 だからな。」 「そのような、おっしゃりようは……」 「なんだ。」 「お義母様が、お気の毒でございます。」 「心にもないことを。」 おりつはその一言でぐっと黙って、脱ぎ捨てられた着物を畳んでいる。自分の実家では 子が親を悪しざまに言うことなど、考えられない。何より、悪く言う必要もない身内であ った。 靖志郎は文机の前に座り、書面を開きながら、 「少し、調べ物をする。一人にしておいてくれ。」 「お疲れなのでは。」 「お前と母上が顔を付き合わせていると、倍は疲れるのだ。」 こういう時も、靖志郎は嘆息も苦笑も交えない。 「では、お茶をお持ちいたします。」 「それが済んだら、先に寝ていなさい。」 「はい……。」 少し経って、おりつが熱い茶を運んでくる。靖志郎は文机の上の書物に目を落としたま ま、ふと思い出したように、 「今日、乙弥に会った。 「まあ、左様でございましたか。」 乙弥とは、亡父が妾に生ませた、二十一になる靖志郎の異母弟である。少年の頃、この 家に引き取られて育ったが、養母の松枝と全くそりが会わず、剣術に熱を上げ、市中のと ある道場に修業と称して住み込んでいる。靖志郎とはまた別の意味で屈折した性格で、扱 いにくい青年である。おりつからみれば義弟に当たるのだが、嫁ぐ前からそんな按配で、 祝言の時以来、年に数回しかこの家に顔を見せることがなく、自然、おりつにも義姉義弟 らしき親しみはない。靖志郎とも、血を分けた兄弟として笑いあっている場面などは見た こともなかった。 「おとなしく修業に励んでいるのかと思えば……近頃では流行りの攘夷熱とやらにかぶれ て、おかしな連中と交わっているらしいな。付け焼き刃のくせに、私にまで過激な論説を 吹き込もうとする。」 「………。」 「のぼせ上がって、うかうかと脱藩などせぬうちに、手を打たねばなるまい。」 「はい。」 としか、おりつには返事のしようがないだろう。 「する事もなく我が身をもてあましているから、あんな風になるのだ。」 「まだ、お若いのですから……」 「私はもっと若くして家督を継いでいた。」 「はい。」 「しかし、あれではそうそう婿の口も見付かるまい。」 「………。」 「まあ、よい。お前に話しても仕方のないことだ。」 夫は、手応えのない妻に話すのに飽きた口ぶりで、硯の墨をすり始めた。 「乙弥どのにも、久しくお会いしておりませぬ。こちらにも時々顔を見せて下さればよろ しいのですが……そうお伝えしてくださいませ。」 「無理だな。」 墨をすりながら、わずかに苦笑が入った。 「なぜでございます。」 「あいつが、この家に寄り付くはずがない。葬式でもないかぎり、戻っては来るまい。」 「え?」 「私か、母上のだ。」 「そんな事を……」 少しの間があった。靖志郎は冷たい表情のまま、また書物に目を落として、 「もう呼ぶことはない。寝なさい。」 「はい、……そうさせて頂きます。」 おりつは形ばかり両手をついて、「おやすみなさいませ。」と言った。夫の、「うむ」とい う背中越しの返事をあとに、そっと部屋を出た。そのまま暗い廊下に、しばし佇んでいる。 |
| 3 |
| 月が変わって、おりつは昼前に恒例の先祖供養と八幡への病気平癒祈願、と断って家を 出た。しかし、今はほど近い料亭の廊下を一人で歩いている。中庭の緑が美しい。おりつ は仲居に伴われて、離れに入った。座敷には、祖父古谷順徳が座っている。おりつの顔を 見て、嬉しそうな顔をした。 「おお、来たか。」 順徳はおりつが礼をするのももどかしそうに、破顔したまま席をすすめた。 「今日は、姑どのにお小言をくらわずに、出られたかな?」 「はい。病気の平癒祈願と申しましたら……今では認めてくれているようでございます。 それに、早坂が先日……」 「靖志郎どのが?」 「月に二日や三日、文句を言わず出掛けさせてやればよいではないか、と、お母様に……」 「ほう。そんな事を言って下さるようになったか。」 「近頃は、お母様にきつい事をおっしゃるようになって、私は側で、ひやりといたします。」 「それは、あの婆さんにはそろそろおとなしくしてもらいたいものだが……それで、肝心 の夫婦仲の方は、どうじゃ?」 その問いに対し、おりつはつい、目を伏せて黙った。幾分、嫁して子のないままの恥ずか しさも手伝っている。寂しげな微笑を含んで顔を上げると、 「あまり、かわりばえいたしませぬ。」 「そうか。……困ったものじゃな。」 「でも、特に波風が立つ、というほどでは……」 「しかし、なあ。」 「それは、よいのです。おじいさま。」 あまり触れてほしくない様子を察したのか、順徳もすぐに話題を切り替えた。 「容態の方は、どうじゃ?」 「はい。これに……」 おりつは書き付けを差し出した。それは看護日誌とでもいうべきもので、おりつの文字 でびっしりと、靖志郎の病状が書き込まれている。順徳は手にとって読みながら、 「ふむ、……ふむ。この日発熱、……吐き気があったか。最後の発作は……」 と、病状を察しているようである。 「最近は、お薬のおかげか、落ち着いているようですけれど。」 順徳はややむずかしい顔をして、拳をあごに当ててしばし黙ったあと、 「まあ、可もなく不可もなく……というところじゃな。このまま無理をせず、薬を続けて 様子を見るほか、ないじゃろう。後でまた、松代屋に処方を渡して、新しく調合させてお くから、都合を見て引き取りに来るとよい。」 と言って、書き付けを懐にしまった。 「いつも、お世話をおかけして……申し訳ございません。」 「気にせずともよい。わしこそ、早坂の家に往診にいってやらねばとも思うのじゃが、こ の年になっても、まだまだ忙しくてな。それに、あの松枝殿の慇懃無礼な態度には、わし は我慢がならぬ。こちらを町医と見て、そなたや、亡くなった美鈴の事まで身分が低いよ うな言いぐさじゃ。」 順徳は、思い出しても腹が立つ、といった様子である。美鈴、というのは順徳の次女で、 おりつの生みの母であり、惜しくも三十代半ばで病死したが、それは当時の医学では治癒 の及ばぬところでやむを得ず、婚家では主婦として母として、幸福な生涯を終えた。親の 欲目を除いても才色に恵まれた女性で、順徳は五人の子の中でも最も可愛がっていたし、 それ故に先立たれた事を惜しんでも余りある、という気持ちで、他の孫たちよりもおりつ たちを愛しく思う気持ちが強い。 「言っておくが、わしは美鈴を武家の妻にしようとして、画策したわけではないぞ。そな たの父上が、どうしても欲しいというから嫁がせたのじゃ。その頃、わしはいずれ藩のお 抱えを辞するつもりであったゆえ、美鈴が後々肩身の狭い思いをしてはならぬと、わざわ ざ家中へ養女に出して、身分柄不足のないようにしてやったし、それが証拠に、美鈴は亡 くなるまで、藤本の家で粗末に扱われたことはなかった。まして、おりつは生まれながら に武家の娘じゃ。早坂の嫁として何ら恥じるところはないわい。」 藤本、というのはおりつの実家の姓である。 「大体、多少家禄が上だといばってみても、息子の薬礼も満足に払えぬのではないか。わ しがおりつ可愛さで、無償で治療に当たっているというのに、傲慢もはなはだしい。」 「おじいさま。それは……」 「おお、すまぬ。……いや、だからな。それを思えば、嫁のおりつをもう少し、大切にし てくれてもよいではないか、と、わしはそれが、腹が立つのじゃ。」 「おじいさまにまで、嫌な思いをさせて申し訳ございません。」 「それがいかん。おりつ、何事につけても自分のせいと思いつめるのは、悪い癖じゃよ。 そんなに気鬱な顔をしておっては、そのうちそなたが病人になってしまうぞ。」 順徳は、深い皺にはさまれた目を注意深く細めて、孫娘の顔色を見つめた。 「……私、そんなに暗い顔をしておりますか。」 「いや、わしの前では、いつも可愛い顔じゃがな。たまには気晴らしが必要じゃ。鬼婆ア がなんとわめこうが、知らん顔をしておればよい。」 おりつはくすっとしのび笑いをした。 「おじいさまも、お口の悪い。」 「なんの。松代屋の直次郎も、同じ事を申しておったぞ。……さて、腹が減ったな。」 順徳が、ぽんぽんと手を打つと、やがて仲居が、さまざまな料理をのせた膳を運んで来 た。年寄りと女だけの昼食にしては多すぎるほどの豪華さである。 「お前の好きなものばかり、こしらえさせたのだよ。」 「まあ。こんなにたくさん、いただけませぬ。」 「なに、まだ若いのだ。たんとおあがり。おなかにしっかり溜めていくといい。」 「私ばかり、こんなに美味しいものをいただいては……申し訳ないようで。」 「何を言うか。わしの前で遠慮はいらぬ。どうせ毎日、遠慮ばかりして暮らしておるのじ ゃろう?」 「でも……残るばかりで勿体のうございます。」 「なに、ちゃんと平らげてくれる者が来ておる。」 「え?」 「これ、もう入ってよいぞ。」 やや高いその声を機に、障子を明け、一人の武士が入ってくる。おりつが思わず膝を浮 かせた、懐かしい顔が笑っている。 「まあ、……お兄さま。」 「久しぶりだな、りつ。」 藤本東吾、りつとは同腹の実兄である。先年に父が亡くなり、今は藤本家の当主となっ ている。 「御無沙汰をして……」 「お前がちっとも顔を見せないので、おじいさまにお願いして連れて来ていただいた。」 ちなみに先に話の出た美鈴は、東吾とおりつの間にもう一人の娘を産んだが、それは早 世して、順徳にとって次女の忘れ形見といえばこの二人になっている。 「びっくりさせようと思ってな、黙っておったのじゃ。」 順徳がいたずらっぽく笑った。東吾は元気よくからりと答えて膳の前に座り、 「さあ、話は後だ。いやあ、豪勢な……おじいさまの、おごりだからな。しっかりいただ いていかねば、損だぞ、りつ。」 血を分けた三人の、なごやかな昼餉が始まった。おりつが案じた料理は、みるみるうち に兄の口元へ消えていった。 |
| 4 |
| やや時が経って、食後の茶を飲みながら、身内のよもやま話となった。 「いや、わしも近頃は、めっきり弱くなった。先月などは、酔ってほんの少しうたた寝を しただけでタチの悪い風邪をひきこんでの。三日も熱が下がらなんだ。往生したわい。」 という祖父に、東吾は大きく肯きながら、 「医者の不養生ですなあ。」 と言ってにやっと笑った。 「そのわしを診て、了徳の奴め、『ずいぶん遅い知恵熱でございますな』じゃと。」 「はっはっは……。」 順徳が孫の哄笑を笑い過ぎじゃ、と言って嗜めていると、この料亭の仲居が「先生にお迎 えの駕籠がお着きでございます。」と告げに来た。 「何、もう来たのか。」 仲居の話では、今日は患者が多くて忙しいので、ぜひお早くお戻りを、との、婿の了徳 からのことづけも預かっているという。順徳は渋い顔をして、 「まだこの年寄りを当てにするか。まったく、不甲斐ない婿殿じゃ。」 と、言いながら重い腰をあげている。しかし、見送る東吾とおりつには、 「そなたたちはゆっくりしておいで。」 という微笑を残して、この甘い祖父は屋敷へ帰っていった。 兄と妹は、祖父を玄関まで送った後、料亭の中庭を歩いている。緑が柔らかく、市中の 繁華を忘れてしまうほどの清閑さで、他の客の気配を感じない。池の側にかがんで魚影を ぼんやりと追っているおりつの背後に立った東吾は、いつになくやさしく、静かな口調で、 「もう、帰って来ぬか。」 と、言った。 おりつが「え?」と振り返ると、兄が先程までの談笑とは全く違った思慮に包まれた顔で こちらを見ている。 「早坂の家でのこと、大体の察しはついておる。……もう、よいではないか。」 「お兄様……。」 おりつはその時、何故兄がわざわざ祖父との会食に顔を見せたのか、悟っていた。 「表向きは、子が出来ぬゆえ離縁されたという形にすればよい。もう四年も経つのだ。充 分だと思う。」 「………。」 「もちろん、早坂へは俺が話をつけにゆく。お前を矢面に立たせることはせぬように配慮 をするから、安心してまかせておけばよい。」 おりつはうつむいて、 「でも、それでは、藤本の面目が立ちませぬ。」 「馬鹿だな。俺が、妹を見捨てて保身をはかるような男だと思うか。」 「いえ……」 昔程の勢いはないとはいっても、家中での格は明らかに婚家の方が上なのである。藩に 届けを出し、許可を得て婚姻を結んだ以上、身分の低い嫁の実家から離縁を申し出る事は 不遜と思われても仕方のない所であった。まして今は父の代ではない。長兄が上役や親族 にいらぬ気兼ねをするのではないか、おりつはその事も危ぶんでいるのだ。しかし兄のほ うはとっくにそんな心配を察していて、 「周りに何と思われてもよいではないか。今は、お前の先行きを考える方が大切だ。それ に、早坂には今さら文句を言う筋合いなどあるまい。」 「それは……。」 そうだが、という言葉を飲みこんで、おりつは黙った。ぽちゃん、と魚の跳ねた音がする。 「何を恐れている?」 「恐れてなど。」 「俺ばかりではない。母上も新之助も待っておるぞ。妻の郁代は、気のおけぬ女だから、 心配する事はない。」 娘の頃とは実家も様がわりしているが、藤本家の人びとは確かに、温和な性質の持ち主ば かりが集まっている。おりつのためらいは、出戻った後の居心地の事ではない。 東吾はさらに、 「これは、父上の遺言でもあるのだ。」 と、言った。先年病を得て亡くなった実父にまで、気を揉ませていた事を言われると、お りつは身のすくむ思いであった。またしばらくの間を置いて、ようやく、 「もう少し、お待ちくださいませぬか。」 と言うと、東吾は厳しい表情になった。 「りつ。何故だ。理由を申せ。」 「………。」 「待ってどうなる。みすみす、不幸な月日を重ねるだけではないか。」 「不幸。」 「不幸ではないか。今の暮らしに、何の喜び、何の生き甲斐がある。言っておくが、わが 家はお前を、病人の面倒を見るために嫁にやったのではないぞ。それどころかまるでてい のいい金づるではないか。」 「お兄様。」 東吾ははっとして我に返り、 「……いや、すまぬ。言わでもの事を。」 と、正直に詫びた。日頃の本音が口をついたのだろう。今度は語気を和らげて、 「それともお前、靖志郎どのと……その、離れがたいのか?」 おりつの肩がひく、と動いた。 「俺には、お前達が夫婦として心が通じ合っているとは思えんがな。」 妹が黙り込むと、東吾は池の淵に立って、小石を一つつま先で蹴り込み、その波紋を眺め ながら答えを待った。 「だからこそ、でございます。」 「何?」 「うまく、言えませんけれど……だからこそ、このままでは戻れないのです。」 いつの間にかおりつの眼からは涙が伝っている。 「こんな、寒々とした気持ちのまま、逃げ出しては……私この先、立ち直れないような気 がいたします。いつまでも悔いを残して、苦しいまま引きずってしまうような気がするの でございます。」 「そんな事はない。暖かな家で過ごせば、傷も癒えよう。」 「いいえ……」 「りつ。」 「初めから、終わりまで……ただ無駄な縁であったなどと思いたくはございませぬ。夫が ……一緒に暮らす値打ちのないほど……そこまで冷たい人だなどと……どこか、信じたく はございませぬ。せめてたった一度でも……あの人の心が……」 そこでおりつは息を吸いこんで、 「あの人の心が開くのを、見とうございます。」 言い切ってしまうと堪え兼ねたように、泣く動作が激しくなった。東吾は、肩を抱き締め てやっている。 「泣け。吐き出してしまえ。」 妹がこうして自分の胸に額をつけて泣くなどという光景は何年ぶりだろう。そういえば、 娘の盛りを迎えた頃から、これほどに近く体を寄せ合ったことなどあったろうか、と思い ながら、東吾はおりつの背中を「よしよし」というように軽く叩いている。 「お前は小さい頃から、泣き虫のくせに意地っ張りだった。ちっとも変わらんなあ。」 胸の辺りでかすかに、はい、という声が聞こえた。 「俺には、女の気持ちはよくわからん。だが要は、中途半端で放り出せぬというような事 だろう。」 こくり、と人妻の形に結われた頭がうなずいた。 「よし。……俺も、もう少し辛抱して待つ。お前は納得のゆくまで、靖志郎どのに心を尽 くしてみろ。明晰で名の通った男だが、それさえわからぬようなら仕方がない。その時は、 さっさと飛び出してしまえ。」 「はい。」 「りつ。何でも一人で我慢するなよ。辛い時には頼ってくれ。よいか。」 「はい……。はい。」 丸みを帯びた肩が、返事をしながら震えていた。 その後刻、料亭からの帰路。東吾は一人で歩きつつ、ふと暗い顔付きになっている。先日 勤めの帰りに祖父の順徳と二人で話をしたときの情景が思い浮かんだのだ。 「おじいさま。……それは、まことでございますか。」 順徳は医者らしく謹厳に、また祖父としての沈痛な面持ちを交えてでうなずいた。 「靖志郎どのの病は、治らぬ。医者も薬も無駄じゃ。」 ある程度予測したとはいえ、滅多に患者を投げ出さぬという評判の祖父の言葉に、東吾も動 揺したのは確かである。あとどのくらい、という質問に対して、 「わしの診立てでは、あと一年。長く見て、二年。」 と、順徳はここまではきっぱりと言ったあと、また祖父の顔に戻って、 「これ以上、おりつを悲しい目に合わせたくはないがのう。」 とつぶやいた。 「連れ戻してやった方がよい、と?」 「それは、藤本家のお考え次第じゃ。わしの口から、先のない病人ゆえ見放してよいとは、 申せぬ。」 当主である東吾の胸ひとつ、であるというのだ。 そこまでの回想から戻って、東吾は嘆息しつつ、 「……哀れだな。」 と独り言を漏らしながら家路を辿った。 その頃。兄と別れた後のおりつは、穴八幡宮の前の茶店の軒端に近いところに、席を決 めて座っていた。お初とここで待ち合わせをしている。 それとなく外を眺めながら、ぼんやりと考え事をしていたが、ある瞬間の視線を感じて 顔を上げた。 はっとした。 少し離れた茶店に、着流しで笠をかぶった男が座っている。おりつはどぎまぎとして、 すぐに目を逸らした。 歳三である。さりげない風にこちらを見ている。 (あの方が……なぜ?) おりつは瞳を上げられず、我にもなく胸が高鳴っているのを感じた。偶然だと思えば、 何気なく挨拶をしてもよさそうなものであるにも関わらず、何故かそうする考えが浮か ばなかった。うろたえている。試衛館の道場に向かう時にも、こんな強い鼓動は感じな かった。なぜ、という思いが強く支配している。 しばらくして、お初が店の西側から、小走りに現れた。息を切らせている。 「若奥様。お待たせして申し訳ございません。」 「ああ。……いえ、そんなには……」 おりつはけんめいに平静さをよそおって、 「弟さんには、会えましたか?」 「はい。お陰様で、風邪も治って……元気そうに働いておりました。」 「それはよかったこと。おじいさまも、先月風邪をこじらせたとおっしゃっていました から、ちょうど流行っていたのかもしれませんね。」 「まあ、医者の不養生でございますねえ。」 お初が奇しくも兄と同じ冗談口を言ったので、それを機におりつはほっと心がゆるんだ。 「……お買い物は?」 「はい。大奥様に言われたものは、ちゃんと。」 「そう。あなたも喉が乾いたでしょう。お茶を……。」 「いいえ。弟の店で、頂いてきたばかりでございますから。それより早く帰りませんと、 またお小言が大変でございますよ。」 そう言われて、おりつは無意識にこの場所に留まる時間を引き延ばすかのような事を していた自分に羞恥を覚えた。 「そうね。……では、参りましょうか。」 おりつは席を立ち、歳三の方には顔を向けず、さりげなく店を出た。もちろんお初は よその店の客には気づいていない。 女二人の姿が視界から遠ざかった時に長い鐘の音が鳴り、やがて、歳三も腰を上げた。 茶店の小女に声をかけ、 「済まん、ここに置くぞ。」 と代金を見せると小女が奥から出て来て、 「あら……お連れ様は、お見えにならなかったのでございますか?」 と、周囲を見渡した。そろそろ日が翳る頃で、人の姿は少ない。 「いいんだ。」 歳三は別にわずかな心付けを手渡すと、小女の「ありがとうございます」と言う声を後 に、閑散とした茶店を出た。 (五) へ続く |