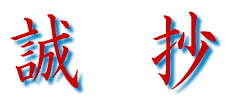 |
| 第 6 回 |
| 源さん、惚れられる |
 (一) おじさん侍 |
| 1 |
(四十を二つ三つ過ぎたところだろう。) と、女スリのお袖は思った。 慶応二年の春も盛りで、ここ京の町では清水寺へ参詣ついでの花見客が連日訪れている。 本来、京で最も桜が美しいのは嵐山だというが、やはりそれは、市中から出掛けるには一 日仕事になってしまう。清水で充分だ、と思う市民や観光の者も多いらしく、午後の門前 町は、仕舞いぎわの茶店がまだ少し、歩き飽いた客の姿をそこここにとどめていた。 といって、江戸から流れてきて日の浅いお袖が、清水からほど近い土産物屋の並ぶ往来 を日がなぶらぶらしているのは、何も高名な桜を見るためなどではない。花に浮かれ、行 楽に疲れて、ぽうっとそぞろ歩いている人びとをお客にすることのほうが目的なのである。 細い坂道をおりようとする時、人の注意はどうしても、足元にいく。少し酒気の入った 者も多い。この辺りの仕事は、お袖にとっては絶好の稼ぎ場所になっていた。 おかげで、その日自分に課した目標の金額はとうに手に入れ、いくつかの財布が空しく 京の水路に消えていったあとなのだが、西日が茜色を少し濃くしてきた時刻になって、お 袖はふと、そのお客を今日の仕事納めにしてみよう、と思いついたのである。 四十過ぎ、とお袖がみとめたその「お客」、つまりカモだが、その男は武士だった。だ が、「武士」というご立派な文字がおよそ似つかわしくないほど、どう見ても野暮ったい、 ぽっと出の田舎ざむらい、と表現したほうがぴったりの、冴えないご面相をしている。着 ているものは粗末ともいえないが、どことなく借り着のような、肩幅や袖丈がすっきりと 身に合っていないような、まあ、ひとことでいうと垢抜けないいでたちなのだ。 ───リャンコには、うっかり手エ出すなよ。 と、スリの技を仕込まれた当初、お頭の善平衛にはくどいほどに言われたものだが、お袖 はそれを承知で、仕掛けてみる気になっている。運試しでもあり、技試しでもあるだろう。 「リャンコ」とは二つのこと、つまり二本ざし、侍の俗語である。大して懐も豊かでない 上に、思いがけず手練の武芸を持っていたりして、スリを試みるには得のない相手だから、 というもっともな教えだった。その教訓にお袖があえて逆らってみる気になったのには理 由があるのだが、それは後で述べることにする。 お袖は白く繊細な指を軽く鳴らしてから、ごく何気ない足取りでその武士に近づいてい った。ほろ酔いの通行人たちを避けるかのように、少しそちらの方へ距離を縮めると、肩 先が触れるか触れないか、というまさに絶妙の間合いでそばをすり抜けている。 (ふっ。) お袖はそのまま、細い無人の小路の中に折れてゆき、天水桶に身を隠すようにして、左 の袂から藍色の財布を取り出した。 「おや、まあ。」 収穫のお宝を拝んだ時、お袖は意外な声を出した。 「あの、サンピン……こんなに持っていやがった。」 見かけによらず、中にはしめて五両に近い金が入っている。その印象の差に、お袖は面食 らったのだ。 いったん空にした財布を、今度は縞の帯の中へ深めに挟み込むと、お袖はもう一度表通 りに出て、西の方向を見た。 例の侍が、さっきとまるで同じ歩調で飄々と歩いてゆく背中が見える。 (くにから持ってきた、なけなしの虎の子だなんていうんじゃないだろうね。いやだよおじ さん。青くなって首でもくくるんじゃないよ。) そのやや丸い背中を見ていて、お袖は常にない好奇心を抱いた。仕事の後でお客に近づく などという、これも師匠の戒めにそむく形で、その侍のあとをつけてみる気になっている。 理由は今のところ、当のお袖にもわからない。 十分も歩いたろうか。ふと、その「おじさん」は、いずれ歴とした家中の武士であろう と見てとれる(こちらの方が風采がいいのだ)二人連れと、ばったり行き会った。「おお、」 という最初の声だけが聞き取れた。 「おじさん」はその二人連れの武士に、深ぶかとお辞儀をしている。その挨拶ぶりが、 どちらかというと野良で庄屋に出会った小作の百姓、とでもいったほうがいいような、純 朴そのものの頭の下げ方であった。二人のほうもつられて丁寧にお辞儀を返しているとこ ろを見ると、公のつきあいがあるらしい。 (上役かな。) 「おじさん」は何かにこにこと笑いながら、合計で六回も頭を下げて、やっと歩き出し た。その仕草を遠目に見ていて、お袖は何だか、気の毒になってきた。 (お人よしそのもの、って感じだねえ。) またさりげない距離を置いて後を歩きながら、 (どう見ても、自前で大金を持っているって顔じゃないもんね。仕事で京に上ってきて、お 役目がらみの金を持っていたんじゃないかしら。) と、お袖は想像をたくましくしている。江戸では芝居見物を欠かしたことのない女だから、 多少はその影響もあるだろう。 (このまま屋敷について……公金を無くした、ってんで、腹でも切らされるなんてことにな ったら……いやだ、寝覚めの悪い。) お袖は、とりあえず「おじさん」の行く先を見届けるつもりだった。 しかし、その「おじさん」は、数丁も歩いて繁華な町並みに着くと、ひょい、と一軒の 居酒屋の暖簾を分けて、中に入ってしまった。 「ありゃりゃ、」 お袖はぎょっとして足を速めると、あまり考えずに、同じ店の暖簾をくぐっていた。 |