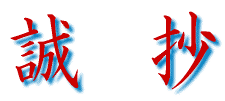 |
| 第 10 回 |
★緑色のマークをクリックすると、前後の場面にジャンプできます。
通常、読むときはスクロールしてください。
| この作品を、わが友 S、E、N の3人に贈る。 |
| ご来訪のお客様各位へ この「こぬか雨」に関しては、主人公の状況により、前後編の二部構成になっております。 (一)から(四)までの前編では、新選組はまったく登場することがありません。 また、この物語はひとつの「青春ドラマ」のようなもので、幕末の歴史に主眼を置いた、 というものでもありません。 そのため、他にも増して考証等に未熟、またご不満な点が多々あるかと思いますが、 あらかじめご了承いただける読者の方のみ、足を止めていただければ、と考えております。 平成11年7月 作者 千太夫 |
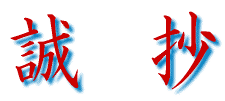 |
| 第 10 回 |
| こぬか雨 |
| (一) 雨 中 の 花 |
| 1 ▼ ─── その日、城下の剣術道場「誠武館」では、甲乙つけがたい、といわれる二人の若 こごおりかずのすけ 者が立ち会っていた。中背で細身の方が小郷和之助、長身でがっしりしているのが だいごうせいいちろう 大郷征一郎。共に十八才。 征一郎 うおおりゃあっ。 和之助 おうっ。 ─── 征一郎が振り下ろした面を交わして、びしりと胴を抜いたのは和之助である。 征一郎 うっ。 和之助 三本先取だ。今日は俺の勝ちだな。 征一郎 くそっ。 ─── 二人は、面を脱いで汗をぬぐっている。 征一郎 だいたい、お前は太刀筋が器用すぎる。それじゃ小手先の技で固まるぞ。 和之助 お前は力にまかせて大振りしすぎなんだ。 征一郎 何を。 ─── 道場の兄弟子たちは、笑いながら二人のかけあいを見ている。 門人1 まーた、やっとるぞ。あの二人。 門人2 放っておけ、あれは痴話喧嘩だ。 門人1 はっはっは。しかし、あれほど好対照の組み合わせも珍しい。 ─── 二人は稽古を終えて道場を出た。梅雨時で、いつ止むともしれない細かな雨が降 っている。 征一郎 あーあ、いやだいやだ。こう毎日、ジトジトと降り続けられたんでは、頭の中 までカビ臭くなる。 和之助 こぬか雨と言えよ。せめて風情がある。 征一郎 しゃれて言っても同じことだ。 ─── 門人たちがからかっている。 門人1 おお、また大小お揃いでお帰りか。 門人2 傘は二本もいるまい。相合い傘で仲良く行け。ははは…… ─── 征一郎と和之助は、舌打ちした。 征一郎 大小二本差し、とは誰が言いだしたんだっけな。 和之助 知らん。大郷と小郷……似ているというだけで、勝手につけられたのだ。 征一郎 お前とお対で呼ばれるとは、面白くない。 和之助 こっちこそだ。大小といったら、俺が脇差しということになるじゃないか。 征一郎 藩校の大森師範に言われたぞ。「道場の方はともかく、学問の方では小刀ばか り切れがいいようだ」とな。 和之助 ふ……。秋の考試には頑張れという意味だろう。 征一郎 この春はさんざんだったからなあ。 和之助 修了まであと一年半じゃないか。 征一郎 お前は修了後、義学館の師範代を狙ってるんだろう。 和之助 うまく行けばな。 征一郎 藩校の過程を終わってまで、学問など続けたいかねえ。俺はまっぴらだ。上級 組を終わったら書物などとはおさらばして、道場一本に打ち込みたいよ。 和之助 藩校の師範代になれれば……藩から手当てが出て、一人で食っていくあてが出 来る。 征一郎 ふむ。確かにお前は次男坊、俺は三男坊の部屋住みだからな。婿の口でも見つ からんことには、一生厄介者だ。 和之助 婿養子か。家付き娘に頭を下げて食い扶持をあてがってもらうなんて、ぞっと しないな。 征一郎 それが次男以下の宿命だ。 ─── 征一郎は、からっとしている。 征一郎 お前ならいくらでも、婿の口がかかるだろう。家中でも年頃の娘を持つ家では かなり早くから品定めしているらしいぞ。文武に才があり、容姿端麗、品行方 正の小郷和之助は候補の筆頭だな。 和之助 茶化すな。 征一郎 何の。妹の妙まで、「お嫁に行くなら和之助様がいい」と言っている。 和之助 妙さんは、まだ十二じゃないか。 征一郎 早い話でもない。女の方がませているからな。しかし、「和之助も妙も跡取り ではないから一緒にはなれん」と言ったら、むくれておった。ははは。 和之助 ………。 征一郎 いや待てよ。子のない家に夫婦養子という手もあるか。 和之助 折角だが、妙さんはごめんこうむりたいな。 征一郎 なぜだ。確かにお転婆だが、器量はまあまあだぞ。 和之助 お前の義弟になるのはまっぴらだ。 征一郎 そうか。 ─── 二人は、城下の武家屋敷が並ぶ中を歩いている。といっても、中級以下の屋敷が 並ぶ道である。板塀の内側で若い娘たちが数人、ささやき会っている。 娘1 お姉様、いらしたわ。 娘2 見せて。 娘3 私にも。 娘4 まあ、はしたないじゃありませんか。 ─── 娘たちは塀の隙間から、和之助と征一郎が通るのをのぞいている。 娘2 やっぱり小郷様ね。 娘1 あら、大郷様の方が素敵よ。男らしくて。 娘2 子供にわかるものですか。 娘3 しっ。 ─── 娘たちが目をこらしていると、征一郎は笑って、ぱっと手を上げた。 征一郎 やあ、お嬢様がた。のぞき見とはけっこうなご趣味ですな。 ─── 「きゃっ」という歓声が漏れた。 和之助 よせよ。 ─── 和之助は苦い顔で歩いている。 征一郎 気取ることはないじゃないか。あの娘たちは、茶の稽古に寄り集まっては誠武 館道場から帰る若い男の噂をするのが、ささやかな楽しみなのさ。 和之助 馬鹿馬鹿しい。 征一郎 ここいらの屋敷の娘たちなら、家柄も頃合いだ。将来、あのうちの誰かと一緒 になるかもしれんぜ。 和之助 あれじゃ、品がないな。 征一郎 可愛いもんじゃないか。この先の上士屋敷のご息女たちには手が届かないが。 ─── その角を折れると、家中でも高禄な家柄の、広壮な屋敷町になる。 和之助 無妙寺を通って帰るか。 征一郎 ああ、近道だからな。 ─── 二人は寺の境内を通った。雨天のことで参詣の者は見当たらない。 征一郎 こんな「こぬか雨」の日に、野暮な男の二人連れ。願わくば、見目麗しい美女 としっぽり歩きたいもんだ。 和之助 あてもないくせに。 征一郎 何を。お……噂をすれば。 和之助 え? 征一郎 美女発見、だ。 ─── 征一郎は、小走りで鐘楼に近づいていった。その下に、雨宿りをしていたらしい 武家娘が一人佇んでいる。 和之助 おい。 ─── 現代とは違い、若い武家の男女が気軽に声をかけあうということは、まずない。 しかし征一郎は構わず、大胆に娘に近づき、自分の傘を差し出した。 征一郎 よかったら、お使い下され。 薫乃 え? ─── 娘はとまどったように顔を上げている。 薫乃 ですが……あなた様は、いかがなさいます。 征一郎 何、連れがもう一本持っています。 ─── 征一郎が娘と話をしているうちに追いついて来た和之助は、振り返った娘の思い がけぬ美しさに一瞬、呆然となった。艶やかな黒髪が雨に濡れて光っている。派手 ではないが品格のある身なりに、先程の娘たちと違う上士の家柄が見てとれた。 薫乃 男の方お二人で、一つ傘では……肩が濡れておしまいになりませぬか。 征一郎 多少濡れたって構いやしませんよ。我々男は、はなから傘などなくてもよいの です。本当はあんな奴よりあなたと寄り添って歩きたいところだが、そうもい かんでしょう。 薫乃 ま。 ─── 娘は小さく笑った。 征一郎 あなたの方こそ、冷えて風邪でもひいたらいけない。遠慮なく、持ってお行き なさい。 薫乃 ……ありがとうございます。それではお言葉に甘えて、お借りいたします。 ─── 娘は慎ましく二人に頭を下げると、傘をさして立ち去った。 2 ▼ ▲ 征一郎 やった。あの人と話をしたぞ。 和之助 今のは。 征一郎 御番頭の木暮市右衛門殿のご息女で、薫乃どのだ。 和之助 ゆきの…… 征一郎 風薫るの薫に乃と書いて、「ゆきの」と読む。当年十九だ。 和之助 詳しいな。 征一郎 知らぬ方がどうかしている。家中でも第一といわれた美人だぞ。 和之助 ふうん。……御番頭の娘が、なぜ一人で寺などにいる。 征一郎 さあ、墓参りだろ。 和之助 ここは、木暮家の菩提寺か? 征一郎 いや……ああ、そうか。 和之助 何だ。 征一郎 おそらく、須美という人の墓があるのだろう。 和之助 須美? 征一郎 おぬしは学問は出来るが、本当に世情にうといな。須美というのは、郡奉行の 島田重太夫殿の娘だった人だ。先年、確か十七で死んだ。 和之助 若いな。 征一郎 表向きは病死ということになっているが、実は自害したという話だぜ。 和之助 自害? 征一郎 ああ。 和之助 その若さで、なぜだ。 征一郎 しかも、あの薫乃どのが死なせたというな。 和之助 あの人が? 征一郎 ああ。かつて加納道場にその人ありといわれた、西条源吾の名前くらいは、知 っているだろう。 和之助 知っている。江戸詰めになって城下を離れたが、その以前は藩内に敵なしとい われた男だろう。 征一郎 そうだ。須美どのはその西条のいいなづけで、薫乃どのは西条のひそかな思い 人だったということさ。しかも、女二人は幼なじみの親友だった。 和之助 あの人が、友だちのいいなづけを奪ったというのか。 征一郎 違う。間違いを起こした、というほどの事実はないらしい。 和之助 では、なぜ。 征一郎 西条と島田、両家の婚約はめでたくあい整ったものの、当の西条源吾は薫乃ど のに惚れていたらしい。江戸行きの前に、祝言の日取りを急ごうということに なっても、本人がなかなかうんと言わず逃げ回るというふうだったそうだ。 和之助 それで。 征一郎 ところが須美どのの方は、家が決めた相手というだけでなく、西条を本気で慕 っていて、嫁に行く日を心待ちにしていたらしい。もともとは娘が、あの方な らぜひに、と島田奉行を口説いて決まった縁組だというからな。それなのに、 好いた男から嫌われていると思って悩んだ。もちろん、仲のいい薫乃どのにも 相談した。 和之助 ………。 征一郎 ところが、どういう経緯かは知らんが、西条が実はその薫乃どのを思っている ということが須美どのにわかってしまった。その結果、こう、さ。 ─── と、征一郎は喉を突く真似をした。 和之助 ほう……。 征一郎 死んだ娘も哀れだが、薫乃どのも気の毒だぞ。島田の家族は動転して、焼香に 来た薫乃どのをなじったそうだ。おかげであっという間に噂が広まり、他人の いいなづけを誘惑した不道徳な娘と呼ばれて、自分の縁談まで壊れたそうだか らな。以来、島田と木暮の家は犬猿の仲になっているというし、西条などは両 方の家から仇敵扱いだそうだ。 和之助 短慮だな。 征一郎 誰が。 和之助 島田の娘だ。黙って嫁いでしまえば、何事もなくすんだはずではないか。一時 の激情のおかげで、三つの家が大迷惑をこうむったことになる。 征一郎 そう理屈通りにはいかんだろう。それも結構辛いぜ。 和之助 何がだ。自分は好いた男と添えるのだから本望だろう。 征一郎 じゃあ聞くが、お前は自分のいいなづけが俺に惚れている、と知っても平気で 妻に出来るか。 和之助 ………。 征一郎 俺はいやだな。自分の女房になる女が小郷和之助を慕っているなどと知ったら 悔しくて眠れないだろう。俺の腕の中で、お前の顔を瞼に浮かべながら抱かれ ているなどと思ったら、興ざめもいいところだ。 和之助 馬鹿。(赤くなる) 征一郎 夫婦になる、ということは毎日一緒に暮らすということだ。当然、夜のことも するわけだろう。 和之助 ………。 征一郎 まあ、男女のことははた目からはわからん。西条の一方的な片恋だった、とは 限らんからな。もし、薫乃どのも西条を慕っていたのだとしたら……須美どの はよけいに辛かったかもしれんさ。 和之助 まさか。 征一郎 むろん、例えそうだとしても須美どのの前では隠しただろうが、仲のいい女同 志ならわかってしまうだろう。西条源吾は、薫乃どのが恋心を抱いたとしても 不思議がないほどのいい男だというぞ。剣の達人だというだけでなく、頭は明 晰で気性も爽やかだ。風貌も清々しく、殿の覚えもめでたいという……まあ、 難のないのが難点だ、というほどだからな。 和之助 ………。 征一郎 そういう奴ほど周囲のやっかみを受けやすい、ということだ。和之助、お前も 気をつけろよ。 和之助 俺などは、噂の種にもなるまい。 征一郎 本人がそう思ってるだけさ。上級組の首席をめぐって、戸田や伊沢などは敵意 むき出しじゃないか。 和之助 自分がやるだけのことをやるまでさ。 征一郎 は、そういう澄ましかえったところが憎たらしい。 ─── その時、若い寺僧が来て、 僧 恐れ入りますが……そろそろ、暮六つの鐘をつきまする。 征一郎 おお、もうそんな時刻か。 和之助 すまん。征一郎、行こう。 ─── 和之助は傘をさした。征一郎は行きかけて、ふと僧に、 征一郎 ちょっと尋ねるが、この寺には、郡奉行の島田家の墓所がおありか。 僧 島田様……はい、ござります。 征一郎 では、数年前に亡くなった須美という人の墓も? 僧 ……ござりますが。 征一郎 そうか。いや、お邪魔をした。 ─── 和之助はすでに歩きはじめている。 和之助 おい、早くせんと置いていくぞ。 征一郎 待ってくれ、濡れ鼠になる。 ─── 征一郎はひょい、と傘の中に入ってきた。 征一郎 確かに狭いな。 和之助 お前が、よけいなお節介をするからだ。 征一郎 美人の難儀を見過ごしておけるか。 和之助 あの、薫乃という人は……わざと傘を持たずに来たのかもしれんぞ。 征一郎 なぜだ。 和之助 なんとなく、さ。 ─── 和之助には、薫乃が亡き友への償いに墓参に来ていたというのが本当ならば、自 分の身をいたわることなく雨に打たれて帰るのがふさわしい、と考えたのかもしれ ず、またそういう気遣いが、あの美しい物静かな娘には似合っているように思われ た。明るい征一郎にはわかるまい、とも思った。 3 ▼ ▲ ─── 小郷家、和之助の自室。外はまだ雨が降っている。 母 よく降りますこと。 ─── 母が、勉強中の和之助に茶を運んできた。 母 喜んでいるのは、庭の紫陽花くらいなものですね。道之助が、おんもで遊べな いとぐずって困ります。 和之助 さっき、この部屋まで走ってきました。 母 おや、まあ。 和之助 義姉上に叱られて、連れて行かれましたが。 母 和之助は、本の虫ですからね。叔父様の邪魔になるからと、追い出されたので しょう。 和之助 本の虫……。 母 悠一郎が、あれは学者になるつもりかな、と首をかしげておりましたよ。 和之助 学者になりたいわけではありませんが……うまく、次期師範代になる推薦がと れればわが家のためにもなるでしょう。 母 おや、職を得るための学問ですか。 和之助 婿入り先探しにやっきにならずとも済みますよ。 母 そなたなら婿に欲しいという人はもう、ちらほらとおりますよ。 和之助 まさか……もう決めようとなさっているのではないでしょうね。 母 ほほほ。まだ、あせらずともよいでしょう。行き先が決まって、修行の手を抜 いたりしては困りますからね。 和之助 ………。 母 まあ、女と違ってもう少し年齢がいってからでも……。縁談は一生のことです からね。 和之助 ………。母上は……。 母 え? 和之助 なぜ、父上のところへ嫁いでこられたのですか。 母 何です、改まって。(笑う) 和之助 何となく……男の子二人を抱えたやもめのところへ後妻に入るなどと、勇気が いったのではないかな、と思って……。 母 まあ。生意気になったものですね。 和之助 すみません。 母 そうねえ……(首をかしげて)父上がいいお方だと思えたことと、二人の男の 子が可愛らしかったから、かしら。 和之助 可愛らしい。 母 ええ。特に、下の子が。(くすくす笑って)八つにもなって、まだお袋様のお 乳が恋しいような、寂しげな顔をしていましたからね。 和之助 私が? 母 ええ。今と違って、それはそれは……いたいけで愛らしいお子でしたよ。私は 一度嫁いで子供が出来なかったので、この子のためなら、と思った時から迷い はなくなりました。 和之助 ………。 母 でもおかげで今は、八重という新しい娘も出来たし、道之助が生まれてからは 「ばばさま」とまで呼ばれるようになって、幸せだと思っておりますよ。 和之助 母上。(頭を下げる)ありがとうございます。 母 何です。 和之助 兄上と私を育てていただいて……この家がもっているのは、母上のお力です。 母 いやに持ち上げること。その言葉は、父上に言っておいて下さいな。 ─── 母は笑いながら行ってしまった。 和之助 ………。 ─── 和之助には、生みの母の記憶がない。その人は和之助が四つの時、離縁されてこ の家を去っている。生前の姑、つまり和之助の祖母と折り合いが悪かったためだと か、病がちで子育てに疲れたからだとか聞いているが、真相はよくわからない。色 白で美しい人だったらしい。 和之助 (確か、雨の日だったな。) ─── 母が家を出される日の記憶だけはぼんやりとある。和之助が後追いするのを、兄 と祖母が肩を押さえつけて止めた。ほっそりとした母親の姿が、傘の下で一度も振 り向かずに雨中に消えていくのを和之助は見た。 和之助 (捨てられた、と思った。) ─── その後四年ほどして父に後妻がきた。今度の母は器量は人並みだったが、ごく穏 やかな明るい女性で、一家にとっては救いの神だったといえるだろう。 ─── 藩校の庭。 征一郎 三つ子の魂百まで、というからな。お前がどことなくさめているのは、幼い時 の記憶が影を落としているんだろう。 和之助 知ったふうなことを言うな。俺はそんなに女々しくはない。 征一郎 その、生みの母という人には会ってないんだろう。 和之助 ああ。離別されてから、他藩の家に再縁したらしい。 征一郎 美人だったそうだな。 和之助 さあ……後ろ姿しか覚えていないからな。 征一郎 薄幸の佳人、か。木暮のご息女みたいじゃないか。 和之助 ………。 ─── その日の講義が終わった。征一郎は居残りの補習組に入っている。 征一郎 お前がうらやましい。 和之助 頑張れ。考試に落第して、俺の下級になりたくはなかろう。 征一郎 帳面を置いていってくれ。写す。 和之助 役に立つかな。 ─── 和之助はにやっと笑って、教室を出た。廊下で師範の大森金三郎に呼び止められ た。 大森 ああ、小郷。ちょっと話がある。 和之助 はい。 4 ▼ ▲ ─── 別室に呼ばれた和之助。 大森 この度の漢学、国学、算術の考試……おぬしの成績はみごとなものだったな。 頭取もほめておられた。 和之助 は……ありがとうございます。 大森 秋の進級まで、大分暇になるだろう。 和之助 ええ、おかげさまで。 大森 そこで、おぬしに頼みがある。 和之助 は。 大森 御番頭の木暮市右衛門様を知っているか。 和之助 木暮様……はい、お名前だけは。 ─── 和之助はちらっと考えた。あの薫乃の父である。 大森 その木暮様の末子で、朋之進どのという男の子がある。当年、九つだ。 和之助 はい。 大森 本来なら、この義学館の初等組に通う年齢になっているのだが、気の毒に足の 怪我をしてな。もう長いこと、外へ出て歩けぬようになっている。 和之助 は。 大森 そこでだな。おぬしがあちらのお宅へ通って、朋之進どのの学問の手ほどきを してほしい。 和之助 私が? 大森 そうだ。藩校の上級組の中から、誰か優秀なものを紹介してくれ、と頼まれて な。 和之助 私には、まだ人を教えることなど…… 大森 何、九つの子の素読の教授だ。おぬしなら難なくつとまる。それに、体の勝手 がきかず家の者だけを相手にしているのは可哀相だと言ってな。学業の合間に 遊び相手になってやってほしい、というのだ。それには年若い者のほうがよい だろう。 和之助 ………。 大森 子供のお守りといえば大郷征一郎などがうってつけだろうが、あいにくと奴は 今、人の学問どころではない。ははは。 和之助 はあ。 大森 どうだ。おぬしの将来のためにも、代々の名家である木暮様と顔つなぎをして おくのは、悪い話ではないぞ。 和之助 私のためというのでしたら、お断りいたします。 大森 ほう。 和之助 しかし、その……気の毒なお子のためにいささかお役に立つということでした ら、お引き受けいたします。 大森 堅物だな。(笑う)しかし、だからこそ安心しておぬしを紹介できる。 ─── 和之助は木暮家の客間に座っている。 和之助 (さすがに、藩祖以来の重臣だけあって……身分の違う家だな。) ─── 屋敷も庭も広い。案内されなければ迷子になるだろう。 和之助 (しばらくの間のことだ。頼まれて来たのだから、卑屈になることはない。) ─── と、気を取り直した時、障子の向こうで女の声がした。 薫乃 失礼いたします。 ─── 茶菓を運んできた娘を見て、和之助はどきっとした。まさか、この家の令嬢が自 ら出てくるとは思わなかったのである。 薫乃 まあ。あなた様は…… 和之助 小郷和之助です。(頭を下げる) 薫乃 ご無礼いたしました。朋之進の姉で、薫乃と申します。 和之助 は。 薫乃 どうぞ。 ─── 美しい手で差し出された茶を、和之助は緊張して飲んだ。 和之助 確か、先日の雨の日に……。 薫乃 はい。お連れ様とご一緒のところを、お目に掛かりました。 和之助 大郷が、あなたが傘を返しに来られた日に、藩校に残ってお会いできなかった と残念がっておりました。 薫乃 ……さようでございますか。 和之助 ご自分で返しに行かれるとは……やはり、あの寺へはお忍びでいらしたのです か。 薫乃 無妙寺に? 和之助 ええ。 薫乃 別に……通りかかって、雨をやり過ごしていただけですわ。 和之助 そうですか。 薫乃 こぬか雨…… 和之助 え? 薫乃 こぬか雨が、あの鐘楼の前の紫陽花を濡らして美しかったのです。それを、ぼ んやりと眺めておりました。 和之助 ………。 薫乃 おしゃべりが過ぎました。小郷様、弟のことよろしくお願いいたします。 ─── 薫乃は一礼して部屋を去った。かすかに、花の香りが残った。 ─── 梅雨晴れの日。和之助と征一郎は、例によって無妙寺の境内を通り抜けている。 征一郎 大体、お前は水臭い。いや、冷たい。 和之助 何が。 征一郎 木暮の家に通うようになったこと、俺に隠していたろう。 和之助 また、お前にやいやい言われるのが面倒だっただけだ。 征一郎 嘘をつけ。薫乃どのの弟と聞いて、二つ返事で引き受けたんだろう。 和之助 怒るぞ。 征一郎 ははは。で、噂のご息女にはもう、お目にかかったか。 和之助 同じ家の中にいるんだから……時々、会釈ぐらいはするが。 征一郎 ふうん。その、朋之進という子はどうなのだ。 和之助 いい子だ。足が悪いというので暗い雰囲気かと思っていたが、ちっともひねた ところがない。多少ひ弱だが、素直でいい子だ。 征一郎 ほう。お前が子供をほめるとは珍しいな。 和之助 それに……あの家に出入りしてみて思ったことだが、世間の噂などというのは あてにならんな。 征一郎 何が。 和之助 藩の重役といっても木暮家はごく清廉な家柄だ。ああいう家風で育った娘が、 友人の夫になると決まった男に妙な誘いをかけたりするとは思えん。 征一郎 なるほど。 和之助 薫乃どのが横恋慕してうんぬん、というのは中傷だな。 征一郎 妙に肩入れするな。さては、惚れたか。 和之助 な……。 征一郎 やめておけ。いくらなんでも御番頭の次女とでは、話にならんぞ。 和之助 ばかばかしい。 征一郎 いや。家中の娘たちは、小郷和之助が木暮家に出入りするようになったと聞い て騒いでいる。堅物の小郷が薫乃どのに籠絡されるのではと、心中おだやかな らずといったところらしいぜ。 和之助 また……そういう事を言うと連れていかんぞ。 征一郎 何が。 和之助 朋之進どのが、今度は俺の友人も連れて来てくれぬか、と言っている。 征一郎 本当か。 和之助 もちろん、遊び相手のほうだがな。行くか。 征一郎 おお、行く行く。やはり、持つべきものは友だちだな。 和之助 ちゃっかりしてるな。 次回 (二)へつづく 5 ▲ |