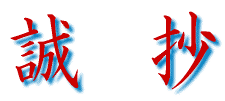 |
| 第 11 回 |
★緑色のマークをクリックすると、前後の場面にジャンプできます。
通常、読むときはスクロールしてください。
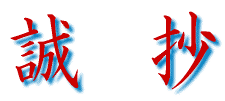 |
| 第 11 回 |
| こぬか雨 |
| (二) 少 年 |
| 1 ▼ ─── 九才の朋之進少年は、ひょうきん者の征一郎の来訪をことのほか喜んだ。 朋之進 はは、あははは……。 征一郎 よろしいかな、行きますぞ。鼻、鼻鼻鼻……目。 ─── 相手が最後に言ったところと、同じ場所を指さしたら負けという遊びである。 朋之進 ふふ。目、目目目……口。 征一郎 口口口口……ヘソっ。 朋之進 ずるい。 ─── 朋之進は、体を折り曲げて笑っている。 征一郎 勝負に奇策はつきもの。油断大敵ですな。 朋之進 おへそも入るとは、聞いておりませぬ。 征一郎 なんの。ヘソヘソヘソヘソ……足のうら! 和之助 おい。 ─── ひょい、と片足を上げた征一郎を見て、和之助はあわてた。朋之進は足が不自由 である。 征一郎 気の使いすぎだ。この足は治る。なあ、朋之進どの。 朋之進 本当? 征一郎 ああ。しっかりと稽古して鍛えれば、また歩けるようになりますとも。後生大 事に、部屋の中で撫でさすっているから治らんのです。 和之助 征一郎。 朋之進 ……そうかな。 征一郎 私の祖父などは、七十を越えてから腰をいためて寝込みましたが……毎日杖を つきつき、あぶら汗をかいて歩く稽古をしておりましたぞ。あの頑固じじいの 気力には驚いた。 和之助 ………。 朋之進 それで、おじいさまはどうなったの。 征一郎 ぴんぴんして、加瀬川へ釣りに出掛けておりますよ。 朋之進 すごいな。 征一郎 朋之進どのは、まだ骨が柔らかい。今に、我々と同じように走り回れるように なりますよ。じいさまに負けてはなりません。 朋之進 うん。 ─── 和之助は、感心して征一郎の顔を見た。 和之助 (根っから、いい奴なのだ。大郷のご隠居は、確かに晩年はその通りの人だっ たが……去年の春に亡くなったではないか。) ─── 死んだと言えば、少年ががっかりすると思ったのだろう。 征一郎 大体こんな天気のいい日に、子供が部屋のなかで遊ぶということからして間違 っている。お天道様に笑われますよ。 朋之進 うん。外に……出たい。 征一郎 よっしゃ、その意気。 ─── 征一郎はぱっと立って、朋之進の体をおぶった。和之助は気が気ではない。 征一郎 藤吉郎、これ猿。履物を揃えぬか。 ─── 和之助は苦笑して、縁側から降りる沓脱ぎ石の上に草履を揃えてやっている。 和之助 俺が藤吉郎で、お前は信長公か。 征一郎 そうだ。草履取りの分際で、頭が高い。控えよ。 朋之進 でも、天下を取ったのは藤吉郎だ。太閤秀吉だもの。 征一郎 うう……本能寺を忘れていた。 ─── 征一郎は顔をしかめて沓脱ぎの上に立った。背中の朋之進はちょっとおびえて、 朋之進 この石で、怪我をしたんだ。 ─── と、征一郎にしがみついた。 征一郎 そうか。 ─── 征一郎は、少年の細い体をぎゅっと力をこめて支えてやり、 征一郎 大事な若様に痛い思いをさせるとは、悪い石め、こいつめ、こいつめっ。 ─── と、石を蹴った。 征一郎 若君。石は拙者がこらしめておきました。こやつも謝っておりますゆえ、勘弁 しておやりなされ。 朋之進 うん。許す。 ─── 征一郎は朋之進をおぶったまま、広い庭を駆け回っている。歓声が響いた。 薫乃 にぎやかですね。 ─── 薫乃が、真っ赤に熟れた西瓜を切って運んできた。 和之助 あ……。(一礼する) 薫乃 ひと休みされてはいかがです。 征一郎 これはこれは……ご息女自らかたじけない。いやーっ、うまそうだ。 ─── 征一郎と朋之進は、汗びっしょりになっている。西瓜をかぶりつくと、 征一郎 ふむ。運ぶ人がいいと、西瓜まで甘くなるらしいですな。 薫乃 面白いかた……大郷様は。 ─── 薫乃は軽く声を立てて笑った。和之助はその笑顔を見てちくりと胸が痛んだ。 ─── 薫乃は、父の書斎にも茶を運んでいる。 木暮 朋之進はずいぶんと楽しそうだな。ここまで声が聞こえた。 薫乃 ええ。 木暮 小郷はよく出来た青年だが、大郷というのも面白い男らしい。 薫乃 はい。お二人とも……まだお若くて、まっすぐでいらっしゃいます。何物にも 染まらず、まぶしいような……。 木暮 西条源吾の若い頃に似ているか。 薫乃 ………。 木暮 すまぬ。源吾をそちの夫にしてやれなかったのは、わしの不覚だった。 薫乃 いいえ。 木暮 あの頃の源吾は、単純明快な剣術馬鹿かと思っていた。わしに、見る目がなか ったな。 薫乃 ………。 木暮 派手好みの島田が娘を嫁がせることにしたと言っても……源吾の剣客としての 高名ぶりを気に入ったのだろう、と……さほどにも思わなかったが、今となっ ては悔やまれる。江戸詰めになって以降のあの男の敏腕を見抜いておれば、是 が非でもそなたを行かせるのであった。 薫乃 父上。 木暮 年をとると、繰り言が多くなっていかんな。 薫乃 ……あの方が、藩のまつりごとに打ち込むようになられたのは、あの事件があ ったからこそではございますまいか。 木暮 ふむ。 薫乃 であれば……須美様の死もほんの少し、報われます。 木暮 藩のためには、か。しかし、当のそなたたちにとっては哀れだ。 薫乃 私は……これでいいと思っております。 木暮 本心かな。 薫乃 ご縁があって、先に島田様のお話が決まられた以上は……私も西条様も身勝手 でございました。 木暮 好きだ、と思うただけで別段過ちをおかしたわけでもあるまいに、何の悪いこ とがある。わしや母上にも、秘めたる初恋の一つや二つはあったぞ。 薫乃 ………。(くすっと笑う) 木暮 若い頃はいろいろとある。いや、そなたはまだ若いが。 薫乃 何も知らなかったあの頃ほどではございませぬ。 木暮 若い者には先が見えぬ。見えぬからこそ面白いともいえるが……時にはそれゆ えに、物の道理をわきまえずに走り出すことがある。 薫乃 ………。 木暮 開港以来、朝廷を持ち上げる風潮が高まっておるが、そもそもわが藩の成り立 ちは徳川家あってこそのことだ。父祖代々、生を受けてこの世に永らえること のできた恩顧は将軍家にあって、天子様にはない。そこのところが、新しがり の連中にはわかっておらぬ。 薫乃 はい。 木暮 わしらは、天朝を敬うことが悪いと言っているわけではない。尊皇の志は、広 く普遍のものであってよい。しかし、わが殿が将軍家を主と仰ぐ以上、家臣一 同は殿のお心に従うべきであり、その中で最善の策を用いるべきである。古い と言われようと、それがそもそも武家の忠義ではないか。 薫乃 はい。 木暮 は、は、は。また繰り言だな。……そろそろ、出掛ける刻限ではないのか? 薫乃 はい。 木暮 小郷を頼んでから、そなたの外出が容易になったな。 薫乃 ええ。それに、朋之進が明るくなりました。そのことも助かっております。 木暮 では……気をつけて行けよ。 薫乃 はい。行ってまいります。 2 ▼ ▲ ─── 和之助と征一郎、木暮家からの帰り道。 征一郎 お前の言った通りだ。上品だが気どりがなくていい家だな。 和之助 ああ。 征一郎 最初、御番頭に会わされた時はさすがに緊張したが。 和之助 ゆったりしたお人だろう。 征一郎 うむ。しかし次の家老と評されるだけあって、なかなかの人物だな。俺たちの ような若輩まで、息子の客人としてきちんと遇してくれた。 和之助 かといって、晩飯まで食っていこうというのは行き過ぎだ。 征一郎 食って行けというもの、遠慮せずに食ってくりゃよかったんだ。あーあ、腹が 減った。 和之助 西瓜を食ったろう。しかも、一人であんなに。 ─── 征一郎は、西瓜を「おかわり」までしたのである。 征一郎 水菓子じゃないか。しかし、薫乃どのが自分で持ってくるとは思わなかった。 あの様子からすると、初めてではないだろう、ん? 和之助 ……時々、だ。 征一郎 (笑う)会釈だけだなんて言ってたくせに。しかし、ああいう人が嫁にも行か ず、実家でひっそりと暮らしているなんてのは、いかにも勿体ないなあ。 和之助 ………。 征一郎 来年は二十だろう。女も二十の声を聞くと、いかに器量良しでも縁談の幅が、 ぐっとせばまるというぜ。 和之助 別に、無理に嫁ぐこともないさ。 征一郎 そうか。お前の楽しみが減るものな。 和之助 馬鹿。 ─── 藩校。同級の金井修平という若者が和之助に話しかけてくる。 金井 小郷。お前、木暮様のお宅へご子息の手習い相手に通っているんだって。 和之助 ああ。 金井 ふうん。そんなことをしていて、大丈夫なのか。来年の考試。 和之助 時間は取られるが……まあ、乗り掛かった船だ。 金井 今度、国学の山岡塾へ行ってみないか。 和之助 山岡義左衛門どののお宅か。 金井 ああ。山岡先生なら、藩校の補習も快くみて下さる。仲間も多いし、一人で黙 々とやるよりためになるかもしれんぜ。 和之助 ありがとう。……考えておく。 ─── 木暮家。朋之進の部屋。 朋之進 今日は、大郷どのは? 和之助 征一郎は……藩校の補習があって、居残りです。 朋之進 小郷先生は、いいのですか。 和之助 私は、ひと足先に今年の課程を終えましたので、しばらく時間があきます。 朋之進 しばらくとは、どのくらい? 和之助 ………。 朋之進 ずっと教えに来て下さるのでしょう。 和之助 ああ……それは、出来る限り。 朋之進 よかった。 和之助 しかしこの分でいくと、同年の組にじき追いつきますよ。少し歩けるようにな れば義学館にも通えるでしょうから、私がお教えせずともすむようになりまし ょう。 朋之進 私は、ずっと小郷先生でもいいな。 和之助 それは、いけません。 朋之進 なぜ? 和之助 藩校には、学問のために行くというだけではありません。さまざまな先生や先 輩、それに、友達が出来る。そういう人の間でもまれていく中で身につくもの もたくさんあります。 朋之進 友達……。 和之助 私は、あまり人付き合いの得意なほうではないが、それでも……友達というも のはいいものですよ。そこでは家柄や身分に関わりなく、呼び捨てにしあった り冗談を言ったり……もちろん、時には喧嘩もする。その時には、誰も木暮の 若様だといって遠慮はしてくれません。また、家柄が目当てで近づいて来るよ うなのはろくな奴ではない。一人でも二人でも、本音でつきあえるような友達 を見つけることが大事です。 朋之進 ………。 ─── 和之助は、ふと自分の演説に照れたように咳払いをした。 和之助 ……先程の続きを読みましょうか。 朋之進 小郷先生。質問します。 和之助 何ですか。 朋之進 友達には、年も関わりないですか。 和之助 まあ……そうでしょう。 朋之進 では、私と先生も友達になれますか。 和之助 ………。 朋之進 先生はお師匠様だから、駄目ですか。 和之助 いや。朋之進どのさえよろしければ……友達になりましょう。 朋之進 大郷どのも? 和之助 向こうはとっくにそのつもりですよ。 朋之進 よかった。 ─── 朋之進はにこっと笑っている。 ─── 後日、木暮家の庭で、和之助は思わず胸のつまる光景を見た。朋之進が、姉の薫 乃にかたわらをささえられて、よろよろと歩く練習をしている。 朋之進 (汗をぬぐって)ああ、見つかっちゃった。内緒にしていたのに。 和之助 ………。 薫乃 朋之進。先生がおみえですから、もう中に入りましょう。 朋之進 はい。 薫乃 (和之助に)着替えをさせますので、少しお待ちを…… 和之助 はい。 ─── 朋之進が家の者たちに抱えられて行くと、薫乃は微笑した。 薫乃 驚かれました? 和之助 ええ。 薫乃 私もです。今までは足が痛いといやがっておりましたのに……急に、「どうし ても他の子供たちと同じように義学館へ行くのだ」と申しまして。 和之助 ……そう、ですか。 ─── 薫乃の額にも、汗が光っている。 薫乃 あの子も、このまま努力すれば藩校に通えるようになるでしょうか。 和之助 なりますとも。……きっと。 ─── 和之助は、柄にもなく目がうるんでくるのを感じた。 3 ▼ ▲ ─── 征一郎はその話を聞いて喜んだ。 征一郎 それはいい。やはり、おぬしの教えがよかったんだな。 和之助 いや。きっかけはお前の話だろう。近頃では加瀬川に釣りに行きたい、と言っ て家族を困らせているそうだぞ。 征一郎 けっこうじゃないか。なんなら、俺がおぶっていってやるさ。 和之助 ぴんぴんしているはずのじいさまは、どうするんだ。 征一郎 ううーん。まさか、墓から掘り出して来て会わせるわけにもいくまい。はっは っは。 ─── 征一郎は愉快そうに笑っている。 ─── 新年である。城下は残雪が積もっている。藩校では和之助たちが最上級組に進級 した。 大森 おぬし達も、本年中には当義学館を修了する。多くの者はそこで学問を一段落 して将来のお役目に備えるわけだが……この最上級組の中から数名の者は、本 校の初等組を教える師範代となり、また、そのうち特に認められた者は江戸、 京、大坂、長崎……と、藩命により遊学を許されるということもある。そのつ もりで、心して最後の学業に取り組むように。 征一郎 (小声で)は、俺には縁のない話だな。 和之助 しっ。 大森 その代わり、最終の考試において全課程に合格せざる者は、容赦なく落第させ ることも周知の通りである。もう一年でも二年でも通ってもらうぞ。 ─── 征一郎は、うひゃっ、と首をすくめた。 大森 かねて聞き及ぶ通り、かの黒船来航以来、世情は大いに不安である。わが藩も 多分に漏れず苦しい財政の中、十年余の歳月をかけて子弟の教育に力を注いで おられるご主君、父兄、ひいては城下の民びとの恩を、決しておろそかに思う べきではない。義学館に学んだおぬし達一人一人が立派に成人して、お国のた めに身をつくすことこそ、報恩、忠孝の道と心得るべし。そもそも…… ─── 征一郎はあくびをかみ殺している。 ─── 学生たちは、その日の講義が終わってざわざわと藩校の門を出ている。 征一郎 いやいや、今日の大森師範の演説は、長かったな。 和之助 まあ、仰せごもっともだ。 征一郎 ああは言われても……俺は読み書き算盤、一通りできりゃ充分だ。机の前にか じりつくより、道場で体を動かしているほうが性に合っている。遊学というな ら、江戸の撃剣道場にでも入ってみたいよ。 和之助 しかし近頃は、剣術だけでは遊学の許可がおりぬらしい。兵学、砲術、軍艦操 練術など、いずれかの学術をあわせて学ぶことが必要だそうだ。 征一郎 戦争の学問か。まっぴらだな。 和之助 なぜだ。武士はもともと戦のために禄をはんでいる。武芸だってその一端だろ う。 征一郎 俺が剣で強くなりたいというのは、人を殺す技を磨いているわけじゃない。 和之助 剣は、もともと相手を倒す目的のものじゃないか。 征一郎 ちょっと違うな。うまく言えんが…… ─── 征一郎の頭の中には、後世でいうスポーツマンシップのようなものがある。 征一郎 昨日までできなかったことが、ある日ふと出来るようになる。見えなかったも のが見え、なかった力が心身についてくるのを感じる。そういう……自分のた めの楽しみかな。 和之助 楽しみ?剣が、か。 征一郎 そう。俺は、そういう楽しみを子供らに教えるようなことなら、道場に残って やってみたいような気がする。おぬしは藩校で学問を教え、俺が武術を教え、 ……なかなか、面白いじゃないか。 和之助 ふむ。 征一郎 今日の師範の話の中で、一つだけ合点がいったことがあったな。 和之助 一つだけ?(苦笑する) 征一郎 ああ。藩校の教授たちは、やはりお前を師範代推薦の候補にあげている、とい うことさ。おそらく、朋之進どのの手習い師匠を勧めたのは、その年頃の子供 の扱いに慣れておけという含みだろう。 和之助 まさか。 征一郎 いやいや……すぐにネを上げるかと思ったら、いつの間にかちゃんとなつかれ てしまったじゃないか。その点でも、きっと合格だぞ。 和之助 朋之進どのを採点の道具みたいに言うな。 征一郎 すまん。(笑う) ─── 征一郎は、道端の木につもった雪をばさっと振り落として、 征一郎 春になったら、朋之進どのを加瀬川に連れて行こう。 和之助 川釣りか。 征一郎 薫乃どのも誘ってな。 和之助 来るはずがなかろう。 征一郎 姉も弟も、家にひきこもっていてはよくない。 和之助 いや。薫乃どのも、時折は外出するようになった。 征一郎 へえ。……まだ、島田の娘の墓参に通っているのか。 和之助 そうとも限らん。和歌や能楽の会など……お父上の使いらしい。 征一郎 ふむ。ほとぼりがさめて、縁談でも探すつもりかな。 和之助 ………。 征一郎 いい女だからなあ。実際に会ってみれば、これなら、という家があるかもしれ んぞ。 和之助 ぶしつけだぞ。 征一郎 ならば、なおのこと今のうちに……一緒に出掛けておきたいもんだな。 和之助 え? 征一郎 思い出になるさ。 和之助 ………。 ─── 春。木暮家。薫乃は母の部屋にいる。 母 桜が開き始めたようですね。 薫乃 ええ、ようやく。 母 朋之進が、近々花見に出掛けるとか。 薫乃 はい。篠田村の駒ケ淵まで。 母 まあ、わざわざ。 薫乃 釣りをかねて行くそうでございます。 母 あの子が……釣り?(くすっと笑う) 薫乃 大郷様、小郷様のお二人が教えて下さる、と。 母 そう。 ─── 母は、ふと思案してから、 母 そなたも行っておいでなさい。 薫乃 え? 母 今年は、国元の桜を眺めておくのもよいでしょう。町なかでは、人目につきま しょうが……篠田村のあたりは、ひなびていてよいところですよ。 ─── 郊外、篠田村。藩内を流れる加瀬川が大きな淵になっているところで、周辺には 見事な山桜の木が満開になっている。和之助、征一郎、薫乃、朋之進は、木暮家の 奉公人らを連れて花見に来ていた。朋之進は岸に腰掛けて釣り糸を垂らしている。 そばで征一郎も竿を持ちながら介添えをしている。 朋之進 本当に、釣れますか。 征一郎 辻占と同じですな。当たるも八卦、当たらぬも八卦。 朋之進 小郷先生は? 和之助 遊びにかけては、征一郎の方が先生ですよ。 征一郎 そうそう。このさい、秀才なんぞ役には立たん。 ─── 和之助は苦笑して、ぶらりと散策を始めた。うららかな春の日で、木暮家の下男 たちは持参した弁当の番をしながら、木陰でうたた寝をしている。川に沿って歩く と、ふと薫乃と出会った。 和之助 あ。 薫乃 まあ。 和之助 お一人ですか。 薫乃 ええ。私がそばにおりますと、供の者が気を抜けませんでしょう? 和之助 そういえば、よく眠っていたな。 薫乃 ここまで朋之進を背負って来たのですもの。 和之助 それに、大荷物と。 ─── 二人は同時にくすっと笑った。数人分の弁当を、木暮家伝来の立派な重箱に詰め てきている。 和之助 あんなに食いきれるかな。 薫乃 大郷様がおいでですから。 和之助 は、は。 ─── 薫乃は、川端の桜をあおいだ。 薫乃 このあたりは、私も朋之進も初めてです。 和之助 川遊びも? 薫乃 ええ。……ご城下とは、花にもまた違った風情がございますね。 和之助 風情、か。そんなことを考えたことはなかったな。 薫乃 鳥の声が近くて……何でしたかしら。「春山一路、鳥空しくなく」という詩が ございましたね。確か、川べりの風景ではございませんでしたか。 和之助 ああ。李華でしょう。「春行して興を寄す」という詩です。 薫乃 覚えておいでに? ぎよう せいせい かんすい ま おの 和之助 「宜陽城下草萋萋、澗水東流して復た西に向かう。芳樹人無くして花自ずから 落ち、春山一路、鳥空しく啼く」。 薫乃 花おのずから落ち……鳥空しく啼く。なぜ空しいというのでしょう。 和之助 ただ春の山河を詠んだのではなく……宜陽というのは唐代に栄えた城下町で、 その地が乱によって荒廃し、今は訪れる人の姿もないことを嘆いたのではない か、といいます。「国破れて山河あり」という詩に近い。 薫乃 春のさかりの風景なのに……なんだか寂しい詩ですこと。 和之助 唐詩には、世の憂愁をうたったものが多いですからね。 薫乃 でも、芳樹の花は人に見られるために咲いているのではなく、山鳥は人に聞か せるために啼くのではない……そうではございませんか。 和之助 なるほど。そう考えれば、人の世の盛衰に関わらず、自然はその営みを続けて いる、という意味にもとれる。花が咲いて落ちるのも、鳥が啼くのも自然の道 理であり……それを空しいと感じるのは、人間の勝手な思い入れにすぎないの かもしれない。 薫乃 ええ。同じ花を見、鳥の声を聞いても……それをもの哀しいと感じる時もあれ ば、美しいと思う時もあるのではないでしょうか。 和之助 その人の気持ち次第、ということですか。 薫乃 ええ。たとえば、この加瀬川の流れも……小郷様たちにとっては子供の頃から 慣れた遊び場所であっても、私には新鮮な眺めに見えますわ。連れて来ていた だいて、ようございました。 和之助 そう、ですか。 ─── 和之助はふと、薫乃の微笑に照れたように、身軽く水辺におりた。水に手を入れ ると、 和之助 まだ冷たいな。 薫乃 そんなに? 和之助 ええ。夏になれば、あの駒ケ淵で泳げるのですがね。 薫乃 深いのでしょう。 和之助 ええ。足がつかなくて、こわいですよ。だから、小さいうちは浅いところの水 遊びから始めるんです。年長になって泳ぎが達者になってくると、淵に入るの を兄たちから許されるようになる。そうなると……一人前になったような気が したものです。 薫乃 男の子の遊びですね。 和之助 村の子供は、女でも泳ぎますよ。 薫乃 まあ。 和之助 女の子は逆に、恥ずかしがって泳がなくなると、一人前になった証拠だそうだ が。 薫乃 和之助様も、その子たちとご一緒に川遊びをなさいましたの。 和之助 ええ。 薫乃 私は、泳いだことがございませぬ。ご城下の川も岸から眺めるだけで。 和之助 それは……村娘とは育ちが違う。 薫乃 ま。 ─── 薫乃はふと、うらやましそうな顔をした。 和之助 ここへ、おりてみますか。 薫乃 え?……ええ。 ─── 薫乃はおっかなびっくりという足取りで石の上を歩いてきた。 薫乃 きゃっ。 ─── ふらついた薫乃の手を、和之助はつかんだ。 和之助 失礼。 薫乃 ……いいえ。 ─── 薫乃は川岸に立って、和之助がしたように清流の中に手を差し入れてみた。 薫乃 まあ、本当。 ─── 薫乃は水の冷たさに肩をすくめて笑った。 ─── 釣り場である淵まで、和之助と薫乃が戻ると何か騒いでいる。 征一郎 まだまだ、合わせてっ。 ─── 朋之進の竿に、魚がかかったようだった。征一郎が後ろから抱き留めながら、竿 の上げかたを教えている。 下男 坊っちゃま、しっかり。 征一郎 こりゃ、大物だぞ。 ─── 魚影がきらきらと光りながら二人の足元に跳ね上がった時、歓声が上がった。 朋之進 やった! ─── 帰り道。朋之進は疲れて、征一郎の背中におんぶされて眠りこけている。 下男 大郷様、本当に私どもが…… 征一郎 いいさ。俺のほうが、力は強い。 和之助 そう。それに、帰りの荷物を増やした本人だからな。 征一郎 弁当は減らしたぞ。 ─── 確かに、重箱の中身は軽くなったが、かわりにびく魚籠一杯の獲物が増えている。和 之助と下男が分けて持つほどだった。 4 ▼ ▲ ─── 藩校の朝。和之助と征一郎は、門前に立っている。 征一郎 来た。 ─── 朋之進が、下男に背負われて登校してきたのである。 征一郎 おおーい。 ─── 朋之進は二人に気づいて、下男の背をおりた。杖をつきながら、おぼつかない足 取りで歩いてくる。 征一郎 ようやく、だな。 和之助 ああ。 ─── 和之助は、思わず胸が熱くなっている。 ─── 師範の大森は、にこにこしている。 大森 小郷。おぬしも来てみろ。 和之助 え。 大森 初等組師範の山崎には話してある。 征一郎 先生、私は。 大森 おぬしはいい。 ─── 征一郎は、ちぇっという顔をした。 ─── 和之助と大森は、十才の級の教室の後ろに立った。子供たちは、皆興味津々とい う顔で、座席の朋之進を見ている。 山崎 本日より、木暮朋之進がこの組へ入ることになった。 ─── 朋之進は、気恥ずかしそうにしている。 山崎 朋之進は見ての通り、怪我をして皆のように身軽には動けぬ。しかし、一時は 全く歩けぬほどであったものが、努力を重ねて一人で立って歩けるまでになっ た。同じ年頃の皆に負けまいと、上級組の小郷和之助に教えを受けてたった一 人で学問もつんできた。途中から組のなかに入ることはなかなか勇気のいるこ とだが、今日からは同じ義学館の仲間として睦まじくやってもらいたい。 ─── 子供たちから拍手が起こった。朋之進は心持ち頬を染めて、頭を下げている。 大森 小郷。おぬしから言っておくことはないか。 和之助 え。私が? 山崎 そう。皆、最上級組の小郷和之助だ。たいへんに優秀な先輩だぞ。 ─── 子供たちの目が一斉に、和之助を振り返った。 和之助 ………。 ─── 朋之進の目が、ひときわ熱く見つめている。 和之助 私も、まだ皆と同じ修行中の身で、偉そうなことは言えないが……。朋之進ど のはたいそうな頑張り屋で私にも見習うべきところがたくさんある。学問では 皆に遅れないように、と今日までやってきたつもりだ。だが、いくら本を読ん でも、義学館に通わなくては得られないものがある。 ─── 子供たちは、しんとしている。 和之助 それは、同じ子供どうしの友達だ。皆が、ぜひ朋之進どのと友達になってほし い。私から望むことはそれだけだ。 ─── 大森の自室。 大森 なかなか、簡潔でいい演説だった。 和之助 昇級の考試より緊張しました。 大森 は、は、は。 和之助 しかし、山崎師範の組であればひと安心です。 大森 ……先日、木暮殿に「よい師匠を紹介してくれた」と礼を言われた。わしも鼻 が高いぞ。 和之助 私は、何も……。 大森 謙遜だな。木暮殿はおぬしのことを今時しっかりした若者だ、とほめておられ たぞ。本当に、おぬしの将来のことも考えて下さるかもしれん。 和之助 それが目的でお引き受けした話ではございませぬ。人に、出世目当てで御番頭 の家にとりいったと思われるのは心外です。 大森 ふむ。確かに、人の噂はこわいものだからな。 和之助 ………。 大森 当の木暮家も過去にあらぬ噂でいやな目にあっている。聞いたことはあるか。 和之助 いいえ。 大森 しかし、朋之進どののことは久々の吉兆である、と喜んでおられた。ご次男の 縁組もまとまる気配だし、あとは次女の薫乃どのの身のふりかただけだという が……。 和之助 ………。(どきっとする) 大森 城下一といわれた美人だそうだが、すでに二十歳になるからな。 和之助 は……。 た お 大森 もっとも、高嶺の花で今まで誰も手折れぬらしい。ははは…… ─── 和之助の胸に、とっくに承知しているはずの「高嶺の花」という言葉が棘のよう に刺さった。 次回 (三)へつづく 5 ▲ |