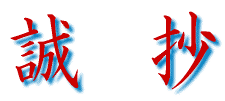 |
| 第 17 回 |
★緑色のマークをクリックすると、前後の場面にジャンプできます。
通常、読むときはスクロールしてください。
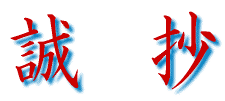 |
| 第 17 回 |
| こぬか雨 |
| (八) 乞食と直参 |
| 1 ▼ ─── 慶応三年の春、新選組から大量の離反者が出た。といっても表面上は局長了承済 みの「分派」であったが。 和弥 嘘だろう。 隊士1 それが、嘘じゃないから驚きなのだ。 和弥 あの、斎藤先生が…… ─── 和弥はその話を聞いて、唖然とした。かねて思想的に近藤、土方とは相いれぬと いわれていた参謀の伊東甲子太郎が、徒党を組んで新選組を分離独立して、薩摩の 庇護下に入り、「御陵衛士」という隊を作る。そこまでは噂通りであったが、なん とその中に三番隊長の斎藤一もついて行くという。 和弥 斎藤先生が近頃、伊東参謀の仲間と親しいとは聞いていたが……あの人は徹底 して中立、いやどちらかと言えば局長派の人間なのだと思っていた。伊東派と 違って新選組の最古参……生え抜きではないか。 隊士1 それなら、八番隊の藤堂先生も同じだろう。 和弥 藤堂先生は伊東参謀と剣の同流で、もともとの結びつきがある。しかし斎藤先 生がわざわざ分離派に飛び込むなどと…… 隊士2 何、もとを正せばつまらぬことさ。 和弥 何が。 隊士2 斎藤先生は、近藤先生の股肱として働いてきた。それが、自分の色である祇園 の芸妓が、ある時金につられて局長に寝返ったらしい。 隊士1 女の取り合いか。 隊士2 そのことで、局長と斎藤先生がもめたらしいぜ。寝返りには、寝返りをもって 報いたわけだ。 隊士1 へえ。人は見かけによらんな。 隊士2 日頃まじめな人ほど、女に関しての思い込みが激しかったりするのさ。なあ、 小木。 和弥 えっ。 隊士2 おぬしもどこかに思い込んだ女の一人くらい、いるんじゃないのか。 和弥 冗談を言うな。こんな時に…… ─── 裏庭に出ると、その斎藤一が小者の久助と無駄話をしながら、焚き火をしていた。 和弥 斎藤先生。 斎藤 やあ。 和弥 何を燃やしておられます。 斎藤 持っていってもしかたのないものさ。 ─── 斎藤は、不要になった紙類の他に、歴戦の証しでもある「誠」の文字入りの袖章 や鉢巻きなどもくべようとしている。隊服もある。 和弥 そんな。燃やすのなら、私がいただきます。 斎藤 馬鹿だな。私のなんかもらったってしょうがないよ。そんなことが知れたら、 近藤先生たちがいい顔をしないだろう。 和弥 しかし……。 斎藤 ゴミと一緒に捨てるのはあんまりだからな。こうすれば、久助の焼き芋の役に は立つ。 久助 芋なんか、焼いてしまへんで。時期が違いますがな。 斎藤 そうか。 久助 せっかく大事な思い出のつまったもん……勿体ない。 斎藤 何、こうして……煙になって天に返してしまえばいいんだ。 ─── 斎藤は、隊服などをくるっと丸めて、火に投げ入れた。 和弥 あ……あ。 斎藤 何も持たない方が、さばさばするさ。 ─── 和弥と久助は、しばし呆然として、浅葱の羽織が燃えるさまを見つめている。 和弥 斎藤先生。 斎藤 何だね。 和弥 少し、お話が……。 ─── 久助は和弥の顔をちらっと見て、さりげなく場を外した。 和弥 なぜ、斎藤先生まで分離に加わったのです。 斎藤 ああ……そのことか。 和弥 分離などといっても、実態は脱盟でしょう。今後、新選組と伊東先生の一派と の間で、おかしなことになりはしませんか。 斎藤 (ふっと笑って)君は、頭がいい。 和弥 おやめ下さい。私は……上洛以来、斎藤先生の三番隊だったからこそ、安心し て働いて来られたようなものです。先生ほどの剣客が伊東参謀の甘言につられ て、わざわざついて行くことはない。他の加盟者は皆、伊東先生の取り巻きば かりではありませんか。彼らは、実践よりもっぱら議論を重んじる弁舌の徒で す。しかし、先生は不言実行を絵に書いたような方だ。毛色が違いすぎて、い づらくなってしまわれるのではありませんか。 斎藤 (苦笑して)確かに、私は剣術以外に取り柄のない男だ。 和弥 そんなことはありません。私は……斎藤先生を尊敬している。黙っていても信 頼のおかれる隊士になりたい、と思ってきました。先生が新選組を離れること は、残念でなりません。 斎藤 ありがとう。 ─── 斎藤は、ふわっと笑みを浮かべた。 斎藤 しかし、思うところあって決めたことだ。引き返すことはできんよ。 和弥 ………。 斎藤 小木君。私の後任の三番隊長……無理なら、せめて伍長になりと、君を推薦し ようと思っていた。 和弥 え。 斎藤 しかし、新選組と袂を分かって出ていく私が、とやかく言い残していく立場で はない、と思って……やめた。悪く思わないでくれ。 和弥 そんなことは……望んでいません。 斎藤 その方がいいかもしれん。 ─── 斎藤はかがんで、棒で火を掻き起こしている。 斎藤 君は、頭がいい。腕も立つし、外見もいい。人の上に立って恥じることはない と思う。……だが惜しむらくは、君に欠けていることが一つある。 和弥 は? 斎藤 ソツがなさすぎる、という点かな。君には、清濁合わせ飲む、といったふうな ……物事の裏表を包容するふてぶてしさがない。よく言えばまっ正直、悪く言 えば懐が狭い。 和弥 (頭を掻いて)……おっしゃる通りです。 斎藤 一介の平隊士としてならばそのままでいいが、幹部になると、見聞きしたくな いようなことも色々としなきゃならなくなるよ。 和弥 斎藤先生。 斎藤 は、は。つまらんことを言った。 ─── 斎藤は立ち上がって、ふと煙を見上げつつ、 斎藤 春の焚き火というのは、何となく間抜けなものだな。 ─── 伊東甲子太郎ら十六名は、三月二十日に新選組を去った。 2 ▼ ▲ ─── 新選組はその年の初夏、西本願寺の仮屯所を出て、花昌町の広壮な新屯営に引っ 越した。そのつくりは大名屋敷顔負けの豪華さを誇ったという。 和弥 (しかも、ご直参か。) ─── この年六月、新選組隊士一同は正式な幕臣に取り立てられている。局長の近藤は 見廻組与頭格としてお目見得以上の旗本となった。以下の隊士も、役職に準じて 身分をもらっている。 和弥 (嘘のような話だ。たった四年の間に、一農民の子が数百石取りの旗本にまで なったというのは……聞いたことがない。) ─── 和弥は、ま新しい畳の匂いがする平隊士の部屋で、一人寝ころんでいる。 和弥 (俺だってそうだ。数年前には、部屋住みの身で田舎にくすぶり……将来、職 につけるかどうかもわからずにいた。それが……あの御番頭の木暮市右衛門殿 またもの ですら、たった今会えば「陪臣」として頭を下げさせることが出来る。これは 大変なことかもしれない。) ばいしん ─── 幕府体制下では大名の家臣は全て将軍家から見て陪臣(家来の家来)であり、禄 高の違いはどうあれ、将軍家直参の方が一藩の家老よりも格が高い。 和弥 (史学の講師が言っておられた。古来、急激な栄華を得て永く世に残った者は いない、と。……おごれる平家にならなければいいが。) ─── 和弥の頭には、藩校きっての秀才といわれた、まともすぎる教養がくっついてい る。他の隊士たちのように、手放しで喜ぶことは出来なかった。 ─── 別の日の午後。和弥は、五条橋の上を同隊の数人と歩いている。橋の上に、乞食が 一人、ムシロをかぶって寝そべっていた。 隊士1 おい、あの乞食……武士ではないか。 隊士2 本当だ。頭の格好からすると、浪人者らしいな。 隊士1 尋問してみるか。 和弥 後ろ暗いところがあれば、昼間っから我々の通り道におらんだろう。 隊士1 わからんぜ。 ─── 隊士1、ぼろぼろの着流しにぼさぼさの髪と不精髭を伸ばした浪人乞食に近づき、 隊士1 おい、乞食。顔を上げろ。 男 ………。俺のことか。 隊士1 こんなところで商売されては、往来の邪魔だ。 男 乞食ではない。 隊士1 ならば、何の目的でここにいる。 男 動くと腹が減る。 隊士1 何。 男 ここに寝ていると、時々小銭を投げてくれる者がいるからな。 隊士1 それが、乞食だというのだ。(笑う) ─── 乞食はむくりと起き上がって、大きくあくびをしながら伸び上がった。 男 う、うあ……あ。うるさいことだ。新選組は、浪人と見れば昼寝までいちいち まぐそ 取り締まって歩くのか。馬糞にむらがる蠅でもあるまいし。 隊士1 何をっ。 ─── 和弥たちが近寄った。 和弥 おい。もういいじゃないか。その男、丸腰だ。 ─── その時、男がすっとんきょうな声を上げた。 男 あっ! 和弥 え? 男 和之助。和之助じゃないか。 和弥 何? 男 俺だ。 ─── 男は、伸びた前髪を手のひらでかきあげてみせた。和弥は仰天した。 和弥 ……征一郎か! 征一郎 おお。いやあー、久しぶりだな。 ─── 征一郎は、黒ずんだ顔に真っ白な歯を見せ、和弥の両肩をつかんでいる。 ─── そのまま和弥は、征一郎と二人で歩いている。 征一郎 仕事の途中だったんだろ? 和弥 いいんだ。用事は終わったし、あとは仲間が隊に届けておいてくれる。 征一郎 そうか。どこへ行く? 和弥 その格好ではどうにもならぬ。俺の馴染みの家に行く。 ─── そう言って連れられて来た家を見て、征一郎はぽかんとした。 征一郎 本屋か。なんだ、色気がないな。 和弥 ここの親父が、俺と懇意にしている。まずはその体をさっぱりしろ。 征一郎 さっぱり……。 和弥 におうぞ。 征一郎 そうか。 ─── 中へ入って行くと、本屋の老夫婦は真っ黒な征一郎の姿を見て目を丸くした。 店主 おや、まあ……。 和弥 すまん。私の、古い友人なんだ。 店主 そうどすか。さながら……弁慶と九郎判官どすな。 征一郎 はっはっは。 和弥 今、そこで偶然会ったのだが……この格好では飯屋にも連れていけん。悪いが 体を洗わせてやってくれないか。 店主 へえ、へえ。よろしおす。小木はんのお友達どしたら……おい。 女房 へえ。ほなら、おぶ、たんと沸かしてきまひょ。 征一郎 この陽気だ、水でいい。 女房 そやけど、おぶで流したほうが、さっぱりしやはりますし。 和弥 すまない。 女房 いいえ。そのなりでは……湯屋にも入れてもらえまへんやろ。あてが、垢ごと こそげ落としてきれいにしてさしあげます。 征一郎 ははは。 店主 そやけど、大きいお人や……わしの着物では間に合いまへんな。ほな、ちょっ と古着でも買うてきまひょか。 和弥 私が行こう。 店主 いえ、馴染みの店がおすさかいに……。小木はんは、上がって待ってとくれや す。 和弥 すまん。では、これで適当なものを。 ─── 和弥は店主に財布を渡した。 ─── 征一郎は本屋の庭を借りて行水をし、髭を剃って、髪をなでつけてきた。 和弥 ようやく、昔見た顔になったな。 征一郎 体を洗ったのは何日、いや……何十日ぶりかな。 和弥 汚いな。 征一郎 おぬしはずいぶんいい着物を着て、綺麗ななりをしているじゃないか。新選組 もとうとうにわか旗本にまで成り上がったというのは本当らしい。 和弥 相変わらず、口が悪いな。 征一郎 生まれつきだ。 和弥 何か食いに行こうか。 征一郎 すまんな。だが遠慮はしないぜ。 ─── 料理屋の小座敷に連れていき、征一郎の食欲を見て、和弥は唖然とした。 和弥 腹をこわすなよ。 征一郎 そう簡単にこわれる腹じゃない。 和弥 なぜ、京都にいる? 征一郎 なぜって、お前と同じ脱藩さ。 和弥 婿に行って、小納戸役の跡取りになったんじゃなかったのか。 征一郎 行ったさ。 和弥 では、なぜ。 征一郎 やはり駄目だな。俺には、婿養子も城勤めも向いておらん。 和弥 それは、そうだろうが…… 征一郎 あの、多紀。俺の女房だが……とんでもない女だった。あんなのと何十年も暮 らすくらいなら、のたれ死にした方がましだ。 和弥 子供は? 征一郎 いる。男の子だ。 和弥 (驚く)いるのか。 征一郎 ああ。何故か、俺は作った覚えがないのに、ちゃんといる。 和弥 え? 征一郎 他に男がいたのさ。 和弥 不義か! 征一郎 どういうのかねえ……。そうでなくとも、一緒になってすぐ、ああ、俺はこの 女とは駄目だ、と思った。あれなら、中山町の女郎どもの方がよっぽどやさし くていい女だったと思うぜ。器量はいいが性根は最低で、男遊びは結婚前から ちょくちょくやっていたらしい。 和弥 信じられんな。 征一郎 さすがに親も勘づいて、早々に婿を見つけてやろうと思ったらしいのさ。とこ ろが多紀は好みのうるさい女で、自分のことは棚に上げていろいろと条件を出 したらしい。婿は人に自慢できるような男でなければいや、だとさ。 和弥 ほう。 征一郎 それで、その頃誠武館道場で免許をとったばかりの俺に白羽の矢が立ったとい うわけだ。 和弥 なるほど。 征一郎 しかも、多紀は最初おぬしの方がいいとごねたそうだぜ。 和弥 えっ。 征一郎 父親がその話を先生に打診したところ、「小郷は腕も立つ上に藩校でも師範に 取り立てるという噂があるほどの秀才で、他にもあまたの口がかかるだろうか ら、承知するかどうか難しい。」と言われて、他に取り柄のない俺に乗り換え たというわけだ。馬鹿にした話じゃないか。 和弥 俺は、知らなかった。 征一郎 しかも、しゃあしゃあとそのことを俺にいいやがった。「あなた様は、お背も 高くて男ぶりもよく、道場の若手では一番お強い、と城下の娘たちが騒いでい ると聞きました。ですから、わざわざ婿にもらってさしあげたのです。小郷様 では競争相手が多くて、もしも断られたら私の誇りに傷がつきますゆえ」だと さ。いくら家付き娘でも、高慢ちきにもほどがある。頭に来てしばらく抱きも せずに放っておいたら、いつの間にか腹に子が出来たというじゃないか。これ が我慢していられるか。 和弥 そのこと……他言したか。 征一郎 言わん。生まれてくる子供には罪がない。 和弥 なるほど……。では、その子はお前の息子として育っているのだな。 征一郎 ああ。だが今頃は、多紀がさっさと新しい父親でも見つけているだろうさ。 和弥 ……お前なら、女房子供が出来て幸せにやっているものだと思っていた。 征一郎 お前こそ、なぜだ。 和弥 え? 征一郎 お前が周囲の誰にも告げずに脱藩した時は、そりゃあ驚いたぜ。この俺にすら ひとっことも言わなかったものな。 和弥 すまん。……あの時は、事情があったのだ。 3 ▼ ▲ ―――征一郎はその時になってようやく飲み食いをやめ、旧友の顔をのぞきこんだ。 征一郎 ふうん。今ごろ新選組あたりでうろうろしているところをみると、密約に加わ ったというわけではなさそうだな。 和弥 密約……。 征一郎 お前、脱藩する直前にしばらく、扇町の山岡塾に通っていたろう。それだけじ ゃない。末広町の松本由之進の私塾なども。 和弥 ああ。 征一郎 山岡塾の金井修平、宮田助五郎などは牢に入れられたぜ。 和弥 えっ。 征一郎 山岡儀左衛門、金井、宮田などの連中は流行りの勤皇倒幕論者で、藩の佐幕政 策を不服として当時の要人たちの暗殺を企てていた。いわば、政変を起こして 藩政権の転覆をはかろうとした、というわけだな。 和弥 その計画は事前に阻止された、と聞いたが。 征一郎 お前がいなくなったあと、彼らの謀議がばれて牢屋入りの者が七人も出た。 和弥 ……俺は当時、何も知らなかった。 征一郎 そうか。ひと頃はお前が彼らの仲間に加わったものの、暗殺は潔しとせず、と 反対して、一人だけ脱藩したのだという噂が流れた。狙われている相手に、急 を告げにいったのでは、という者もいた。 和弥 その相手というのは、誰だ。 征一郎 当時の中枢にいた家老たちはもちろんだが、殿のふところ刀といわれる江戸留 守居役の西条源吾……あれこそ君則の奸だ、といって真っ先に血祭りにあげら れるところだったらしい。 和弥 ………。 征一郎 お前は木暮殿の内意を受けて江戸に立ったのではなかったのか。 和弥 違う。 征一郎 ふうん。では、小郷の家の処分が軽く済んだのは、単に木暮殿の好意だったと いうことか。 和弥 俺の家が? 征一郎 ああ。小郷家は親父さんの蟄居で済んだはずだ。その後親父殿は隠居して兄貴 の代に変わったぞ。 和弥 皆、無事で暮らしているのだな。 征一郎 ああ。脱藩の処分が名目だけで終わったのは、木暮の御番頭が助け船を出して くれたからだと聞いている。 和弥 木暮殿が……。 ─── 和弥は、いまさらながらあの温厚な重役を裏切ったことを恥じた。 征一郎 お袋さんは、お前が家を出たわけがわからん、といって初めは悲しんでいたが 暴挙に加わって牢送りにならなかっただけよかった、と安心したらしく、また 孫の世話で忙しくしている。ああ、兄上夫婦の二人目は女の子だったぜ。 和弥 そうか……いや、家族のことだけは心残りだったが、それを聞いて安心した。 征一郎 ご挨拶だな。親友の俺を置いてけぼりにしたくせに。 和弥 すまなかった。 征一郎 これは俺のよけいな勘繰りだが……お前が出奔したのは、木暮の薫乃どのに関 係があるんじゃないのか? 和弥 ………。 征一郎 やはりな。薫乃どのが江戸へ送られるのが辛かったんだろう。あの頃のお前は どこか普通ではなかった。 和弥 ……薫乃どの、か。 征一郎 お前、薫乃どのに惚れていたのか。 和弥 もう、昔のことだ。 征一郎 そうか。しかし……薫乃どのは今、この京にいるらしいぞ。 和弥 えっ。 征一郎 藩の内命を受けてどこかの京屋敷に勤めることになった、と聞いたが。 和弥 本当か。 征一郎 わからん。俺が放浪に出る前に聞いた噂だ。あの人はあれで、なかなかの才女 らしい。深窓の令嬢として世間に隠れていた時はわからなかったが、江戸のお 屋敷に勤めてからは、奥向きでまたたく間に頭角を表したそうだ。さすがに、 父親の血は争えんな。藩に請われて京都へ来た、となると……やはり、政治む きの役目を受けているのかもしれん。国元の騒動でも薫乃どのがいろいろな情 報を探るに役立った、という話があったからな。 和弥 ………。 ─── 和弥は、最後にしのび会った時の薫乃の言動を思い出している。 薫乃 (回想)私には従ってくれる者があります。……祭礼の当夜まで、誰が誘いに 来ても、必ずお断りになって下さい。 ―── 和弥がぼんやりと押し黙ると、 征一郎 和之助? 和弥 (はっとする)あ、いや……今は、小木和弥という名前を名乗っている。 征一郎 小郷和之助ではないのか。 和弥 ああ。新選組に入隊する時に、改名した。 征一郎 ……新選組の、小木和弥ねえ。 和弥 馬鹿にしたような物言いだな。 征一郎 天下のご直参を馬鹿にできるか。(笑う)大した出世だな。 和弥 いやな奴だな。 ─── 和弥は、ぐいっと酒をあおった。 和弥 征一郎。お前は、今後どうするというあてはあるのか。 征一郎 さあな……無一物でぶらぶらとさまよっているのにも飽きたし。 和弥 両刀まで売っぱらったらしいな。 征一郎 ああ。飯に代えた。刀はなくても生きていけるが、飯は食わなければ死ぬ。 和弥 ………。 征一郎 坂本龍馬の亀山社中にでも入ろうかと思っている。 和弥 (驚く)亀山……海援隊か? 征一郎 うむ。あそこは浪人者を集めて、面白いことをやっているらしい。 和弥 馬鹿。俺に言うな。 征一郎 何故だ。 和弥 土佐脱藩の坂本といえば……幕府に追われるお尋ね者だ。新選組にとっては、 斬って捨てるべき相手だぜ。 征一郎 へえ……そうか。 ─── 征一郎はけろりとしている。 和弥 俺のところへ来い。お前の腕なら、入隊できるかもしれぬ。試験を受けられる ように頼んでやるよ。 征一郎 せっかくだが、それは御免だな。 和弥 なぜ。 征一郎 俺には、性に合わぬ。新選組では、城勤めよりもさらにやかましく規則、規則 で人を縛りつけるというじゃないか。 和弥 城勤めのような形式ばった決まりではない。要は、武士として恥じぬことを心 がけよ、という一点さえ守ればいいんだ。 征一郎 斬って生き延びるか、斬られて死ぬか……それだけしか選択できぬということ だろう。俺はいやだな。 和弥 ………。 征一郎 お前、どことなく顔が変わったと思ったら、人を斬った顔だな。 和弥 征一郎。 征一郎 お前が選んだ仕事ならそれでいい。ただ、俺にはとうてい勤まらぬ、と言った だけだ。 和弥 惜しいな。 征一郎 すまん、悪く思うな。 和弥 仕方がない。住まいは何とか俺が考えてやる。 征一郎 ありがたい。そうと決まったら、飲もう。 和弥 いい気なものだ。言っておくが……土佐の坂本と海援隊には近づくなよ。 征一郎 ………。 和弥 お前を斬るような羽目にはなりたくないからな。 征一郎 わかった。 4 ▼ ▲ ─── 征一郎は、書店「栄林堂」の居候となり、筆耕や代書などの内職をして暮らすよ うになった。和弥が非番の日などに立ち寄ると、机の前に巻紙を書き散らしている 征一郎に会った。 和弥 どうだ、慣れたか。 征一郎 まあまあだ。 ─── 店主夫婦は、征一郎が来て喜んでいるらしい。 女房 うちとこは、子供がおへんし……若い人に来てもろうて、楽しおす。力仕事も いやがらんと、気さくにしとくれやすし……うちの人と二人でいるより、頼も しおすえ。 店主 それに大郷はんは、あれでなかなか文筆の才がおまっせ。 和弥 ほう。 店主 とりわけ、女子はんの文の代筆が上手どすな。ほんまに、女子になりきったよ うに可愛らしい、それでいて艶っぽい文句をいろいろと考えつかはります。あ んなんもろうたら、男はんもぽうっとなりまっしゃろなあ。 和弥 人は見かけによらんものだ。 店主 大郷はんが、ほんまに侍を捨ててもかまへん、いわはるのやったら……可愛い 嫁はんでも見つけて、ずっといててくれたかてええ。うちのもそう言うてます のや。 和弥 夫婦養子か。おい征一郎、どうする。 征一郎 いやあ、当分女房はこりごりだ。 ─── 笑い声がおきる。 次回 (九)へつづく 5 ▲ |